書評
『バイ貝』(双葉社)
資本主義の無間地獄
日々の暮らしは売買の繰り返しである。資本家でもない限り、労働力を提供して稼いだ金でモノを買い、買ったモノの代金を支払うためにまた働く。現代人は生活必需品だけでなく、不要不急のモノでさえ買う。そうした消費行為を、フランスの社会学者ボードリヤールは「記号消費」と呼んだ。日本でもバブル経済期にこうした消費はもてはやされた。長期デフレと不況が続いたこの20年の間に、日本人の消費スタイルはしみったれたものになった。だがそんな時代にも資本主義は人間の感情に収支決算を迫る。本書は「鬱(うつ)と銭のバランスシート」の帳尻合わせを日々迫られている、という強迫観念にとらわれた男が語り手となる物語である。
冒頭で主人公は言う。「ドストエフスキーは、貨幣は鋳造された自由である、と書いた」。だが「鋳造された自由」を得るための労働が、彼をさらに鬱にする。銭を稼ごうとすれば鬱がたまり、鬱を散ずるにはモノを買う銭がいる。
マイナスに傾いたバランスシートを改善しようと、彼はホームセンターへ出向きまず草刈り用の鎌を、ついで鉄のフライパンを購(あがな)う。後者は当初、好調に鬱散じに貢献する。だが資本主義はそれほど甘くない。結局のところ男のもくろみは外れ、バランスシートは悪化の一途をたどる。
この無間地獄から脱するには、純粋な楽しみとしての「趣味」を持てばいい、と男は思う。そのためにモノを買う必要はない。なんとなれば、彼はすでにコンパクトカメラを所有している。にもかかわらず、彼はいつしか、「小さくてメカ然としてやや価格が高い」新しいデジタルカメラが、必要であるような気がしてしまうのだ。
人を食ったような題名は「Buy=買い」という言葉遊びだろう。文学もまた「商品」でしかありえない資本主義のもとでは、小説家はこんなナンセンスで一矢を報いるしかないのかもしれない。
初出メディア
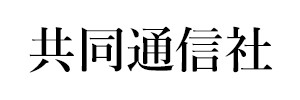
共同通信社 2012年5月10日
ALL REVIEWSをフォローする









































