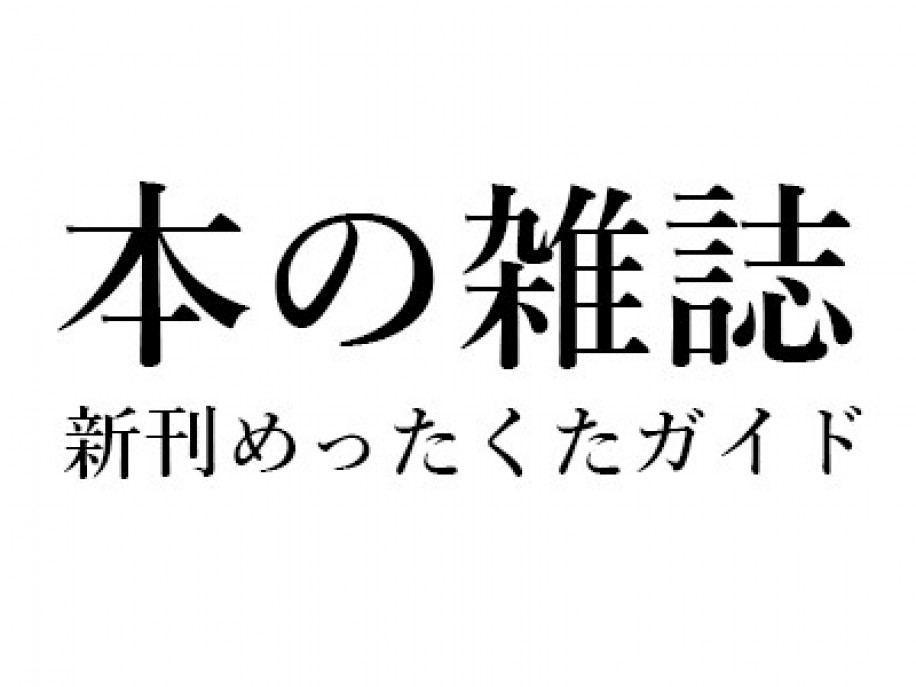選評
『ラス・マンチャス通信』(角川グループパブリッシング)
日本ファンタジーノベル大賞(第一六回)
大賞=平山瑞穂「ラス・マンチャス通信」、優秀賞=越谷オサム「ボーナス・トラック」/他の候補作=堀井美千子「池尻ウォーターコート」、原田勝弘「この晴れた日に、ひとりで」/他の選考委員=荒俣宏、小谷真理、椎名誠、鈴木光司/主催=読売新聞東京本社・清水建設 後援=新潮社/発表=「小説新潮」二〇〇四年九月号
おめでとう、ご精進を
「道なき道の果てには何があるか」という壮大な謎、これを究めようとする三人の登場人物の冒険を、ずいぶんな悪文で綴(つづ)ったのが『この晴れた日に、ひとりで』(原田勝弘)である。どんな悪文か。たとえばこうだ。ヨシュアは男の家に住み続け、畑を受け継ぎ、田畑を耕し、その場所で静かに時を刻み始めた。(第三章の3)
ヨシュアが、つまり人間が時を刻んだりするだろうか。こういう文章に行き当たるたびに苛立(いらだち)、ついでに腹も立てたが、やがて馴染むにつれて、悪文でしかこの内容を書くことはできなかったのではないかと、考えが変わってきたのは、まことにふしぎである。
物語の語り手の「私」は、どうやら天地の創造主……もっといえば、天地を満たす普遍的意志のようでもある。全能の語り手なのでつい、話がべらぼうに大きくなったり、人間には解りにくいことばを使ってしまったりするらしい。そう考えれば、これはじつによく計算された悪文ということになる。
一、道なき道の果ての探求。二、死と狂気で囲われたこの世界の構造についての考察。三、ことばで「無」を表現できるかどうかについての実験などなど……古今東西の知性がついに解き得なかった問題に、作者が一応の解答を出しているのも、すごいといえばすごい。たとえば、三の解答はこうだ。ことばだけでは「無」は表現できないが、そこに擬人法というレトリックを使って、ことばに立体感を与えれば、表現は可能になる。
一の解答の、道なき道の果てにはソラがあったというのも、ばかばかしいが、しかし、このばかばかしさへ辿(たど)り着くまでのしどろもどろの思考を、作者は全身全霊をこめて言語化しており、しかも、ときには成功している。ことばを唯一の武器にして世界の成り立ちに肉薄しようとする作者の壮烈な意欲を買って、評者はこれを第一位に推したが、選考委員のみなさんの賛同を集めることはできなかった。
『池尻ウォーターコート』(堀井美千子)は、又聞(またぎ)きの手法を巧みに駆使した小佳品である。文章に癖がなく、点景人物には陰影があって、とても読みやすい。だが、差し当り二つの不満を持った。第一に、全体に淡すぎる。第二に、せっかく水を主題にしているのに、その主題の追求が淡泊にすぎた。もっとたくさん材料を揃えて、読者を圧倒していただけたらよかったのに。
『ボーナス・トラック』(越谷オサム)は、幽霊物の上作(じょうさく)である。幽霊物では、その出現と退散がなによりむずかしいが、作者はのびのびとこの二つの難関を乗り越えており、そこに作者の才能を窺うことができる。ただし、第一位に推さなかったのは、幽霊の恨みの量の少なさと、謎解きの安易さに、ちょっと落胆したからである。たくさん書けば、その分だけ伸びそうな向日性の資質の持ち主のようだから、これからもどしどし仕事をしていただきたい。
『ラス・マンチャス通信』(平山瑞穂)では、冒頭の「畳の兄」に烈しい衝撃を受けた。語り手の「僕」は、姉と力を合せて、アレを殺すのだ。アレとは兄のことである。こうして弟殺し兄殺しという神話的な物語枠を設定した以上は、この姉弟がどのような流竄(るざん)の運命を辿るか、それが読者の最大の関心事になる。そこで当然、それを書くのが作者の大切な務めにもなる。けれども、作者の筆は「僕の流竄」にあまりにも多くを割(さ)きすぎた。僕が語り手をかねているから仕方がないけれども、それにしても姉の気配が薄い。作者がつぎつぎに繰り出す挿話は、いずれもよくできているが、やはり大事な二本の芯棒のうちの一本を欠いてしまったことはたしかだ。
選考の半ばで、各委員の意見を受け容れたのは、冒頭の凄味だけでも評価に値いすると考えたからである。そして決定を受け容れたからには大きな声で申しあげる、「おめでとう、ご精進を」と。
【この選評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする