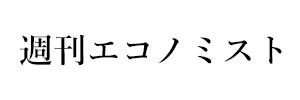書評
『イノベーターたちの日本史』(東洋経済新報社)
「身分の有償撤廃」で近代化 明治日本人の創造的対応
いくら現在の日本が先の見えない曲がり角にあるとしても、明治期の日本が直面した困難や不確実性と比べれば、「ベタ凪(なぎ)」といってもよい。本書が描くのは明治以降の日本の近代における「創造的対応」の軌跡と奇跡である。本書の焦点は制度や政策や組織や機構ではなく、個人の営為にある。津波のように押し寄せる外生的・内生的挑戦に立ち向かったイノベーターたち、明治初期の砲術家にして貿易商の高島秋帆、維新官僚の大隈重信、旧下級藩士にして小野田セメント創業者の笠井順八、三井、三菱の両財閥を成すに至った益田孝と岩崎弥太郎、発明家にして企業家の高峰譲吉、こうした傑物が果たした創造的対応の過程を鮮やかに記述する。
どの章を読んでも面白いが、秩禄処分と士族授産という維新官僚の革新的な政策が小野田セメントという近代的産業資本を生み出していくという、政府と民間の「二重の創造的対応」を考察する3章から4章が本書の白眉(はくび)である。
財政基盤が脆弱(ぜいじゃく)な明治新政府は財政負担の抜本的な削減という課題に直面していた。最大の削減対象は、封建制度の瓦解(がかい)によって不労所得者となった旧士族であった。ここで明治政府が繰り出したウルトラCが、武士階級という身分を金禄公債で買い入れ、その公債を産業資本に転換するという壮大な構想である。これに呼応して時代に鋭敏な一部の士族たちがさらなる創造的対応に乗り出し、日本資本主義の担い手に自らを変身させていく。
つくづく思い知らされるのは、変革におけるリアリズムとプラグマティズムの重要性である。変革というと、よく言えば「理念」、悪く言えば「かけ声」が先行しがちだが、維新官僚と企業家たちは徹底して現実的で実際的であった。これが「身分の有償撤廃」という創造的な政策に結実し、産業近代化の波を生み出した。
マクロレベルの社会変革では既得権益の破壊は避けて通れない。ヨーロッパの市民革命と比較して、明治維新がはるかに血生臭くない革命になりえた背後には、「損得勘定」という人間の本性を見据えた明治日本のイノベーターたちの思考と行動があった。
歴史とは機械的な法則の上に繰り返される自然科学的な現象でもないし、規範的な先進性や後進性があるわけでもない。それは優れて人間的な営為であり、個性的な現象である。このような著者の歴史観が本書の記述のあらゆる部分にすがすがしいまでに行き渡っている。
ALL REVIEWSをフォローする