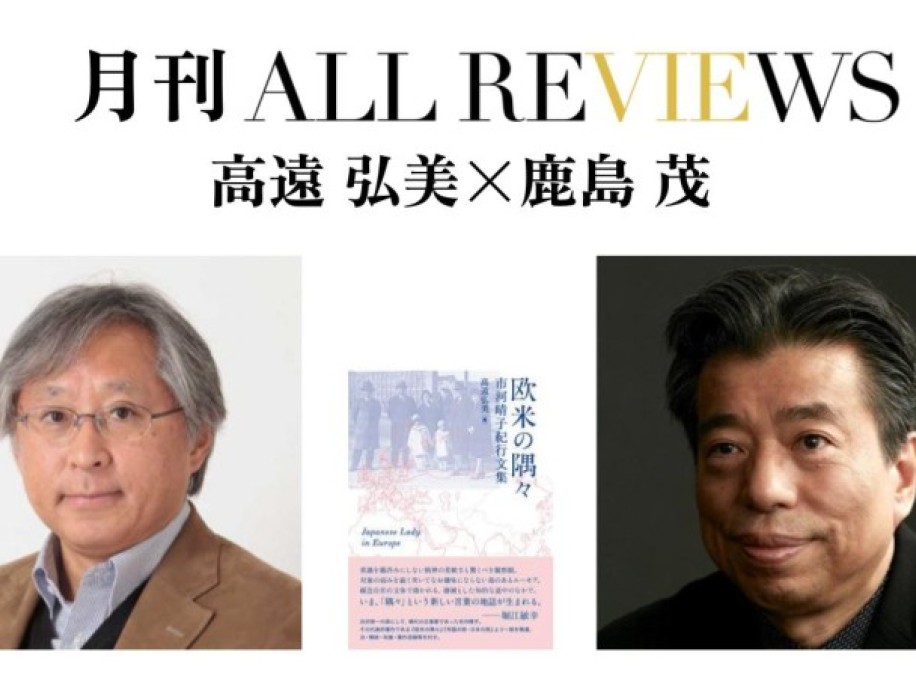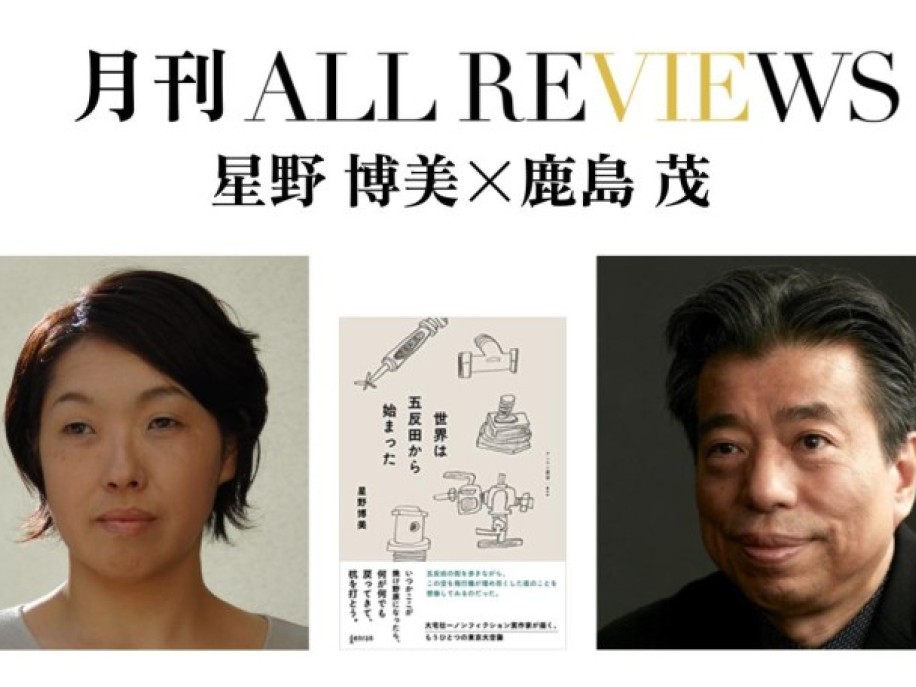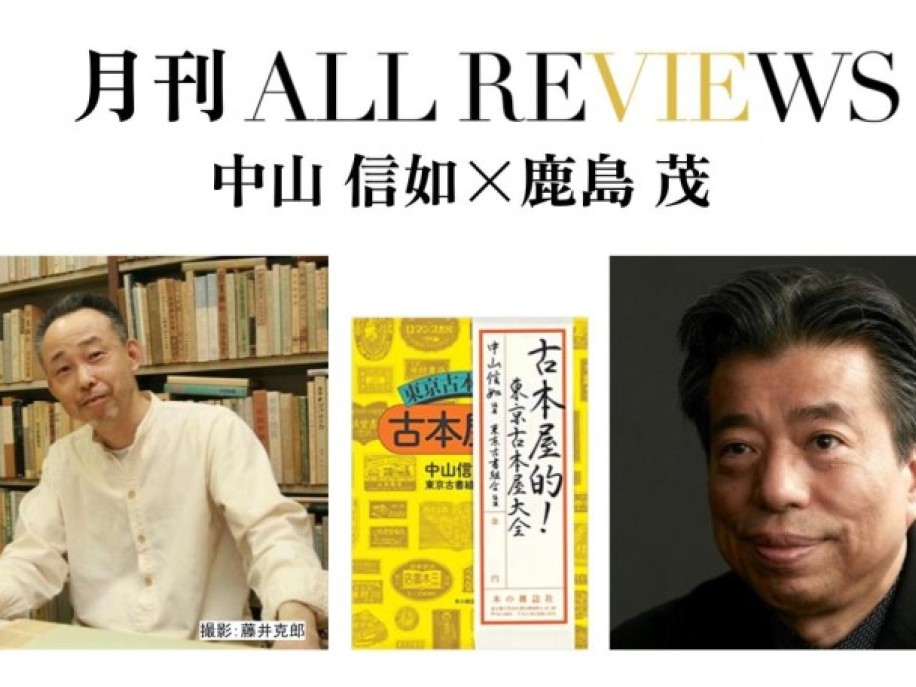書評
『大読書日記』(青土社)
プロの書評は最良の情報源、事後性を克服するため読む
どのようにして未知の良書と出会うか。Eコマースはとても便利ではある。しかし、書名や著者名が分かっていないと検索できない。買い物の場として優れているにしても、出会いの場としては難がある。アマゾンは「あなたへのおすすめ商品」を大量に紹介してくれる。これが頓珍漢(とんちんかん)なこと甚だしい。大規模な購買データをもとにしているのだが、そそられる本がほとんどない。ビッグデータと人工知能には一層の奮起を期待したい。単に僕の趣味嗜好がひねくれているだけかもしれない。
さらに役に立たないのが、ユーザーのコメントだ。ほとんどが匿名で、内容は玉石混交。もちろん玉より石のほうがはるかに多い。評価の星の数となるといよいよ意味がない。本は究極の嗜好品。不特定多数の評価の平均値を本選びの参考にする人の気が知れない。
僕にとっての最良の情報源は、結局のところプロの書いた書評である。ネットでの匿名の評価とは質の次元が異なる。知識・見識はもちろん、自分の名前を出す仕事であるからして、気合とサービス精神が違う。
僕が絶対の信頼を置くのはフランス文学者の鹿島茂。フランス文学には関心がないのだが、氏の人間と社会を視る眼とそこから生まれる大胆不敵な論理展開にいつも深く共感している。あっさりいえば、「面白がりのツボ」が合う。
鹿島茂『大読書日記』(青土社)は2001年から15年間の600ページ超の書評集。興味がない分野の本でも面白く読ませるところが凄い。他の書き物のジャンルと違って書評の価値尺度ははっきりしている。すなわち、読み手にその本を買わせられるかどうか。この書評集を読んだあと、僕は28冊発注した。厳選してもそれだけあった。
「理由は聞くな、本を読め」と題された長めのまえがきがとりわけ素晴らしい。ここを読むだけでも価値がある。なぜ本を読まなければならないのか。「読書は役に立つ」といってもしょうがない。読書の価値は事後的に振り返ってはじめてわかるものだからだ。
読書に限らず、大切なものほど事後性が高い。事後性の克服は人生の一大テーマといってよい。では、どうすべきか。それは読書しかない。本は事後において書かれている。読書によって、人は事後的にしか知りえないことを知ることができる。四の五の言わずにまずは読め――読書の効用の本質をこれほど明快に抉(えぐ)り出した文章を他に知らない。
ALL REVIEWSをフォローする