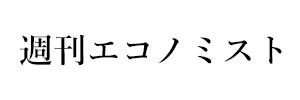書評
『実務で使える 戦略の教科書』(日本経済新聞出版社)
本質的かつ実用的 戦略の本質を明解に提示
経営戦略や事業戦略についての実務家向け解説書は世にあふれている。しかしその多くは「実務家向け」の「わかりやすい」「解説」を意図するがゆえに、結局、戦略とは何かがわからないまま終わってしまう。多くの実務家向けの解説書はSWOT分析(経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法)やファイブフォース・モデル(企業を脅かす五つの脅威)、バリューチェーン(価値連鎖)などのフレームワーク(問題解決に役立つ思考の枠組み)を解説し、その使い方を伝授する。しかし、そこから導出される情報がどのような意味を持ち、全体としての戦略のどこに作用し、他のフレームワークとどんな関係にあるのかまでは踏み込まない。こうした不満を一掃してくれるのが本書である。
戦略の定義を論じる冒頭の章からして味わい深い。戦略とは目的に対する手段である。しかしそれは「選択された手段」でなければならないと著者は言う。一つしか有効な手段が存在しないのであれば、それは「追い込まれている」のであって、戦略ではない。複数の代案を優先順位づけした後に選び取られた何かが戦略であり、戦略とは「何をやらないか」を決めることにある。戦略の本質を鮮やかに突いた定義だ。
何を対象に事業を行うのか。市場の選択から戦略は始まる。市場セグメンテーション(分化)を論じる章の後に、成長マトリクスなどおなじみのフレームワークを扱う章が来る。これらはいずれも個別市場間の資源配分に関わっている。だから市場セグメンテーションの章の後に来て初めて意味を持つ。議論の構成と流れがよく考えられている。だから、「実務で使える」のである。
製品・市場マトリクスを説明するところでも、その使用法にとどまらず、市場を細分化する軸としてなぜ製品(ないしサービス)を使うのか、といった「そもそも論」が出てくるのがいい。さまざまな取引特性のうち、製品が自社で最もコントロール可能な軸だからである。このようにフレームワークの背後にあるロジックにまで目配りが利いている。
評者は「ストーリー」をカギ概念として競争戦略を考えることを仕事にしている。本書には戦略ストーリーの章も用意され、そのわずか十数ページの簡潔な記述のなかに、評者もこれまで思いつかなかった新しい洞察が盛り込まれていて驚いた。
戦略に関わる重要問題を過不足なく網羅しながら説明はあくまでもコンパクト。比喩や実例が多く、読みやすい。「教科書」はこうありたい。
ALL REVIEWSをフォローする