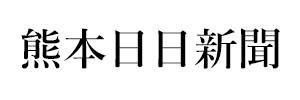書評
『日本文学源流史』(青土社)
ことばの変貌 見渡す視点とは
本文が478ページの大部の本である。日本文学の「起源」ではなく「源流」を問う。日本に文字がなかった時代から、中国から文字が移入され、それが定着しだした時代を経て、古代、中世、近世、近代、現代まで、「ことば」はどのように変貌してきたのか、一望のもとに見渡せる視点はどこにあるのか、それを探りながらの、わくわくするような本である。 著者は詩人であり、『源氏物語』を専門とする国文学者だが、これまで詩や詩論のほかに、神話や昔話、物語をめぐる考察と、文法論、あるいは時評や戦争論など、守備範囲は多彩だ。そしてどの領域でも、詩人としての顔と学者としての顔との両方を突出させる。折口信夫から多大な影響を受けた著者にとっては、詩も学問も創造的な営みとして同一である。わたしは「わくわくするような」と書いたが、それは本書が国文学の専門的知識がなくても読み進めることができる報告集の体裁をとっていることによる。日本文学をふり返るとき、琉球やアイヌの神話文学を含めるという視点も画期的だ。著者のこれまでの仕事の総集編としてのノートとも言うべきもので、古典文学の新しい解釈から、自由奔放な夢想へ、あるいは著者が言う「暴論」へつなげたりして、すこぶる面白い。ここから先どこへ行くのか、と読み出したらとまらなくなる。
本書は民俗学とは距離を置いている。民間習俗や伝承を扱う民俗学は歴史の流れとはかかわらない。それよりも「ことば」の考古学とも言える方法をとり、その時代ごとの歴史の動きに目をくばる。たえず折口信夫の国文学の発生をめぐる論考や芸能史という学問の壮大な構想を横に置き、批判的に検討しながら、「ことば」には「時代ごとに、さらには時代と時代とのあいだに源流があり、〈発生〉がわだかまるさまを、複数文化として把握したい」と考え、「文化と時代とを往還」することをめざす。「〈発生〉がわだかまるさま」とはいかにも著者にふさわしい言い回しで、ここに「起源」という定規をあてはめることはできない。「わだかまるさま」にこそ「源流」を見出(みいだ)せるということになる。
文字がまだ日本になかった時代、1万6500年前から3千年前までの石器時代から縄文時代までを「神話紀」、3千年前から紀元2、3世紀までの弥生時代を「昔話紀」とする。ここで人々の口から耳へ語られていたことは文献上には残っていないが、後に文字が移入された後でも、書物の外で、口承として生き続ける。それをその時代に戻って読み解く手法に、本書の神髄がある。3世紀から7世紀までの古墳時代を、著者は「フルコト紀」と呼ぶ。「フルコト」とは、「古言」であり「古事」である。5世紀頃にそれまで口伝えであった古い伝承が記紀神話として歴史化され、「旧辞」という書物になり、「祝詞」などの基礎が作られ、8世紀初めに『古事記』『日本書紀』が成立する。そして「物語紀」(7、8世紀~13、14世紀)が続き、14、15世紀以降、現在までを「ファンタジー紀」とする。突拍子もない命名だ。現在まで700年近くも同じことばの時代が続いていたとは、驚くべき発見だ。
日本の近代詩が翻訳と向き合いながら育てられ、それを内側から破るようにして成長してきたこと。丸山真男が日本社会の基層部を「つぎつぎになりゆくいきほひ」と位置づけたことに、ポストモダンイデオロギーを読みとること。人類がある限り続く戦争を、人身犠牲論や死刑論、差別問題と重ね合わせること。このどれもが今後、長く検討すべき価値ある提言だと思う。
ALL REVIEWSをフォローする