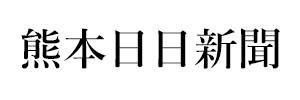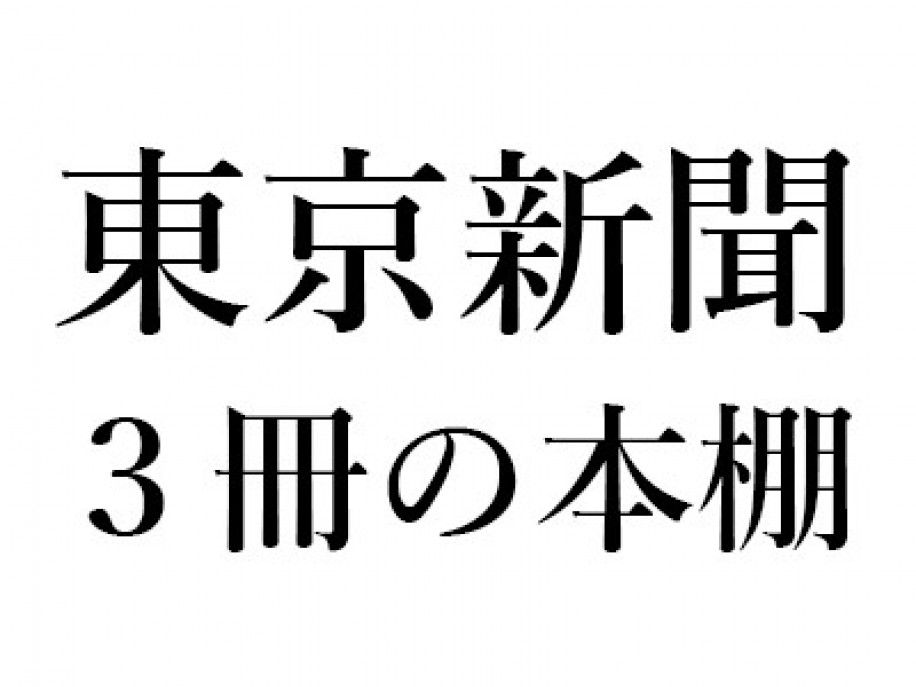書評
『読んじゃいなよ!――明治学院大学国際学部高橋源一郎ゼミで岩波新書をよむ』(岩波書店)
教育現場の理想像がここに
『読んじゃいなよ!』は岩波新書創刊以来、もっとも分厚い新書である。約380ページ。読書入門書としては画期的で、すこぶる新鮮。しかも「入門」などという堅苦しい入り口を作っていない。読書には「門」などないのだ。まず本書冒頭に収められた編者・高橋源一郎の序文「『読んじゃいなよ!』の取扱説明書」が、ふるっている。そもそも「取扱説明書」なのである! 本を読むことを勧めながら、本書の夕イトルを決めるまでの経緯を次のように説明している。
「『読め!』はイヤだ。なんだか、力づくの感じがするから。/『読んでみたら?』も、なんとなく押しつけがましい。/『読まなきゃダメ!』だと怒られてるみたい。/『読むべきだよ』も『読んでみれば?』もピンとこない。/そして、たどり着いたのは『読んじゃいなよ!』だったのです。」
なるほどなあ、とつくづく感心した。わたしも大学講師の経験があるから、若い学生たちに本を読むことを勧めたことは多々あるが、ここまでは考えなかった。若者の読書離れは著しい。というふうに歎(なげ)く一般の大人と同じように、歎く一方だったのである。そのときの説得は、力づくで、押しつけがましく、秘かに怒っていて、上から目線で、結局、若者たちにはピンとこなかったのではないか。わたしが勤めていた大学は音楽学校だったせいもあって、学生たちは楽譜は熱心に読むが、文字を読むのは苦手だったのである。
ああ、彼らに「読んじゃいなよ!」と言っておけばよかった。
本書は、高橋源一郎が明治学院大学国際学部で開いている「言語表現法」講座での、岩波新書を読んで感想文を書くという、2年間にわたる活動記録だ。学生たちが読んだ岩波新書の著者のなかから、ゲスト・スピーカーとして哲学者の鷲田清一、憲法学者の長谷部恭男、詩人の伊藤比呂美の3人が呼ばれ、「白熱教室」が開かれる。そこでの講演者と学生たちの対話を中心にまとめられている。
学生たちはドストエフスキーを読んで「マジやばい!」(これはほめ言葉である)と言い、小林秀雄を読んで「このコバヤシ、って人、なんでこんなに威張ってんの?」と言う。それを聞いて高橋氏は「正しい読み方です。というか、正しすぎる!」と感嘆する。余計な情報で素直に読めなかった自らを反省し、彼らから読み方を学ぶようになり、嫉妬さえしたと言う。
まことに優れた先生だな。こんなに柔軟に受講生と対応できる先生は、日本の大学には滅多にいない。だから、大学というのはいったい何だろう? 先生というのは何だろう? 本書は確かに本を読むことを勧める本なのだが、それよりも何よりも、「学校」について考えさせられたのである。大学って、そんなに面白いところだったの! とも思わせられる。
わたしの父親は半世紀以上、高校と大学の美術教師をしていたが、晩年になって、中学生の孫が不登校生になったとき、学校に行けとは言わなかった。わたしがその理由を聞くと、「学校が好きな子供はいない。毎日行く子供は、中毒だ」と言った。長年の教師生活の結論がこれかと、笑いながら納得する以外なかったが、本書を読んで、こんな「白熱教室」が成立するのなら、別の「学校中毒」が起こっていいだろうと思う。
鷲田清一は学生に言う。「大学って、卒業ってなかったらいいですのにね」。自分が納得するまで大学にいて、潮時が来ていったん去っても、また自由に戻ってこれるような場所。教育の現場は、実はここに理想がある。
ALL REVIEWSをフォローする