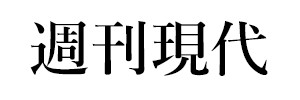書評
『銀しゃり』(小学館)
"握り"登場以前の鮨職人を主人公に寛政の"改革"に揺れる江戸で"誠"を胸に生きる人々の姿を描く
『銀しゃり』は、手で読む小説である。手で読むとは異なことを言う、とお思いですか。しかし読み進めるほどに我が手が「わかる、わかる」と言うのだからしかたがない。たとえば、主人公が庖丁を研ぐ場面。――庖丁の峯(みね)に親指を当てて、両手の人差し指と中指を腹に置いている。そして庖丁と砥石の間に箸一本分の隙間をこしらえると、たっぷり水に濡らした砥石の上を滑らせた。
なんて一文を読むと、庖丁の感触が指先に見事に再現されるのである。
寛政二(一七九〇)年の春から初夏の候を描いた小説だ。主人公・新吉は江戸・深川で「三ツ木鮨」の屋号を掲げる職人である。この時代にはまだ握り鮨はないので、新吉の鮨は箱鮨である。
上質の庄内米を酢飯にして箱に詰めた上に新鮮な魚介類を散らしたものだ。兄弟同然のつきあいをする魚屋の順平や、職人に深い共感を示す旗本家臣の小西秋之助などの暖かい人々に囲まれながら、新吉は鮨の味を完成させていく。
江戸の職人を描く小説なのである。新吉自身、もちろん腕利きの職人だが、彼が縁を結んでいく相手もまた、優れた技能を持った人々である、というのがおもしろい。たとえば武士である小西秋之助までが、熟練職人顔負けの、竹細工の腕を持っているのである。
現代社会への批判
物語の背景では、寛政の改革が真っ盛り。作中でも棄捐(きえん)令により、幕臣が札差に対して負っていた借金が棒引きにされたことが記されている。この乱暴な経済政策は、武士が町人に寄生する存在であることを明らかにしてしまった。なにしろ借金を返す、という当たり前のことさえできないのだ。本書では、そうした武士の虚栄と、職人の誠とが対比されているわけです。山本一力は、虚ろなものばかりがもてはやされる時代に確かな芯を持って生きることの重要性を一貫して描いてきた作家だ。その姿勢の背景には間違いなく現代社会への批判がある。
山本の描く主人公は、決しておのれをひけらかさず、自身の職能を大事に生きるだけだ。『銀しゃり』には、そうした謙虚さ、職人の矜持といった不可視のものを、てのひらにそっと載せられたような読後感がある。
やはり手で読む小説なのです。
ALL REVIEWSをフォローする