書評
『原典訳マハーバーラタ〈1〉第1巻』(筑摩書房)
『マハーバーラタ』は文字通り、世界でもっとも長い物語である。聖書の16倍というその規模は、文学を天文学へと近付けさせるといってよい。それはこれまで西洋中心に形作られてきた叙事詩という概念、文学という観念を、いとも簡単に転覆させてしまう。古代インドで8世紀にわたって朗誦され筆記されてきたこの書物は、宇宙の始源から森羅万象、そして人類の終末までを描き、あたかも巨大な図書館のごとき堅固な構造と多様性をもっているのだ。だがそればかりではない。この書物は驚くべきことに、行動と反省、復讐と和解、狂信と達観といった主題を通して、今日のわれわれを取り囲んでいる混乱と悲惨をめぐって深い叡智をさしだしている。物語の後半では、世界を破滅させてしまう絶対兵器パシュパタがついに用いられてしまう。だがその後でも、人類は生き延びていかなければならない。どのようにして? 答えはこの「偉大なるコード」、『マハーバーラタ』のなかに隠されているのだ。
自分を恋する王女を父親に献上し、生涯を童貞で暮らすことを選んだ代わりに、人間の放つ弓矢によってはけっして落命しないと神々に保証された男。その男に復讐するため、みずから生命を絶って冥界に下り、美少年に転生して男を射止めようとする姫君。一人の王妃を5人で共有する王子たち。とりわけその最年長の王子は、善良ではあるが賭け事に目がなく、金銀財宝どころか王国も、さらに王妃までをもイカサマで奪い取られてしまう……ありとあらゆる企み、策略、戦術が戦わされ、最後に5人の善王子と100人の悪王子の軍勢が15日間にわたって、壮絶な戦闘を繰り返し、最年長の王子ひとりを除いてほとんど全員が死に絶えてしまう。
『マハーバーラタ』は、南アジアと東南アジアに跨る巨大な物語の圏域を構成している。
発祥の地インドでは、それは寺院の彫刻に始まり、絵画、音楽、舞踏、そして漫画と映画に夥しい物語を提供している。インドネシアではガムラン音楽に飾られて人形劇ワヤンの原作となり、タイでは『ラーマーヤナ』とともに、近代の政治人類学に影響を与えている。中国では仏教の本生譚に流れ込み、その一部は本朝の『今昔物語集』に紛れ込んで、能と歌舞伎に『鳴神』という演目を授けた。日本とは『マハーバーラタ』の最北端なのだ。そう、飛行機で成田と関空を出た瞬間からわれわれに襲いかかるのは、まさしくこの物語の強靭な磁力にほかならない。
わたしは1980年代の中ごろ、パリに拠点を置く国際的演出家ピーター・ブルックが3日3晩かけてこの大叙事詩を、アヴィニョン演劇祭の野外舞台に揚げるのを見て、ただちにその恐るべき魅力の虜となった。ブルックは西洋演劇の閉塞状況を打破するために、物語という、長く忘れられていた言語を回復させようと意図していた。それは、巨大な物語などもはや人類の間から消滅してしまったと嘯くポストモダン主義者たちが、演劇を不毛な独白やメタレヴェルの抽象劇に還元してしまったことに対する、挑発的な実験であるように思われた。ブルック版『マハーバーラタ』は登場人物だけでものべ100人を越し、準備に10年の時間がかけられている。この演劇体験が契機となって、わたしは『マハーバーラタ』に飛びついたのである。これまで抄訳や重訳しかなかったこの魔法のような書物が、ここに原典であるサンスクリット語から翻訳されるようになったことは、うれしいかぎりだ。訳者の筆の冴えゆかんことを祈りたい。
【この書評が収録されている書籍】
自分を恋する王女を父親に献上し、生涯を童貞で暮らすことを選んだ代わりに、人間の放つ弓矢によってはけっして落命しないと神々に保証された男。その男に復讐するため、みずから生命を絶って冥界に下り、美少年に転生して男を射止めようとする姫君。一人の王妃を5人で共有する王子たち。とりわけその最年長の王子は、善良ではあるが賭け事に目がなく、金銀財宝どころか王国も、さらに王妃までをもイカサマで奪い取られてしまう……ありとあらゆる企み、策略、戦術が戦わされ、最後に5人の善王子と100人の悪王子の軍勢が15日間にわたって、壮絶な戦闘を繰り返し、最年長の王子ひとりを除いてほとんど全員が死に絶えてしまう。
『マハーバーラタ』は、南アジアと東南アジアに跨る巨大な物語の圏域を構成している。
発祥の地インドでは、それは寺院の彫刻に始まり、絵画、音楽、舞踏、そして漫画と映画に夥しい物語を提供している。インドネシアではガムラン音楽に飾られて人形劇ワヤンの原作となり、タイでは『ラーマーヤナ』とともに、近代の政治人類学に影響を与えている。中国では仏教の本生譚に流れ込み、その一部は本朝の『今昔物語集』に紛れ込んで、能と歌舞伎に『鳴神』という演目を授けた。日本とは『マハーバーラタ』の最北端なのだ。そう、飛行機で成田と関空を出た瞬間からわれわれに襲いかかるのは、まさしくこの物語の強靭な磁力にほかならない。
わたしは1980年代の中ごろ、パリに拠点を置く国際的演出家ピーター・ブルックが3日3晩かけてこの大叙事詩を、アヴィニョン演劇祭の野外舞台に揚げるのを見て、ただちにその恐るべき魅力の虜となった。ブルックは西洋演劇の閉塞状況を打破するために、物語という、長く忘れられていた言語を回復させようと意図していた。それは、巨大な物語などもはや人類の間から消滅してしまったと嘯くポストモダン主義者たちが、演劇を不毛な独白やメタレヴェルの抽象劇に還元してしまったことに対する、挑発的な実験であるように思われた。ブルック版『マハーバーラタ』は登場人物だけでものべ100人を越し、準備に10年の時間がかけられている。この演劇体験が契機となって、わたしは『マハーバーラタ』に飛びついたのである。これまで抄訳や重訳しかなかったこの魔法のような書物が、ここに原典であるサンスクリット語から翻訳されるようになったことは、うれしいかぎりだ。訳者の筆の冴えゆかんことを祈りたい。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
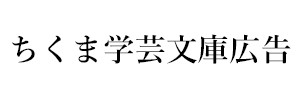
ちくま学芸文庫広告 2001年11月
ALL REVIEWSをフォローする












































