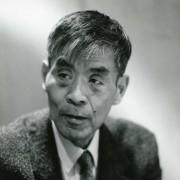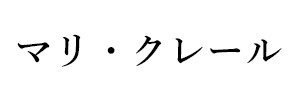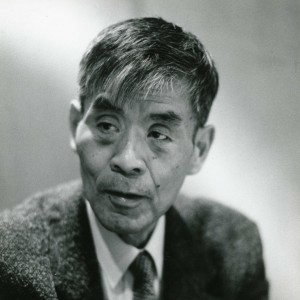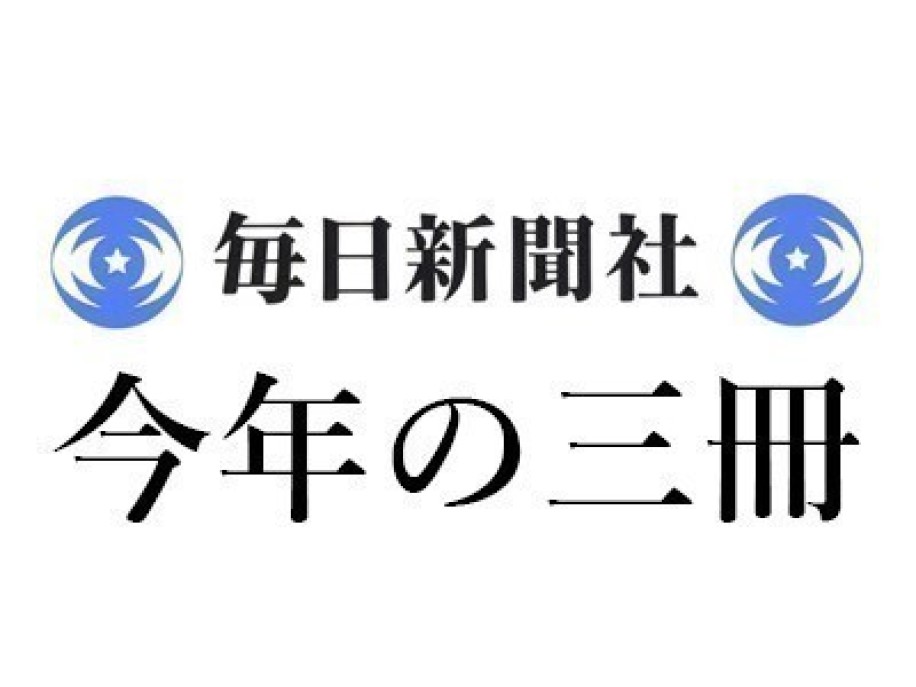書評
『変容の象徴―精神分裂病の前駆症状〈上〉』(筑摩書房)
この本は、ユングの学説が、フロイトの心理学の胎内で育ちながら、これから分娩による分割を受けて独自の存在の姿を現わそうとしている胎動を示す、記念碑的な本だとおもう。その意味でフロイトの思考方法とユング独自の思考方法とが、混沌とした団塊から交替で貌をのぞかせる。興味ぶかい心理学上のドラマの本だといえる。もしここに豊富に引例されているキリスト教やキリスト教以前のヨーロッパの神話、伝説、土俗信仰などのすこしわずらわしすぎる解釈、文学(詩)作品や図版の分析と解釈といった豊富な証拠がためなどが本の中心を拡散させる印象を与えなかったら、心理学の分野にとどまらずに、普遍的古典としてのこるものだったにちがいない。それほどこの本にばらまかれている言語、神話、伝承、美術、文学にたいするユングの洞察と、底を流れて見えかくれするフロイト=ユング合作の心理学の解釈の体系は魅力的である。
ユングはまず「意識」と並行の関係がある言語から独自な発生説をくりひろげる。言語は、はじめはきれいな水をみつけた、熊を殺した、嵐が近づくぞ、狼が小屋のまわりをうろついてるぞ、などと仲間に呼びかける「声」からはじまった。これは二つに分類すれば「感情表出の音声(恐怖など)」と「模倣の音声(水や嵐や獣のうなり声)」とに分かれるが、これこそが言語の起源にあるもので、どんな抽象的な哲学体系の言語でも、この自然界のもの音や声をできるだけ緻密に組合せて再現しようとする原衝動をかくしている。これが無意識やその奥にひそむ集合的無意識(元型)にまで関連をつなげることができるユングの独創的な言語観である。
無意識、その就眠中の表出である夢などは、言語以前の自然界や動物の音や声の象徴的なイメージで綴られた非言語的な物語なのだが、どんなに奥深く秘められたものだったとしても、かならず言語的に語ることのなかで姿を表わすのは、言語がもともと自然界の音や声を緻密に再現しようとする原衝動から発生したものだからだ。これがユングの考え方の根底にある独創的な思考である。
いま師フロイトのリビド(性衝動)という考えを外にむかう無意識のエロスのエネルギーに限定しないで、外界に渦巻き、いたるところで大小のしこりを形成している権力、飢え、憎悪、信念、宗教のせめぎあいの濃度や強度のエネルギーの無意識な衝動力にまで拡大してしまうとしよう。そうすると、それぞれの民族や種族のもっている神話や伝承や、それを形象化した美術や文学のうち、共通の層を形成している同一性の世界は、すべてこれらの広義なリビドの表出として解釈できるものなのだ。神々の物語は元型的なリビドの表われであり、英雄たちの物語は、人間が元型の集合的無意識の世界から、しだいに意識の生活(個体の生活)をもつようになっていった時代の、実際の生活譚になぞらえられる。
またこれは個体のうちに宿る欲動の姿や、その胎児、乳児、思春期へと変容してゆく象徴形成の仕方にも適応している。はじめに母の胎内にあるときには、元型的なリビドの海に誰でも同じく浮遊しており、乳児のときには母の乳房を「吸引」する「リズミカルな活動」を、口唇の周辺からはじめ、しだいに身体の他の部位にまで及ぼしてゆく。それとともに乳児期の栄養摂取の運動だけだったものが、身体の開口部を介して、性的な摂取欲動にまで拡がってゆく。それと一緒に身体の栄養器官と性的器官とが二重にからみ合わされてリビドの「組み」を作るようになる。
この部分の思考を展開するときには、ユングは意図的にも無意識にも師フロイトと合作で理論を展開している。フロイトの性的リビド説を深くじぶんなりに編成しなおしながら、それでもじぶんの集合的無意識(元型)リビドにまでその説を拡大しようとして懸命な努力を払っている。フロイトの学説の母胎から分娩によって分割されようとするユングの姿が、生みの苦しみというよりも、依頼心と反発、尊敬と異和のせめぎ合い、謙虚と自負心の明滅として興味ぶかく展開されている。
この本でユングは、不安神経症や精神分裂病の患者にあらわれる症状やさまざまな妄想は、歴史的にいえば神話の「神々」や「英雄」の行動があらわしている姿の記述された層につぎつぎ退化しているものだし、個体でいえば幼児期から乳児期に、乳児期から元型的な胎児期にと、リビドが層ごとに退化してゆく姿に対応してと述べている。そして精神分裂病の症状は、リビドが性的欲動である集合的無意識まで退化した姿として把握されることを明らかにしている。
【この書評が収録されている書籍】
ユングはまず「意識」と並行の関係がある言語から独自な発生説をくりひろげる。言語は、はじめはきれいな水をみつけた、熊を殺した、嵐が近づくぞ、狼が小屋のまわりをうろついてるぞ、などと仲間に呼びかける「声」からはじまった。これは二つに分類すれば「感情表出の音声(恐怖など)」と「模倣の音声(水や嵐や獣のうなり声)」とに分かれるが、これこそが言語の起源にあるもので、どんな抽象的な哲学体系の言語でも、この自然界のもの音や声をできるだけ緻密に組合せて再現しようとする原衝動をかくしている。これが無意識やその奥にひそむ集合的無意識(元型)にまで関連をつなげることができるユングの独創的な言語観である。
無意識、その就眠中の表出である夢などは、言語以前の自然界や動物の音や声の象徴的なイメージで綴られた非言語的な物語なのだが、どんなに奥深く秘められたものだったとしても、かならず言語的に語ることのなかで姿を表わすのは、言語がもともと自然界の音や声を緻密に再現しようとする原衝動から発生したものだからだ。これがユングの考え方の根底にある独創的な思考である。
いま師フロイトのリビド(性衝動)という考えを外にむかう無意識のエロスのエネルギーに限定しないで、外界に渦巻き、いたるところで大小のしこりを形成している権力、飢え、憎悪、信念、宗教のせめぎあいの濃度や強度のエネルギーの無意識な衝動力にまで拡大してしまうとしよう。そうすると、それぞれの民族や種族のもっている神話や伝承や、それを形象化した美術や文学のうち、共通の層を形成している同一性の世界は、すべてこれらの広義なリビドの表出として解釈できるものなのだ。神々の物語は元型的なリビドの表われであり、英雄たちの物語は、人間が元型の集合的無意識の世界から、しだいに意識の生活(個体の生活)をもつようになっていった時代の、実際の生活譚になぞらえられる。
またこれは個体のうちに宿る欲動の姿や、その胎児、乳児、思春期へと変容してゆく象徴形成の仕方にも適応している。はじめに母の胎内にあるときには、元型的なリビドの海に誰でも同じく浮遊しており、乳児のときには母の乳房を「吸引」する「リズミカルな活動」を、口唇の周辺からはじめ、しだいに身体の他の部位にまで及ぼしてゆく。それとともに乳児期の栄養摂取の運動だけだったものが、身体の開口部を介して、性的な摂取欲動にまで拡がってゆく。それと一緒に身体の栄養器官と性的器官とが二重にからみ合わされてリビドの「組み」を作るようになる。
この部分の思考を展開するときには、ユングは意図的にも無意識にも師フロイトと合作で理論を展開している。フロイトの性的リビド説を深くじぶんなりに編成しなおしながら、それでもじぶんの集合的無意識(元型)リビドにまでその説を拡大しようとして懸命な努力を払っている。フロイトの学説の母胎から分娩によって分割されようとするユングの姿が、生みの苦しみというよりも、依頼心と反発、尊敬と異和のせめぎ合い、謙虚と自負心の明滅として興味ぶかく展開されている。
この本でユングは、不安神経症や精神分裂病の患者にあらわれる症状やさまざまな妄想は、歴史的にいえば神話の「神々」や「英雄」の行動があらわしている姿の記述された層につぎつぎ退化しているものだし、個体でいえば幼児期から乳児期に、乳児期から元型的な胎児期にと、リビドが層ごとに退化してゆく姿に対応してと述べている。そして精神分裂病の症状は、リビドが性的欲動である集合的無意識まで退化した姿として把握されることを明らかにしている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする