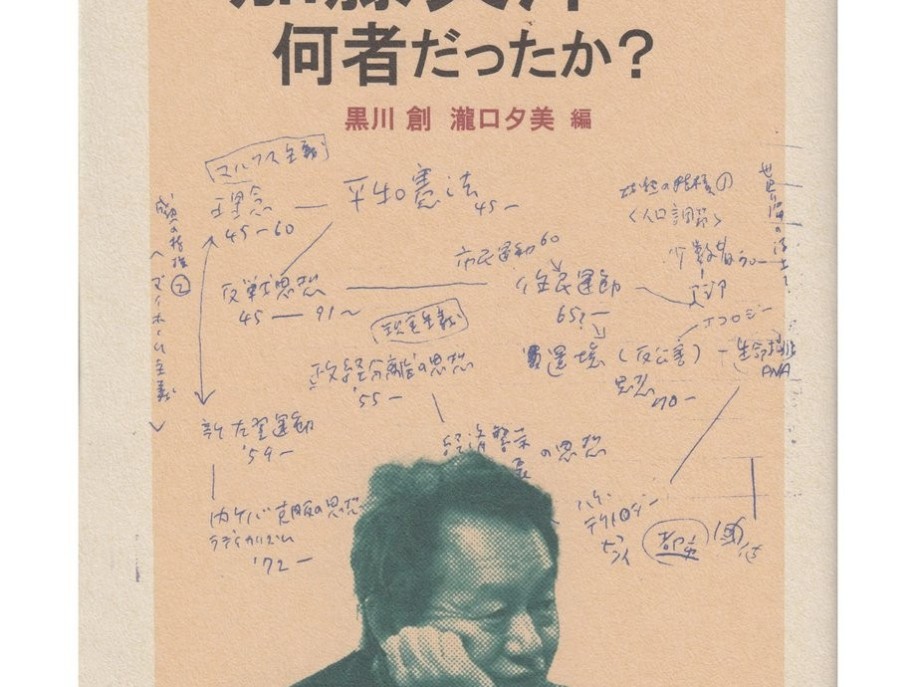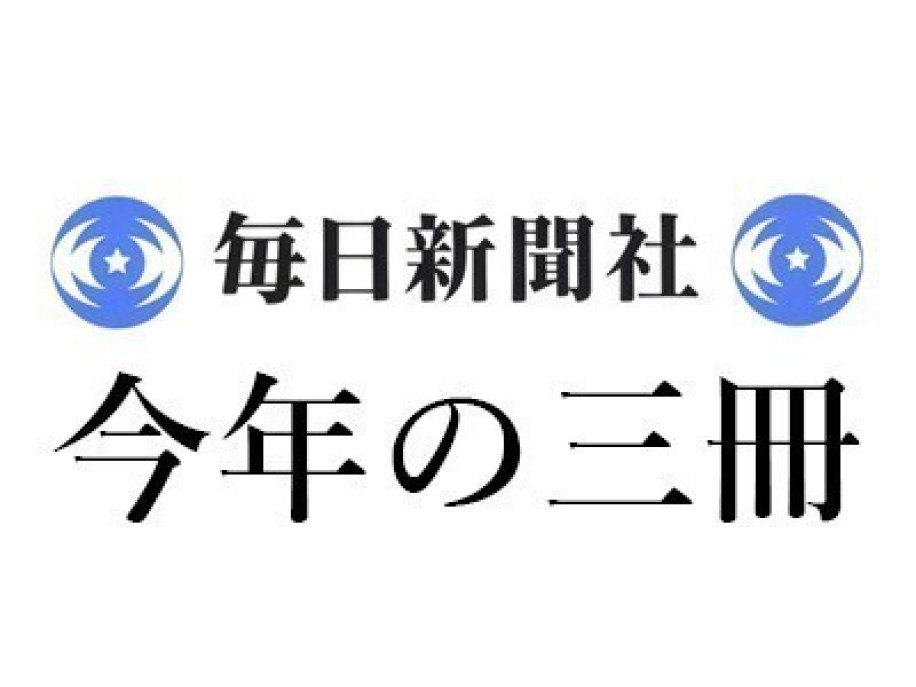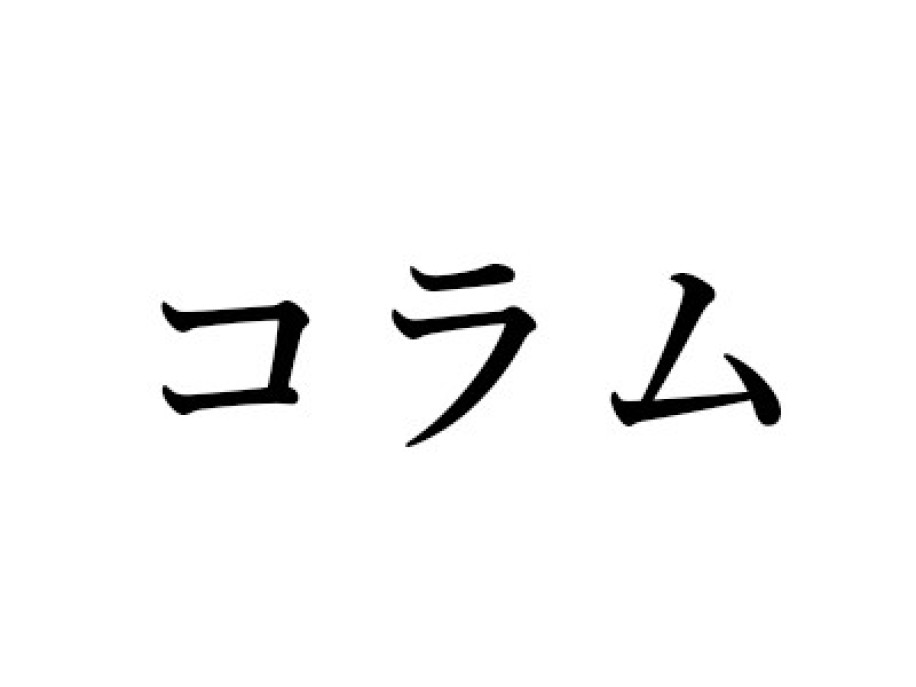書評
『ファンタスマゴリア―光学と幻想文学』(ありな書房)
ここ十数年のあいだに、欧米とりわけ英語圏で盛んになってきている文学批評の一つに、想像力がテクノロジーによってどのように条件づけられているかを調べる、「文学とテクノロジー」研究の潮流がある。削岩技術の発達によって垣間(かいま)見られるようになった地下世界の光景が、人間社会のモデルを、「上と下」という思考法でとらえる想像力を生みだしたとするロザリンド・ウィリアムズの『地下世界』などはその典型といえるが、フランス語圏においても同様の方法論に基づく画期的な研究があらわれた。十七世紀以来急速な発達をとげた光学装置が、いかに幻想文学の想像力の形態を規定してきたかを精神分析的観点から考察したマックス・ミルネールの『ファンタスマゴリア』がそれである。
十八世紀の末、ベルギー生まれのロバートソン(本名エティエンヌ・ロベール)は、かの有名なアタナシウス・キルヒャーの幻燈機に改良を加えた見世物「ファンタスマゴリア」をひっさげてパリに登場し、大当たりをとった。この光学的スペクタクルは興行的には短命だったが、言葉としては意外なほど長く生き延びた。というのもこの光学装置はもろもろの映像が「夢の非合理性をもって出現する《もうひとつの舞台》」を連想させるという点で、同時代のドイツ・ロマン派の想像力の様式を見事に表象していたからである。
ミルネールによれば、ドイツ・ロマン派の中でも、とりわけファンタスマゴリア的な想像力を発揮したのはホフマンだった。なぜなら、ホフマンの作品では、実際に、双眼鏡、顕微鏡、眼鏡、鏡などがふんだんに登場するばかりか、その光学器械が安定した人生の中に穿たれた異世界をのぞかせて、「不気味なもの」の幻影を生ぜしむる点において、語り手の禁じられた窃視症的欲望の隠喩となっていたからである。
日常生活の中に突如侵入してくる「不気味なもの」が光学装置によって示されるという主題は、鏡に映った自分の像が消えたり、迫害者となったりするホフマンの『大晦日(おおみそか)の夜の椿事(ちんじ)』やモーパッサンの『オルラ』等の分身テーマの小説にも同じように観察される。この場合、鏡とは「ナルシシズムをうまく統御できないことから生じる人格遊離」の恐怖を象徴しているという。
ところで、ここまでは、いかに物語の中の幻想が突飛なものであろうと、その表象となっている光学装置自体は非現実的なものではない。だが、作家の想像力はやがて、望遠鏡や顕微鏡といった光学装置の原理を拡大解釈し、「見えないものを見せる」幻想の光学装置を生み出す。この手の幻想光学装置は、乗り越えることのできない距離を消滅させたり、可視空間の領域を変容させたりするものだが、そうした「見えないものを見せようとする」野望は、たんに「権力や監視についての空想的で不気味な夢」としてばかりではなく、「感覚世界における既知の事実相互間の新たな関係の発見」としてもあらわれてくる。
こうした幻想光学装置の中でもとりわけ興味深いのは、第五章「時を征服する光学」で取り上げられている過去や未来を覗(のぞ)く装置である。ただ、こうした装置でも、時間軸に向けられる視線に風刺的、道徳的な意図が付与された場合には幻想を支える想像力は発動されず「不気味なもの」は現れてこない。「不気味なもの」が出現するのは、むしろ使用者の意志ではどうにも制御できないような機械が相手のときである。ボブ・ショーの『時の目』に登場する「遅延ガラス」はこの点うってつけである。というのも、光が通過するのに非常に時間がかかる、この「遅延ガラス」は、いわば無作為の対象を長時間撮影したビデオ映像を時間を隔てて見るときのような、失われた過去に対する不思議な情動を喚起するからである。
光学装置による情動の喚起という点では、ヴィリエ・ド・リラダンの『未来のイヴ』やヴェルヌの『カルパチアの城』を忘れてはならない。なぜなら、これらはいずれも、愛する女の幻影を光学的に作り出そうとする、「光学的恋愛」の物語だからである。現実の女よりも光学的な幻影の「女」の方を好むという、きわめて今日的な愛の形がすでに現れている。
このように、ミルネールによれば、現実世界へ突如現れる「不気味なもの」を表象する幻想文学は、視線に込められた無意識の欲望、すなわち窃視衝動を中核にすえている以上、その錯乱した動態を反映するものとしての光学装置の隠喩を必然的にうちに含むことになる。ただ、それにしては、ミルネールは光学装置のテクノロジー的な想像力への考察を軽視しすぎてはいないかという疑問は残る。
ともあれ、光学装置という思いもかけなかった観点を文学批評に導入した点で、本書は高く評価されてよい。訳文は、朦朧体(もうろうたい)の原文をよく咀嚼(そしゃく)して読みやすい日本語に移しかえている。訳者の労を多としたい。
【この書評が収録されている書籍】
十八世紀の末、ベルギー生まれのロバートソン(本名エティエンヌ・ロベール)は、かの有名なアタナシウス・キルヒャーの幻燈機に改良を加えた見世物「ファンタスマゴリア」をひっさげてパリに登場し、大当たりをとった。この光学的スペクタクルは興行的には短命だったが、言葉としては意外なほど長く生き延びた。というのもこの光学装置はもろもろの映像が「夢の非合理性をもって出現する《もうひとつの舞台》」を連想させるという点で、同時代のドイツ・ロマン派の想像力の様式を見事に表象していたからである。
ミルネールによれば、ドイツ・ロマン派の中でも、とりわけファンタスマゴリア的な想像力を発揮したのはホフマンだった。なぜなら、ホフマンの作品では、実際に、双眼鏡、顕微鏡、眼鏡、鏡などがふんだんに登場するばかりか、その光学器械が安定した人生の中に穿たれた異世界をのぞかせて、「不気味なもの」の幻影を生ぜしむる点において、語り手の禁じられた窃視症的欲望の隠喩となっていたからである。
日常生活の中に突如侵入してくる「不気味なもの」が光学装置によって示されるという主題は、鏡に映った自分の像が消えたり、迫害者となったりするホフマンの『大晦日(おおみそか)の夜の椿事(ちんじ)』やモーパッサンの『オルラ』等の分身テーマの小説にも同じように観察される。この場合、鏡とは「ナルシシズムをうまく統御できないことから生じる人格遊離」の恐怖を象徴しているという。
ところで、ここまでは、いかに物語の中の幻想が突飛なものであろうと、その表象となっている光学装置自体は非現実的なものではない。だが、作家の想像力はやがて、望遠鏡や顕微鏡といった光学装置の原理を拡大解釈し、「見えないものを見せる」幻想の光学装置を生み出す。この手の幻想光学装置は、乗り越えることのできない距離を消滅させたり、可視空間の領域を変容させたりするものだが、そうした「見えないものを見せようとする」野望は、たんに「権力や監視についての空想的で不気味な夢」としてばかりではなく、「感覚世界における既知の事実相互間の新たな関係の発見」としてもあらわれてくる。
こうした幻想光学装置の中でもとりわけ興味深いのは、第五章「時を征服する光学」で取り上げられている過去や未来を覗(のぞ)く装置である。ただ、こうした装置でも、時間軸に向けられる視線に風刺的、道徳的な意図が付与された場合には幻想を支える想像力は発動されず「不気味なもの」は現れてこない。「不気味なもの」が出現するのは、むしろ使用者の意志ではどうにも制御できないような機械が相手のときである。ボブ・ショーの『時の目』に登場する「遅延ガラス」はこの点うってつけである。というのも、光が通過するのに非常に時間がかかる、この「遅延ガラス」は、いわば無作為の対象を長時間撮影したビデオ映像を時間を隔てて見るときのような、失われた過去に対する不思議な情動を喚起するからである。
光学装置による情動の喚起という点では、ヴィリエ・ド・リラダンの『未来のイヴ』やヴェルヌの『カルパチアの城』を忘れてはならない。なぜなら、これらはいずれも、愛する女の幻影を光学的に作り出そうとする、「光学的恋愛」の物語だからである。現実の女よりも光学的な幻影の「女」の方を好むという、きわめて今日的な愛の形がすでに現れている。
このように、ミルネールによれば、現実世界へ突如現れる「不気味なもの」を表象する幻想文学は、視線に込められた無意識の欲望、すなわち窃視衝動を中核にすえている以上、その錯乱した動態を反映するものとしての光学装置の隠喩を必然的にうちに含むことになる。ただ、それにしては、ミルネールは光学装置のテクノロジー的な想像力への考察を軽視しすぎてはいないかという疑問は残る。
というのも、私見によれば、この手の「テクノロジーと文学」研究においては、テクノロジーをやたらに隠喩的に(つまりは文学的に)解釈するよりも、いったん幻想光学装置をも含めたテクノロジーそのものが持つファンタスムを考察し、次にこれを広く同時代の文化的な思考様式へとフィード・バックさせ、しかるのちに再び文学の様式へと戻ってくるといった迂回路(うかいろ)を取ったほうが、テクノロジーと文学の相互規定関係を見るのに適していると思うからである。ミルネールは「幻想」と「光学装置」と「無意識」という三極構造を設定し、この三極のたわむれを、フロイト精神分析の解釈用具で説明しようとしているが、これではせっかく光学装置という外へと広がる要素を持ち込んだ意味が薄らいでしまうのではなかろうか。
ともあれ、光学装置という思いもかけなかった観点を文学批評に導入した点で、本書は高く評価されてよい。訳文は、朦朧体(もうろうたい)の原文をよく咀嚼(そしゃく)して読みやすい日本語に移しかえている。訳者の労を多としたい。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
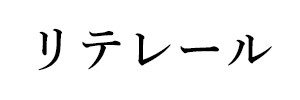
リテレール(終刊) 1994年秋号
ALL REVIEWSをフォローする