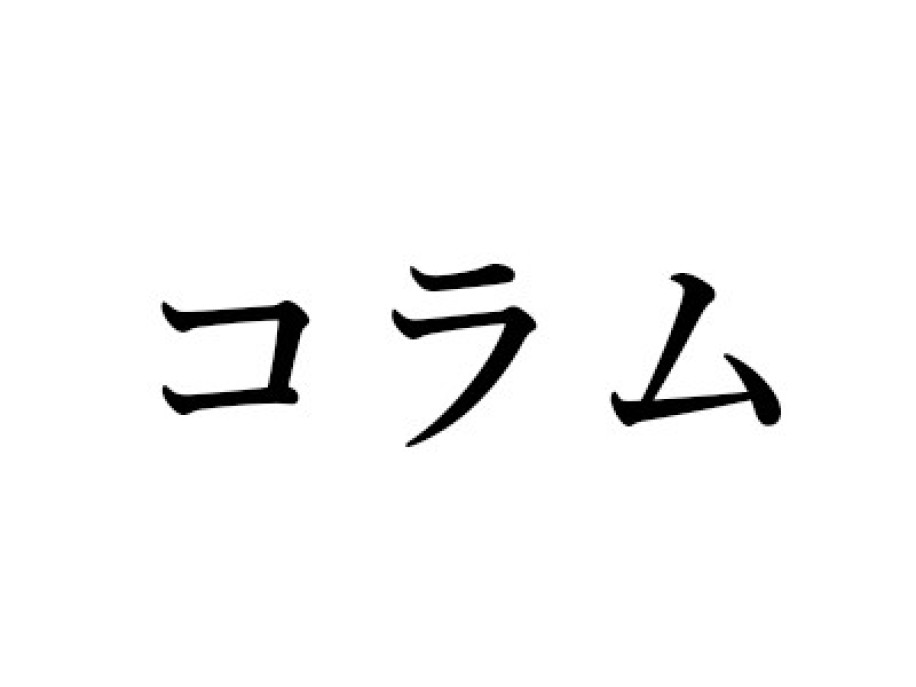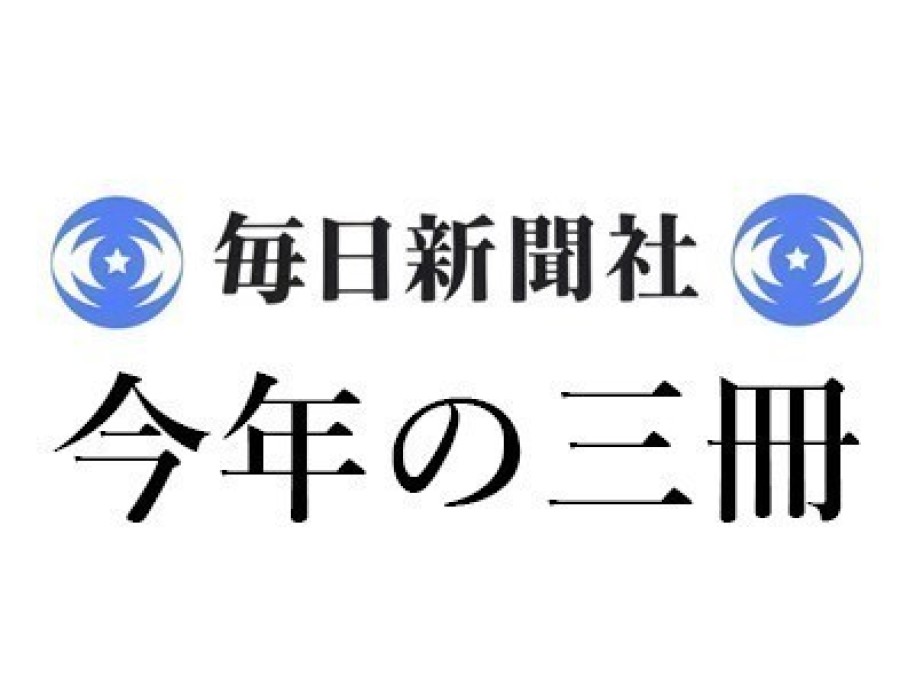書評
『ゾラと世紀末』(国書刊行会)
ゾラという名前を聞いて、日本の平均的読者はどのようなイメージを思い描くだろうか。遺伝学を応用した科学的な実験小説、悲惨な題材を好んで取り上げた現実暴露の自然主義といった文学史の受け売りによる紋切り型知識でもあればまだいい方で、たいていは、原作を手に取ったこともないのに、「退屈」「暗い」「古くさい」「陰気」等々の予断的イメージだけで事足れりとしてしまっているのではなかろうか。
しかしながら、ひとたび偏見を捨ててゾラの作品、とりわけ代表作であるルーゴン=マッカール双書全二十巻を手にしてみれば、どんな軽薄短小好みの読者でも、その面白さに、完全に脱帽するにちがいない。しかも、それは、いったん古びたものが、また新しく見直されるといった循環性の面白さでは断じてなく、あらゆる時代的制約を越えたところで強烈に輝く魅力なのである。筆者はこれに気付いて以来、方々で、「ゾラはすごい」と触れてまわっていたが、翻訳が、『居酒屋』と『ナナ』しかなく、またルーゴン=マッカール双書の全貌(ぜんぼう)を紹介した日本語の研究書も存在していない現状では、いかんともしがたかった。
ところがここに、待望ひさしいゾラ復権のための書が現れた。しかも文学史のレッテルとは無縁の、「黙示録的叙事詩人」という観点からルーゴン=マッカールを読み解こうとする意欲的な研究書である。まさに旱天(かんてん)の慈雨とはこのことだろう。
全体は「世紀末の叙事詩人ゾラ」の序文に始まって、『クロードの告白』と『制作』を取り上げてゾラの内面の真実に迫った第二章「二つの自伝的作品」、『居酒屋』と『ナナ』、『ジェルミナル』と『大地』を構造的に分析した第三章「書き出しと終行」、『夢』『ボヌール・デ・ダーム百貨店』『血』『壊滅』を通してゾラの神話的性格を抽出した第四章「幻想と神話」、『パリ』によってゾラの未来観を探った第五章「世紀末との対決」に大別され、それぞれ個々の作品の本質が適確に指摘されているが、筆者がなににもまして注目したのは、近代の矛盾が一度に噴き出した世紀末を、「生と死」「狂気と崩壊」などの象徴的なイマージュの奔流によって描き出した黙示録的予言者ゾラの姿が、遺伝法則を援用する科学者ゾラという外貌を突き破るようにして蘇(よみがえ)ってくることだろう。すなわち読者は、本書において、自然主義の客観的小説家という古めかしいイメージにかわって、近代のダイナミズムを神話的スケールで描く叙事詩人、という新しいイメージが誕生する光景に立ち会うことになるのである。
ところで、唐突な連想で恐縮だが、筆者は本書を読みながら、SF作家シオドア・スタージョンの『人間以上』という小説を思い出していた。というのも、それぞれ別の欠陥を持って生まれた障害児たちが、一つの人格に融合してゲシュタルト・マンを形成し、《人間以上》のパワーを持つに至る過程を描いたスタージョンのSFと同様に、ゾラの小説はすべて、個々の登場人物が「機関車」や「デパート」や「大地」や「炭鉱」などの象徴へと融合し黙示録的神話を形づくるという点において、まさしくゲシュタルト小説と呼ぶのにふさわしいからである。そして、「個人」が死に絶え、「法人」がひとり歩きする現代の社会において真に蘇るべきは、こうした叙事詩的な規模をもったゲシュタルト小説なのではなかろうかと考えた。この意味で、十九世紀の世紀末の黙示録を書いたゾラは二十世紀の世紀末においてこそ読まれるべき小説家なのである。
なお、本書の巻末には詳細を究めた年表ばかりでなく、ルーゴン=マッカール双書を初めとするゾラの主要作品の梗概、ルーゴン=マッカール家の系統樹、日仏のゾラ文献も付されているので、フランス文学の専門家のみならず、日本文学の研究家にとっても必要不可欠な文献となるだろう。
【この書評が収録されている書籍】
しかしながら、ひとたび偏見を捨ててゾラの作品、とりわけ代表作であるルーゴン=マッカール双書全二十巻を手にしてみれば、どんな軽薄短小好みの読者でも、その面白さに、完全に脱帽するにちがいない。しかも、それは、いったん古びたものが、また新しく見直されるといった循環性の面白さでは断じてなく、あらゆる時代的制約を越えたところで強烈に輝く魅力なのである。筆者はこれに気付いて以来、方々で、「ゾラはすごい」と触れてまわっていたが、翻訳が、『居酒屋』と『ナナ』しかなく、またルーゴン=マッカール双書の全貌(ぜんぼう)を紹介した日本語の研究書も存在していない現状では、いかんともしがたかった。
ところがここに、待望ひさしいゾラ復権のための書が現れた。しかも文学史のレッテルとは無縁の、「黙示録的叙事詩人」という観点からルーゴン=マッカールを読み解こうとする意欲的な研究書である。まさに旱天(かんてん)の慈雨とはこのことだろう。
全体は「世紀末の叙事詩人ゾラ」の序文に始まって、『クロードの告白』と『制作』を取り上げてゾラの内面の真実に迫った第二章「二つの自伝的作品」、『居酒屋』と『ナナ』、『ジェルミナル』と『大地』を構造的に分析した第三章「書き出しと終行」、『夢』『ボヌール・デ・ダーム百貨店』『血』『壊滅』を通してゾラの神話的性格を抽出した第四章「幻想と神話」、『パリ』によってゾラの未来観を探った第五章「世紀末との対決」に大別され、それぞれ個々の作品の本質が適確に指摘されているが、筆者がなににもまして注目したのは、近代の矛盾が一度に噴き出した世紀末を、「生と死」「狂気と崩壊」などの象徴的なイマージュの奔流によって描き出した黙示録的予言者ゾラの姿が、遺伝法則を援用する科学者ゾラという外貌を突き破るようにして蘇(よみがえ)ってくることだろう。すなわち読者は、本書において、自然主義の客観的小説家という古めかしいイメージにかわって、近代のダイナミズムを神話的スケールで描く叙事詩人、という新しいイメージが誕生する光景に立ち会うことになるのである。
ところで、唐突な連想で恐縮だが、筆者は本書を読みながら、SF作家シオドア・スタージョンの『人間以上』という小説を思い出していた。というのも、それぞれ別の欠陥を持って生まれた障害児たちが、一つの人格に融合してゲシュタルト・マンを形成し、《人間以上》のパワーを持つに至る過程を描いたスタージョンのSFと同様に、ゾラの小説はすべて、個々の登場人物が「機関車」や「デパート」や「大地」や「炭鉱」などの象徴へと融合し黙示録的神話を形づくるという点において、まさしくゲシュタルト小説と呼ぶのにふさわしいからである。そして、「個人」が死に絶え、「法人」がひとり歩きする現代の社会において真に蘇るべきは、こうした叙事詩的な規模をもったゲシュタルト小説なのではなかろうかと考えた。この意味で、十九世紀の世紀末の黙示録を書いたゾラは二十世紀の世紀末においてこそ読まれるべき小説家なのである。
なお、本書の巻末には詳細を究めた年表ばかりでなく、ルーゴン=マッカール双書を初めとするゾラの主要作品の梗概、ルーゴン=マッカール家の系統樹、日仏のゾラ文献も付されているので、フランス文学の専門家のみならず、日本文学の研究家にとっても必要不可欠な文献となるだろう。
【この書評が収録されている書籍】
図書新聞 1992年5月23日
週刊書評紙・図書新聞の創刊は1949年(昭和24年)。一貫して知のトレンドを練り続け、アヴァンギャルド・シーンを完全パック。「硬派書評紙(ゴリゴリ・レビュー)である。」をモットーに、人文社会科学系をはじめ、アート、エンターテインメントやサブカルチャーの情報も満載にお届けしております。2017年6月1日から発行元が武久出版株式会社となりました。
ALL REVIEWSをフォローする