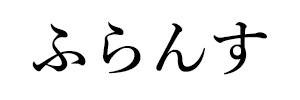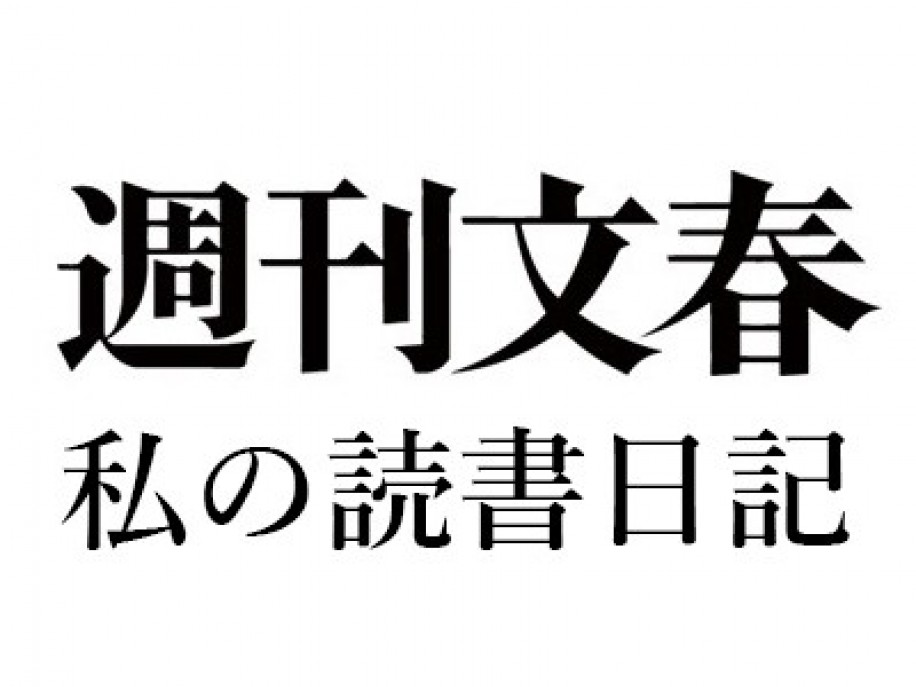書評
『ユリシーズの涙』(みすず書房)
犬の悲しみに同化する断章群
ロジェ・グルニエは、猫派の人々に対抗するそぶりも見せずに、淡々と犬の悲しみを顕揚する。この小さな一書に盛られた文学者と犬をめぐるエピソードの数々は、楽しく麗しい日々の記憶ではなく、むしろ幸福の時代をともに過ごした同伴者なきあとの、しんみりした時間からの恢復であるかのようだ。ちょっとした共犯意識にもとづく笑いもあちこちに響いているとはいえ、どの頁からも、主人の行動のひとつひとつに意味を見出そうとする犬たちの、動物としての境界線を犬の足裏半分くらい踏み出してしまった、つまり人間化し、社会化した動物の宿命がじわじわとにじみ出している。宿命の一語をこちらにつよく感じさせるという点で、ユリシーズと名付けられたグルニエの愛犬のエピソードは、他の諸々の「犬生」をとりまとめるにあたっても有効だろう。この本は文学に鼻の利く物静かな犬を自由に散歩させてできあがった地図のようでもある。ボードレール、スタンダール、カフカ、リルケ、ヴァレリー、ラルボー、ロマン・ガリー、シモーヌ夫人、チェーホフ、ツルゲーネフ、ブルガーコフ、アクショーノフ、シルヴィー・ジェルマン、そしてダニエル・ペナック。作品や人を通じて親しくまじわった文学者と飼い犬の地勢図を、グルニエは気取らずに描いていく。
犬と人間の関係は、文明文化がどのように推移しようと、野生のオオカミから手なずけてつくりあげたこの動物が人間の生活範疇に入り込んで以来、ほとんど変わっていないし、またこれからも変わることがない。犬にとっては、主人の行動ひとつひとつが、自分にとってどんな利益をもたらし、どれほどの愛情を注がれる契機となるのかの試験紙みたいなものだから、その日常は泰然自若とした猫のそれとは比較にならない緊張に満ちている。
逆にまた、人間は人間で、絶望に打ちひしがれていたときに近寄ってくる犬たちに、深く慰められる。犬はそのたびに主人を思って涙を流し、主人は愛犬の死に打ちひしがれる。その悲しみや滑稽さをことごとくぬぐい去る良薬は、どこにも見あたらないだろう。だが、グルニエがあげているいくつもの事例のなかでもっとも納得させられるのは、憎しみや愛情を超えた、動物としての結びつきに言及する次の一節ではあるまいか。
ドイツで、ユダヤ人戦争捕虜からなる森林作業班に入れられたエマニュエル・レヴィナスは、看守はおろか、通りがかりの人々にとっても、自分はもはや人間に属していないのだと悟った。ところが一匹の迷い犬がやってきて、仲間に加わったという。疑いの余地なく、「この犬にとって、われわれは人間であった」のである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする