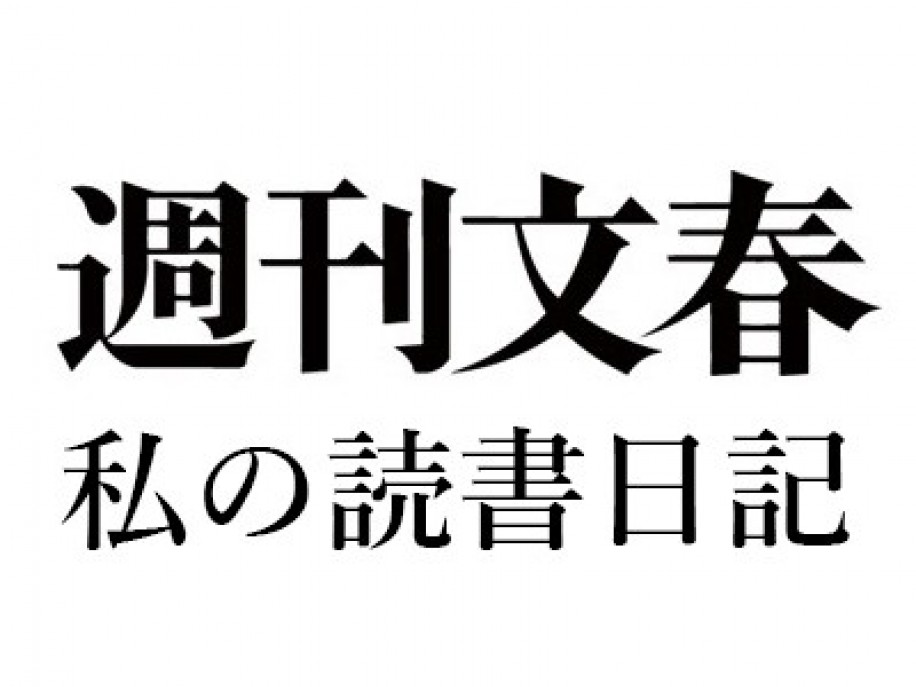書評
『イデーの鏡』(白水社)
地下室は「生」屋根裏部屋は「死」
あることの特徴を理解しようとするとき、反対のものをもってきて併置すると、その特徴が際立って見えることがある。たとえば、神と悪魔、男と女、動物と植物、ドン・ジュアンとカサノヴァ、ネコとイヌ、フォークとスプーン、風呂とシャワー、主人と召使い。本書は、こうした対立するさまざまな概念や事物を並べることで、一つでは鮮明でなかった特徴を発見し、これを大いに楽しもうという趣向の本である。
孤立した概念(コンセプト)だと、それについての思索は、なんというか、つるつるした表面をなぞっているだけで、それをうち破って、内側に入りこめないような気がする。しかしながら、そこに対立概念を、ぽんと置いてみれば、その表面がぱんとはじけて、透けて見えるようになり、奥深いところの構造が読み取れるのだ
試みが成功しているものもあるし、失敗しているものもある。
同じ動物の対照でも、イヌが有用性に生きるのに、ネコは無用性に生き、イヌは仲間を探し、群れたがるが、ネコは孤独を好むという「ネコとイヌ」は案外平凡で面白くないが、雄牛に対して馬を配した「雄牛と馬」はなるほどと思わせる。すなわち、雄牛の力は肩の部分に集まっているのにお尻は貧弱だから、これは男性の象徴、一方、馬のすべては臀部(でんぶ)にあるから、こちらは女性らしさを現す動物であるという。
しかし、『魔王』『赤い小人』の小説家であるトゥルニエの特徴がいかんなく発揮されるのは、こうした観念的な分析よりも、むしろ、対概念をもってくることで喚起されるイメージの飛躍力の方である。
その良い例が「地下室と屋根裏部屋」。両者は暗いという点では同じだが、その暗さの中味はずいぶんちがう。地下室の明かりは地面からやってくるから「清浄ならざる光」であるのに、屋根裏部屋のそれは天窓から入る空の光だ。だから、地下室が「死」で、屋根裏部屋が「生」かと思うと、実は逆で、地下室は「生命の場所」で、屋根裏部屋は「死の場所」なのだそうだ。なぜかといえば、屋根裏部屋は乳母車や手足のもげた人形、裂けた麦藁(むぎわら)帽子、ページの黄ばんだ絵本などしまっておく「過去を向いた存在であって、記憶と保存がその機能」であるのに対して、ワインが寝かせられ、冬用の豆炭が準備され、ジャガイモの山がくすんだ光を放つ地下室では「次の季節が熟している」から「生の場所」なのだ。「そう、地下室には、しあわせの約束が埋もれているのだ。その家の生きた根っこが、地下室まで深くのびているのである。かたや屋根裏部屋には、思い出や詩情がただよっている」
「風呂とシャワー」では、風呂派は右翼で、シャワー派は左翼と分類される。なぜか? 風呂に入った人は羊水に浮かぶ胎児のような心地よい退行状態にあり、何よりも浴槽から出ることを恐れる。これに対して、シャワーを浴びる人は、澄んだ水をバジバジと体に当て、仕事のために新たな一日にむかって飛び出していく。「シャワーを浴びる人間には、道徳的な輝きをも含めて、清潔さへの思いがとりついている。いっぽう、湯浴みをする人にとって、清潔さとは、ほとんどどうでもいいことなのである」
この種の対概念遊びを面白いと感じる人は御一読あれ、そうは思わない人はこの書評だけで充分です。これも対概念遊びの一つ。各章の末尾の引用も気がきいている。(宮下志朗訳)
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする