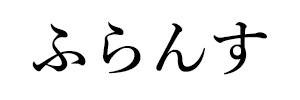書評
『ラバ通りの人びと―オリヴィエ少年の物語1』(福音館書店)
少しだけみなしごでありつづける物語
ロベール・サバティエの『舗道のうえのデッサン』をリーヴル・ド・ポッシュ版で読んだのは、もうずいぶんむかしのことだ。一九六四年に刊行された小説で、筋書きなどきれいに忘れているといったほうが正しいのだけれども、サン・トギュスタン河岸沿いに店を構えて古書やオブジェを扱っている中年の語り手が、舗道にチョークで絵を描いていた男女と出会い、またひとりの船乗りと知り合って得た時間を、書くことで生き直そうとする、さほど新味のない自己再生の試みだった。ただひとつはっきり記憶しているのは、語り手が祖母の思い出に触れている頁があったことである。だしぬけに挿入されたそのエピソードが主人公の心象とどのように関連づけられるのか私にはすぐ理解できず、しかも祖母が住んでいる「ソーグ」という土地に関する知識がなかったため、地図を開いて場所を確認した覚えがあるのだ。オート・ロワール地方の町、ソーグ。語り手の祖母は、松やエニシダやナナカマドや羊歯(しだ)が生い茂り、干し草を運ぶ牛車が通るこの町で蹄鉄工の夫と暮らしていた。進歩的な夫に文字を教わる例外的な境遇にあったものの、本などとはあまり縁がなく、先祖代々の習慣を忠実に守っている。そんな祖母の暮らしのリズムを知る語り手は、文明が決定的な断絶を迎える時期に生きる人間として、つまり裂け目の前後を知る最後の世代としてみずからを位置づけていた。じっさいには一頁にも満たない記述で、断絶の内容が具体的に描かれているわけではなかったのだが、私はソーグという音だけを鼓膜に刻み、表紙の片隅に印刷された《『スウェーデン製のマッチ』の作者による》という惹句を網膜に焼きつけながら、わざわざ他の作品を注文するのも億劫だったのだろう、そのままサバティエとは疎遠になってしまった。
ところがありがたいことに、このたび福音館書店から第三巻をもって完結した同じ作者の《オリヴィエ少年シリーズ》が、かつての謎や不満をやさしく解き明かしてくれたのである。『スウェーデン製のマッチ』(一九六九)は、『ラバ通りの人びと』の表題で訳出された第一巻にあたり、ソーグは主人公の両親が出会う故郷だったのだ。第二巻『三つのミント・キャンディー』(一九七二)につづく完結篇は、『野生のハシバミ』(一九七九)あらため『ソーグのひと夏』。内容に即した的確で美しい邦題であるばかりでなく、ソーグの一語がタイトルに組み入れられたことで、他のいつでもない「その年の夏」に、くっきりとした輪郭が与えられることになった。
シリーズ全体の時代背景は、一九三〇年代のフランス。「不思議なくらい深い緑色をした大きな目」の、十歳になる主人公オリヴィエ・シャトーヌフがたどる運命は、大筋で作者の経歴と一致している。一九二三年、パリに生まれたサバティエははやくに両親を亡くし、印刷所を営んでいた伯父に引き取られており、幼年と少年の端境期に味わいつくした孤独と歓びの核がそのまま作品に埋め込まれているのだ。少年オリヴィエのふるさとは、モンマルトルの裏手、まだ《村》の雰囲気を漂わせているラバ通りの、祝祭と幻想に満ちた空間である。母親ヴィルジニーは小間物屋の主人として女手ひとつで息子を育ててきたのだが、開巻早々わずか三十歳で急死。物語は一挙に、伝統的な「みなしご」譚の系譜に位置づけられる。本国における『ラバ通りの人びと』の成功には、不遇で多感な少年が周囲の助けを得ながら卑屈にならず、明るく強く生き抜いていくさまに読者が勇気づけられるという孤児物の定型と、それを軽やかに超えていく文体の創出があずかっているだろう。
もっとも少年の境遇はそれほど悲惨なものではない。母親の死後、彼女のいとこで印刷所につとめているジャンとその妻エロディーのもとにひとまず身を寄せ、第二巻では、サン・マルタン運河沿いで紙の卸し業を仕切っていた裕福なアンリ・デルソー伯父――ただしオリヴィエと血のつながりがあるのは妻のヴィクトリアのほう――に引き取られ、街頭に放り出されたり孤児院に入れられたりする気配はないからだ。少年が耐えなければならないのはむしろ、社会の底辺で頑張っている個性豊かな人間たちに支えられた村落共同体的なモンマルトルの下町から、ウェストミンスター式大時計が時を打つ世界、ふたりの女中を抱えるブルジョワ世界に入り込んだときの、環境の変化の方なのである。
デルソー家には、胸を病んでスイスのサナトリウムに入っている長男マルソーと、元気のいい丸々とした次男ジャミという兄弟がいて、オリヴィエはとくに年齢の近いマルソーと仲良くなるので、天涯孤独というわけでもないのだが、ヴィクトリア伯母が貸してくれた『家なき子』に没頭し、身体が震えるほどの感動を味わう少年の心から「みなしご」意識が完全に消え去ることはなかった。「子ども時代にみなしごになると、いつまでも、少しだけ、みなしごでありつづける」とつぶやく彼の言葉は、三つの物語に通底する寂しさと、それに倍するやさしさの、大切な素地となっている。
幸運だったのは、伯父と伯母がそれぞれに苦しい時代を忘れず、慢心しない気さくな人物であったことである。かつてバリトン歌手を目指していた芝居好きの伯父が甥っ子をつれて馴染みのカフェやパサージュを散歩してまわる数頁は、胸躍らせるすばらしい「男の友情」を証す場面だし、躾に厳しく仕事熱心だが、からりとして他人に理解のある伯母は、なによりもまだ見ぬ故郷ソーグの匂いを感じさせる点でただの成金と一線を画している。
ラバ通りを去って一年後、オック語が残る独自の文化圏ソーグの祖父母のもとでオリヴィエが夏を過ごす第三巻は、自身のルーツ発見の物語として、また「エスクーラの旦那」と呼ばれて敬愛されている祖父や『舗道のうえのデッサン』でひと筆書きされていた、無愛想だが気持ちの澄んだ祖母の姿を伝える愛の物語として、他国の、それも半世紀以上も過去の話とは思えない近しさを感じさせてくれる。
少年は都市のなかの「田舎」に見立てられたラバ通りに暮らすことで、首都と地方を、過去と現在を一身に引き受ける幸福にめぐまれ、パリのパサージュやソーグの村でも、この通りの人々の匂いを見出していく。全巻を通じていくらか過剰なほど列挙されている生活用品の名が取り結ぶ前世代との記憶の共有は言うに及ばず、ふたつの時空がなめらかに浸透しあい、どちらの側にも不均衡がでないよう心の秤が調整されたとき、オリヴィエは人生における第二の季節を迎え、やがて自分の生きた一時期が、小さな雨に降られただけで消えてしまうあの舗道に描かれたチョークの絵のようにはかなく、それゆえに貴重なものであることを、深く脳裡に刻むだろう。
愛情のこもった訳文と各巻の丁寧な解説が、シリーズの魅力をいっそう高めている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする