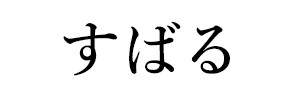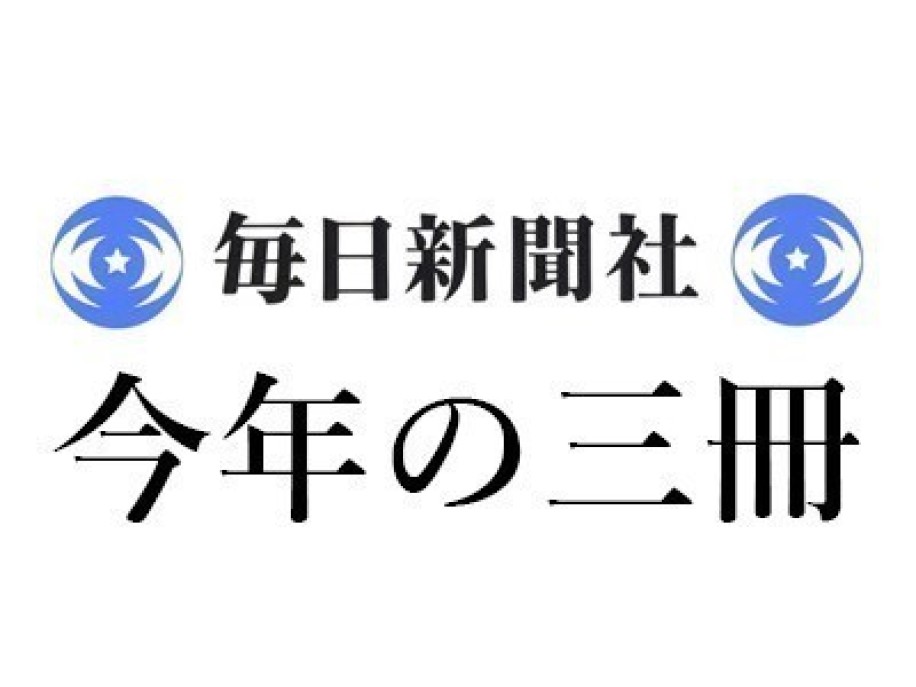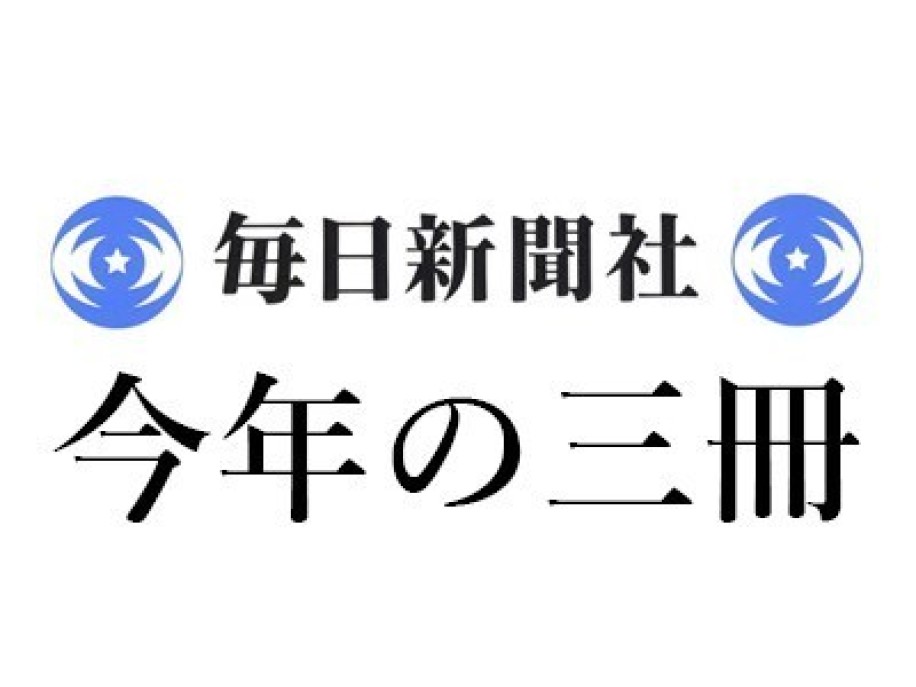書評
『フーコン戦記』(文藝春秋)
わからないことの「回りあんどん」
古山高麗雄の小説には、罪を認めるとか認めないとかの問題を超えたところから響いてくる声がある。現在の文体と比べればやはり若々しさが感じられる『プレオー8の夜明け』(講談社文芸文庫)においても、枯淡と言って差し支えない『セミの追憶』(新潮社)においてもそれは変わらないし、本書『フーコン戦記』でも同様だ。日本軍が英印軍の攻撃で壊滅したインパール戦のみ語られがちなビルマ戦線における、もうひとつの地獄であったフーコン。土地の言葉で「死の谷」を意味するこの場所から、左肘の先を奪われて生還した辰平が、戦友の戸之倉とのあいだでも口にせず、自慢話みたいだと難じられて以後は孫にも語らず、東京の小説家からの取材の申し込みにすら応じなかった戦時の記憶の糸を、結婚したばかりの主人をおなじ土地で亡くした戦争未亡人の文江といっしょに縒りはじめる。当時の軍部は、いったいなぜ負けると判っている場所に兵士を送り込んだのか。上意下達の末端で、なにも知らされずただ盤上戦術の駒のごとく操られ、棄てられた自分にとって、作戦だの国だのはいったいどんな意味があるのか。辰平は文江が揃えているフーコン関係の著作をあたり、白地図を埋めながら、当時もいまも理解できないおのれの位置をたしかめようとする。
しかしそれがどうだというのか。さまざまな情報を把握していた上官たちの行動でさえ、回想録の形をとった途端に主観が介入してどこかが歪むのだから、淡泊な数字が並んでいる文書でもないかぎり、すべては茫洋とした霧のなかに包まれてしまう。おまけに辰平のような一兵卒には、死地のなかで物を書きたいという欲望など生ずるはずもなく、国のためどころか、まずは自身の命が奪われることの恐怖に怯えていたのだから。妻の静子は、満州での少女時代について口を閉ざしたまま死んだ。戸之倉は戦場での自分の姿すら覚えていないという。フーコンに対する文江の執着も、その理由が掴みきれない。「人は、わからないことの『回りあんどん』だ」と彼はつぶやく。「他人はすべてわからない。ただ、わからないことが気になる人がいて、そうでない人がいる」。
達観というにはあまりに厳しい結論である。かつて日本が犯した戦争の愚は、「気になる人」の心にだけ存在しているのだ。辰平の、そして著者の孤独は、いまこの国で、「気にならない人」を容認しつつ生きていかなければならないことなのであり、もしかするとそれはフーコンよりも過酷な戦闘なのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする