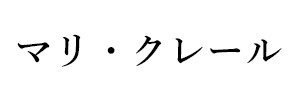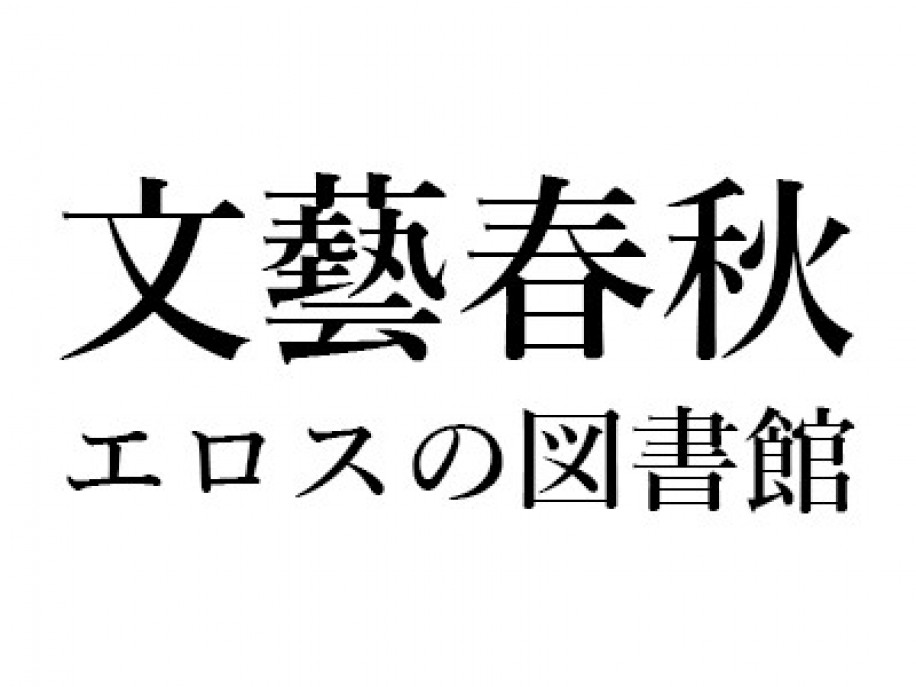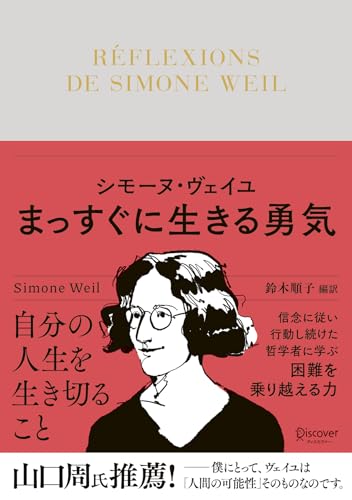書評
『娼館の黄金時代』(河出書房新社)
ファンタスムという精神分析の用語がある。ようするに、人がそれを思い浮かべると最も激しい性的興奮を味わう心的イメージのことで、それこそ百人いれば百通りのファンタスムが存在する。レディース・コミックなどを覗くと、まさにこのファンタスムの花ざかりといった感じがするが、なぜか女性のファンタスムに関してはあまりヴァリエーションに富んだものはないようである。これに対し、男というのは想像力の動物なのか、単純なSMから、「超」のつくような変態まで、じつに驚くほど多様なファンタスムを持っている。それをあらためて認識させてくれたのが、メゾン・クローズ、すなわち、第二次世界大戦までフランスに存在していた、政府公認の娼館の歴史を辿(たど)った本書である。
最近、アラン・コルバンをはじめとして、売春に関するさまざまな社会史的研究が出版され、ブルジョワ社会が自らを性病の恐怖から守るため、売春婦を精液の排水溝と規定して、これを一定のゾーンに囲い込もうとした事実が明らかにされているが、本書は、そのような社会史的記述とは無縁の、どちらかといえば、過ぎし良き時代のメゾン・クローズをノスタルジックに回顧しようとする本である。とはいえ、社会史のいささか鈍重な記述に飽きた読者としては、本書のような好奇心丸だしの態度が、むしろ新鮮なものに映ったことは確かである。というのも、メゾン・クローズは単に性欲の処理場であっただけではなく、男たちがファンタスムを実現するための想像力の装置でもあったことを教えてくれるからだ。
ところで、この想像力の装置の動力源は金である。しかも、そのファンタスムが風変わりなものであればあるほど、料金もかさむ。したがって、メゾン・クローズは、ファンタスムのためとあらば金に糸目をつけない社会のエリートを得意客とするところが多かった。なかでも、プロヴァンス通り一二二番地にあった、「ワン・トゥー・トゥー」やモンパルナスの「スファンクス」は、贅を尽くした作りと、どんなファンタスムにも応じられる対応性において、地上の楽園とでもいえる超高級娼館で、世界中の王侯貴族がここに日参した。
こうした高級店の一つ、「ル・シャバネ」の一番の上得意は、後にエドワード七世となったイギリス皇太子だった。皇太子は、自らのファンタスムを実現するために、トレーニング・マシンにも似た摩訶不思議な構造の「愛の椅子」を作らせた。その写真が出ているが、どうやって利用するのか、いくら頭をひねってもわからない。また皇太子は、特製の浴槽にシャンペンを注がせ、お気にいりの娼婦に入浴させてから、友人たちとこれを飲んだ。この浴槽はその後、競売に付され、サルバドール・ダリの手に渡った。金満家たちによる乱痴気騒ぎも繰り返された。アメリカの鉄鋼王は、娼婦の全身にキャビアを塗ってカウンターに寝かせ、客に代わる代わるこれをなめさせたりした。
だが、やはり愉快なのは、変態的な客たちのファンタスムである。SMの拷問部屋は高級店の標準装備だったが、多かったのはM客のほうで、中に一人、多和田葉子の『犬婿入り』の青年のような犬男がいた。「店にきて素裸になると、彼はようやく彼自身にもどる。首輪と綱をつけ、床に餌皿をおいて食べたり飲んだりする」。ようするに人間が犬に変身するのではなく、普段は犬が人間に変身して社会生活を営んでいるのである。また、馬男というのもあった。この男の楽しみは、拍車つきのブーツを娼婦にはかせて、これで脇腹を蹴ってもらうことだった。社会史的におもしろいのは、子供に変身し、小間使いの恰好をした娼婦に折檻(せっかん)されるのを好んだ客が多かった事実で、これなど当時の上流階級の男性ファンタスム形成に小間使いの果たしていた役割がいかに大きかったかが想像できて興味ぶかい。
とはいえ、著者たちは、こうしたファンタスムの装置が、商業という冷徹な論理に貫かれていたことも忘れてはいない。とりわけ、娼婦を斡旋する口入れ業者やヒモ、やり手婆たちの生態は詳しく描かれている。ただ著者たちの立場を反映しているのか、娼婦たちの心理や社会的状況への考察は、ほとんど省略されている。いずれにしろ、一九四六年に公認娼家廃止法案が可決されるまで、メゾン・クローズは第三共和制、いや世界中のファンタスムを一人で引き受けるかたちで存在しつづけた。その廃止のきっかけとなったのは、メゾン・クローズが占領下でナチ、とりわけ、ゲシュタポに協力的だったため、というが、これなども、ドイツ人がパリに対して寄せるファンタスムの過剰が原因だった、といえなくもない。とすれば、メゾン・クローズは、自らが搔き立てたファンタスムに復讐されたことになるのではなかろうか。
文章部分のレイアウトがまずく、読みにくいのが難点である。
【この書評が収録されている書籍】
最近、アラン・コルバンをはじめとして、売春に関するさまざまな社会史的研究が出版され、ブルジョワ社会が自らを性病の恐怖から守るため、売春婦を精液の排水溝と規定して、これを一定のゾーンに囲い込もうとした事実が明らかにされているが、本書は、そのような社会史的記述とは無縁の、どちらかといえば、過ぎし良き時代のメゾン・クローズをノスタルジックに回顧しようとする本である。とはいえ、社会史のいささか鈍重な記述に飽きた読者としては、本書のような好奇心丸だしの態度が、むしろ新鮮なものに映ったことは確かである。というのも、メゾン・クローズは単に性欲の処理場であっただけではなく、男たちがファンタスムを実現するための想像力の装置でもあったことを教えてくれるからだ。
ところで、この想像力の装置の動力源は金である。しかも、そのファンタスムが風変わりなものであればあるほど、料金もかさむ。したがって、メゾン・クローズは、ファンタスムのためとあらば金に糸目をつけない社会のエリートを得意客とするところが多かった。なかでも、プロヴァンス通り一二二番地にあった、「ワン・トゥー・トゥー」やモンパルナスの「スファンクス」は、贅を尽くした作りと、どんなファンタスムにも応じられる対応性において、地上の楽園とでもいえる超高級娼館で、世界中の王侯貴族がここに日参した。
こうした高級店の一つ、「ル・シャバネ」の一番の上得意は、後にエドワード七世となったイギリス皇太子だった。皇太子は、自らのファンタスムを実現するために、トレーニング・マシンにも似た摩訶不思議な構造の「愛の椅子」を作らせた。その写真が出ているが、どうやって利用するのか、いくら頭をひねってもわからない。また皇太子は、特製の浴槽にシャンペンを注がせ、お気にいりの娼婦に入浴させてから、友人たちとこれを飲んだ。この浴槽はその後、競売に付され、サルバドール・ダリの手に渡った。金満家たちによる乱痴気騒ぎも繰り返された。アメリカの鉄鋼王は、娼婦の全身にキャビアを塗ってカウンターに寝かせ、客に代わる代わるこれをなめさせたりした。
だが、やはり愉快なのは、変態的な客たちのファンタスムである。SMの拷問部屋は高級店の標準装備だったが、多かったのはM客のほうで、中に一人、多和田葉子の『犬婿入り』の青年のような犬男がいた。「店にきて素裸になると、彼はようやく彼自身にもどる。首輪と綱をつけ、床に餌皿をおいて食べたり飲んだりする」。ようするに人間が犬に変身するのではなく、普段は犬が人間に変身して社会生活を営んでいるのである。また、馬男というのもあった。この男の楽しみは、拍車つきのブーツを娼婦にはかせて、これで脇腹を蹴ってもらうことだった。社会史的におもしろいのは、子供に変身し、小間使いの恰好をした娼婦に折檻(せっかん)されるのを好んだ客が多かった事実で、これなど当時の上流階級の男性ファンタスム形成に小間使いの果たしていた役割がいかに大きかったかが想像できて興味ぶかい。
とはいえ、著者たちは、こうしたファンタスムの装置が、商業という冷徹な論理に貫かれていたことも忘れてはいない。とりわけ、娼婦を斡旋する口入れ業者やヒモ、やり手婆たちの生態は詳しく描かれている。ただ著者たちの立場を反映しているのか、娼婦たちの心理や社会的状況への考察は、ほとんど省略されている。いずれにしろ、一九四六年に公認娼家廃止法案が可決されるまで、メゾン・クローズは第三共和制、いや世界中のファンタスムを一人で引き受けるかたちで存在しつづけた。その廃止のきっかけとなったのは、メゾン・クローズが占領下でナチ、とりわけ、ゲシュタポに協力的だったため、というが、これなども、ドイツ人がパリに対して寄せるファンタスムの過剰が原因だった、といえなくもない。とすれば、メゾン・クローズは、自らが搔き立てたファンタスムに復讐されたことになるのではなかろうか。
文章部分のレイアウトがまずく、読みにくいのが難点である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする