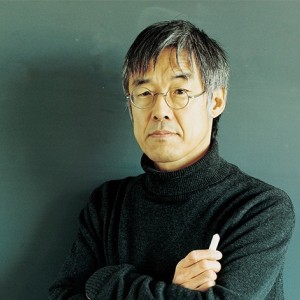書評
『発情装置 新版』(岩波書店)
上野千鶴子という装置
要するに、上野千鶴子は「危険な思想家」ということになってしまうのじゃないだろうか。ぼくは『発情装置』(筑摩書房)を読みながらそう思った。なぜ、彼女が「危険な思想家」かというと、それは彼女の指摘が、ぼくたちがふだん常識にしているようなことを木っ端みじんにしてしまうからだ。いや、「ふだん常識にしているようなこと」といっても、粉砕されてもかまわないようなどうでもいいことと生きる上で必要な常識というものがあるはずで、彼女が粉砕するのは後者の方なのだから、ぼくたちとしてはまいってしまい、慌てて本を伏せ思わず「これは読まなかったことにしよう」と呟いてしまうのである。
たとえば、常識は「売春は悪い」「買春は悪い」「レイプは悪い」という。イエス。しかし、なぜ悪いのか。悪いから悪い。これでは答えになってはいない。心身が傷つくから。そうかもしれない。じゃあ、なぜ売春や買春やレイプで心身が傷つくのか。当たり前じゃないか。当たり前では答えにならない。ここまで来てぼくたちは、これがひどく厄介な質問であることに気づく。なぜ、厄介な質問なのか。
ぼくたちがあまりに深く社会の教える常識で生きてきたために、そもそもそこにどんな問題があるのかさえ知らない領域が存在している。たとえば、それがセックスである。だから、ぼくたちは上野千鶴子を読む時、その批評の鋭さよりも、そこに問題があったのか! という目まいがするような驚きを感じるのだ。同じような驚きを、ぼくはゴダールの映画論を読む時にも、マルクスの経済学を読む時にも感じる。そして、ゴダールを読んだ後、映画は違って見え、マルクスを読んだ後、世界はやはり違って見える。そして、その厳しい批評は自らにも向けられる。
それがどんな未来なのかを、わたしに聞かないでください。マルクス流に言うなら「ありうべき社会における理想の関係についてわたしは語ることができない。なぜならわたしはこの性差別社会ですでに性別社会化を受けてきたせいで、わたしの想像力はこの地平を超えることがないから」とでも答えましょう。
ぼくたちはこの世界に生きている限り、この世界を超えて答えを出すことはできない。そして、もしそこに真の答えがあるとするなら、それはたぶんこの世界の向こうにしかないのだ。それを知りつつ、なおぼくたちは答えを求めて止まないのである。
性と人格が切り離されれば、売春はとくべつな労働ではなくなり、強姦は女性の尊厳に対するとくべつな侵害ではなくなります。松浦理英子さんが「嘲笑せよ、強姦者は女を犯せない」で主張したのはそのことでした。なぜ性器に対する暴力が、身体の他の部位に対する暴力とちがって特権的に人格を侮辱する行為と考えられるのか。そしてそのためになぜ、被害者はとくべつなトラウマを負わなければならないの? 他人から暴力を受けることはたしかにゆるしがたいことではあるけれども、なぜ不幸にして骨を折ったとか外傷を受けた、と同じように受けとめることができないのか。松浦さんのこの挑発的な文章が『朝日ジャーナル』に載ったとき、「強姦被害者の心情に無理解で、強姦犯を利するもの」という激しい反発が女性の読者から寄せられました。……。この論争が示すのも、性の「近代パラダイム」のどちら側に立つか、のちがいのようにわたしには見えます。たしかに現状では松浦さんの説は「現実的」ではないでしょうけれど、どちらが家父長制パラダイムの「改革者」であるかはあきらかです。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする