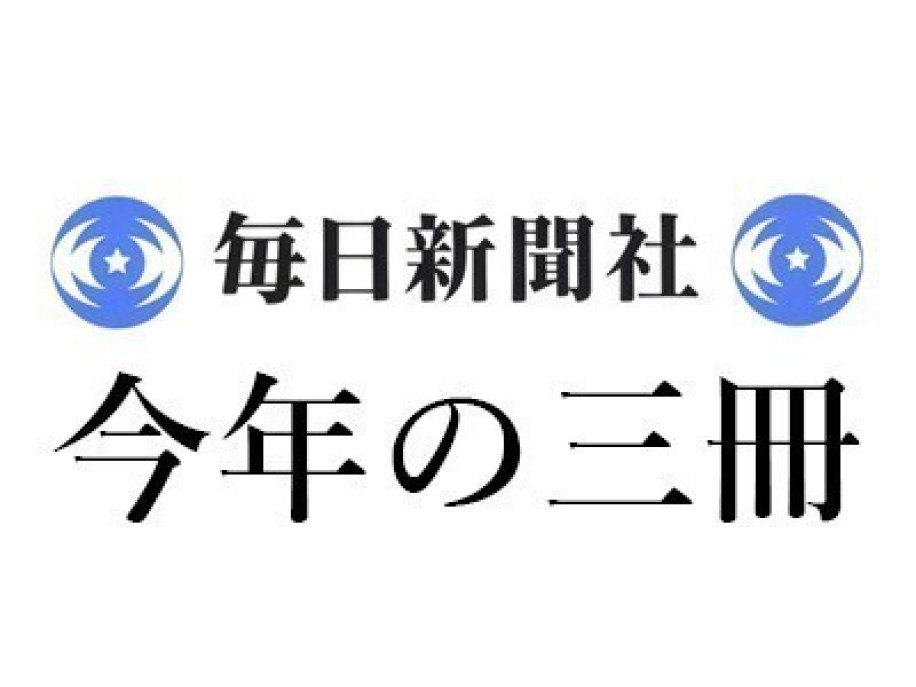書評
『ラジオデイズ』(河出書房新社)
フツーの人たち
『ラジオデイズ』(鈴木清剛著、河出書房新社)は「第三十四回文藝賞受賞作」で、新しい若い作家の書いた小説で、新人の作品を読む時にはいつもそうするように、ぼくはまず当人の写真とプロフィルを見て、なかなかいい面構えをしているなと呟き、一九七〇年生まれで、文化服装学院を卒業して、コムデギャルソンの企画生産部にいたことを発見し、これは面白そうだと思った。なぜなら、コムデギャルソンのデザイナー、川久保玲は(デザインの世界に限定しなくても)日本で革新・前衛という言葉を何十年も生きてきた、もしかしたら唯一の人物なのかもしれず、そのコムデギャルソンで企画に携わってそれから小説に転じたというのなら、「新しい」なにかを期待するのが当然ではあるまいか。そうやって、準備が終わると、ぼくはまず表紙を眺め、そこに雑然とした小さな畳の部屋が映り、たぶん若くて貧しい都市生活者の住むアパートの一室だなと思い、ではそんな若者は「いま」をどうやって生きているのか、それをこの小説は教えてくれるに違いないと思って頁を開きはじめた。
主人公の「カズキ」は高校を卒業すると「カセットテープを加工する工場に勤め」て三年がたち、「最終検品をする部署へと移され」る。そこでは「一本のテープを五人の人間が五回チェック」して「カズキは三番目に調べる係を担当していた」。それは「神経と目が疲れるだけの仕事」で、資本主義の下のいわゆる疎外された労働なのだから、主人公はそういう労働に従事せざるをえない若者の苦痛を描くのかと思うと、どうもそうではない。
その「カズキ」のところに、小学生の頃、友人であった、というより「全く最悪だと思いながらもずるずる」と友人のようになってしまい、そのことが軽いトラウマのようになっている「サキヤ」が突然現れ、理由も告げず、一週間居候させてくれと告げる。不意の闖入者、謎めいた行動。これはまた、小説にとっての豊かな原資ともいうべき素材で、いったいどんな秘密が「サキヤ」には隠されていて、そのことによって「カズキ」は苦痛と共にとてつもない事件に巻き込まれていくのではないかと思うが、「サキヤ」の行動の謎はあっさり解明され、特にどうってこともなくあっさりと「カズキ」のアパートを去ってゆく。
それから、「カズキ」には年が一つ下で「高校の頃アルバイトしていたコンビニエンスストアで知り合った」「チカ」という恋人がいて、その「どちらかといえばエキセントリックなものを欲する」「チカ」は高校を卒業してファッションデザインの専門校に入り「ラジカルで自己愛の強い仲間」と付き合いつつ、その仲間たちとは正反対で「よく言えば素朴で牧歌的。悪く言えば無気力で怠慢型。そ、よーするに牛みたいな」「カズキ」と付き合い続けている。となれば、刺激のなくなった「カズキ」との関係は、流動する社会の窓ともいえるラジカルな友人たちや、謎めいた「サキヤ」の出現によって激しく揺り動かされ、根本から危機を迎える――となりそうなはずなのに、ふたりは小説が終わりを迎えてもはじめと同じようにほのぼのとした関係を続けている。
いや、事件がないというのなら、その徹底した事件のなさによって逆に日常の「凄味」を表現した保坂和志の例もある。だが『ラジオデイズ』は、そういう「凄味」さえ回避しようとしているのである。
作者が描いたのは「フツーの人」だ。そして徹底して「フツー」であるとは、なんと普通ではないことか!
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする