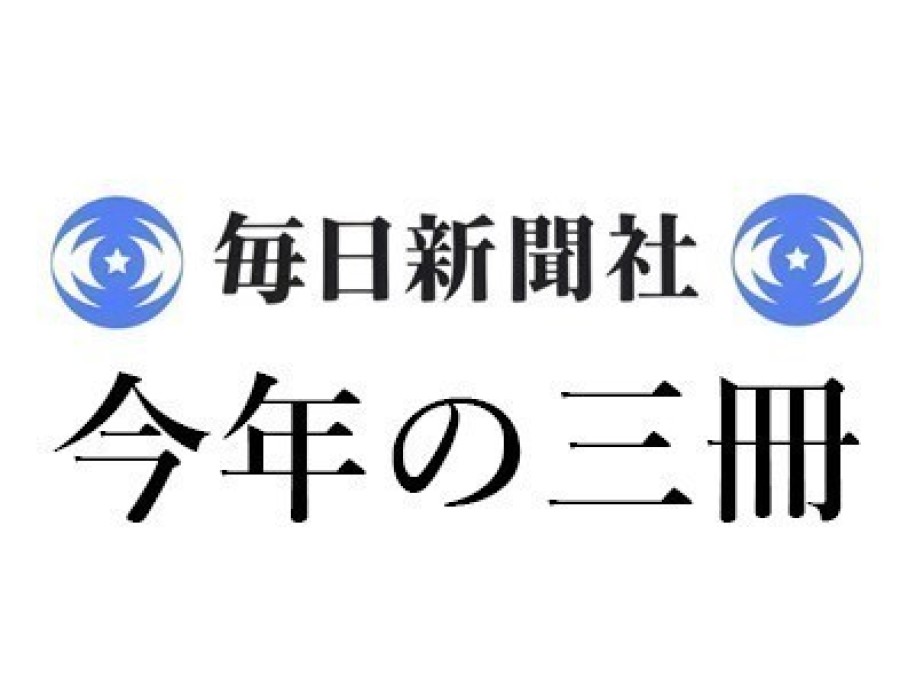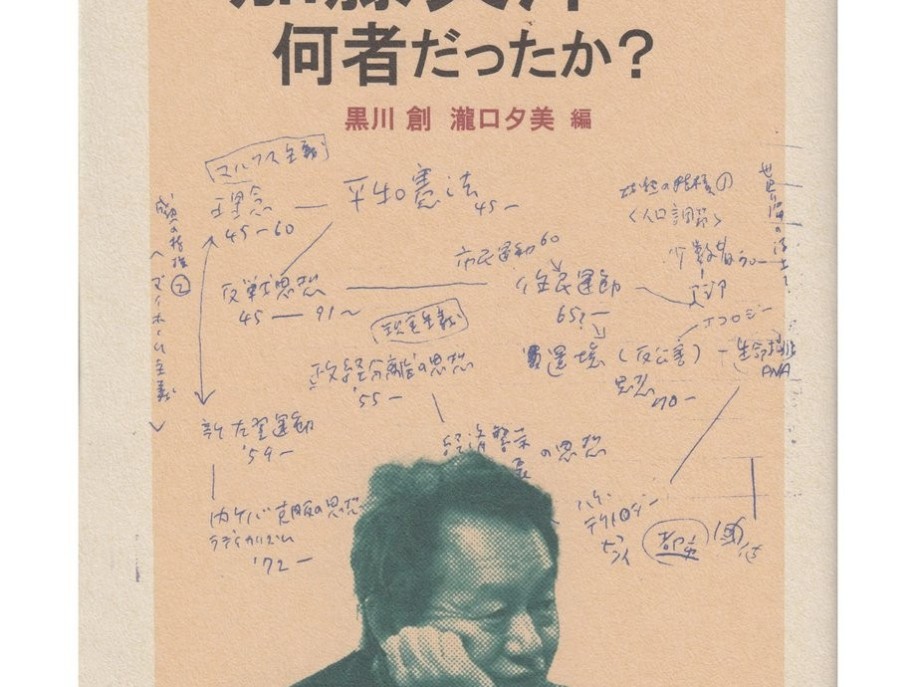書評
『敗戦後論』(筑摩書房)
書くべきだった本
本を読んでいて起こるもっとも奇妙なことは、これは自分が書いたんじゃないかと思えてしまう時があることだ。頭にどんどん入る、よくわかる、といった程度を超えて、読みながらもうその先を著者と一緒に考えて、というか書いているのである。
阿部和重さんの『インディヴィジュアル・プロジェクション』を読んでいる時、ぼくはなんだか自分が書いているような気がした(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1997年7月ごろ)。そして、加藤典洋さんの『敗戦後論』(講談社)を読んだ時も、そう、これはぼくが書いた、書くべきだった本だったのではないかと思ったのだった。
『敗戦後論』は「敗戦後論」「戦後後論」「語り口の問題」の三つのパートに分かれていて、その一つ一つが高い密度で書かれているのでこんな短いコラムで紹介するのは不可能だ。けれども、この三つのパートを通じて加藤さんは一繫がりのことをいっているので、読者の特権として大いに単純化して説明し、そして感想を付け加えてみたい。
加藤さんはこの本の冒頭で、湾岸戦争時の「文学者」の反戦署名声明に触れ、一言でいうなら「誤っている」とした。その声明の作成者のひとりであるぼくが、加藤さんの書いていることをまるで自分が書いているようだと思うのは実に奇妙に思われるかもしれないが、ぼくもまたあの時「誤っている」と思い、「しかし、誤る以外にやりようがないではないか、そんな気がする」と思い、「それにしても誰か、これがどういう具合に誤っているか、ちゃんと指摘してくれないだろうか、ぼくもきちんと考えてみたいから」と思ったのだった。そして、五年がたち加藤さんは、ぼくに「誤り」の中身を教えてくれたのだ。
あの時、ぼくが苛立っていたのは「そんなことは、知らないよ」という「ノン・モラル」の声だった。それは、戦後が生んだ最良の声のはずだった。
「人は、それに関与していない限り、どのような問題にも、オレは関係ない、という権利をもつ」のである。それを自由と、ぼくたちは呼び慣わした。
それに対し、正義を主張する、政治問題を発言する、環境問題で直接行動に訴える、いずれも立場が悪いのである。いやいや、すべからくなにかをするということはなにもしないことに対して立場が悪いのである。なぜなら、なにもしない限り、決して誤ることはなく、なにかをする限り、大なり小なり人は誤ってしまうからである。
いや、それをさらに進めるなら、なにかを書くということはなにも書かぬことより立場が悪くなってしまうのだ。
しかし、加藤さんはいう。
「人はどのような限定の中にいても、無限に触れることができる。どのような限定の中におかれても、オレは関係ない、という権利をもつ。このようなあり方の底にあるものをさして、いま文学と呼べば、わたしが確かめたいのは、その原理とは何か、ということ、つまり、文学とは何か、ということなのである」
湾岸戦争反戦署名、それに連なる憲法問題はやがて「文学とは何か」に行き着く。そして、加藤さんはこのいわば究極の問いに、「さんざん語られ、もう誰からも顧みられなくなった、わたし達の文学史上の石器時代の遺物」「政治と文学」という枠組みを甦らせて答える。それはあまりにも見事な回答なのだが、同時にぼくは、同じ枠組みを使ってもう少し違った答えがあるのではないかと思った。そして、加藤さんからもらった大事な宿題としていつかちゃんとぼくの答えを出したいと思わずにいられなかったのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする