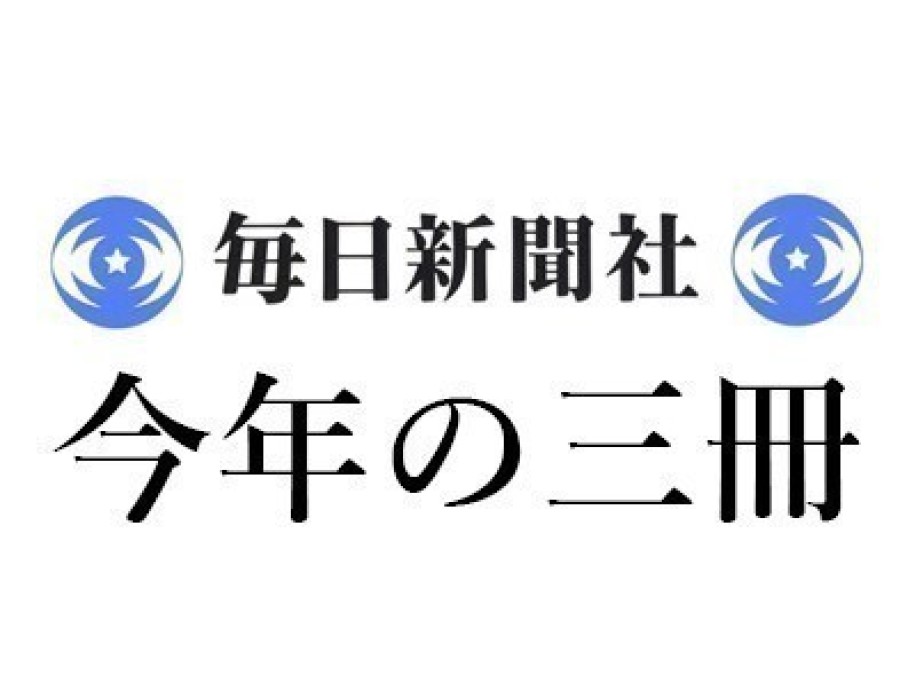書評
『チャンドス卿の手紙/アンドレアス』(光文社)
三十年ぶりの「手紙」
ざっと三十年ばかり昔、ぼくがまだ高校生だった頃、ドイツ文学に強かった同級生の友人(なんとすでにハイデッガーもリルケも原書で読んでいた。トラークルやゲオルゲやヘルダーリンもみんな彼に教えてもらったのである)と話していたら、突然、「あんたなあ、ホフマンスタール読んだことある?」といわれた。
「あらへん」とぼくは答えた(当時、ぼくは関西在住であった)。
「なんで、そんなこと聞くねん」
「高橋のなあ、いうこと聞いとったら、なんや『チャンドス卿の手紙』みたいやからや」
『チャンドス卿の手紙』がぼくの頭脳にインプットされたのはその時がはじめてだった。
もちろん、その『チャンドス卿の手紙』という作品にぼくはたいへん興味を持った。こういう場合、ぼくは、
① 次の日に本屋で探して読む
② 気になるけど、いつまでも読まない
——のどちらかなのだが、『手紙』はなぜか②の方になってしまったのだった。
そして、時が流れた。
以来、何度も繰り返し「高橋さん、『チャンドス卿の手紙』は読んでますよね。えっ? 読んでないんですか? 読むと絶対面白いですよ」といわれた。そして、その度に、読もうと思い、またしても時は流れるのであった。
もちろん、ぼくも知識としては『手紙』が「現代小説の出発点」であり、プルーストもジョイスもカフカも『手紙』以降の作家と呼ばなければならないほど、重要な作品であることは知っている。知ってはいるけど、なんとなく読む機会を逸してしまうということはあるじゃないですか。
二週間ほど前、文庫の近刊予定リスト(ぼくのデビュー作『さようなら、ギャングたち』が講談社文芸文庫というやつに収録されることになったので)を眺めていた家人が、『ギャング』の隣に『チャンドス卿の手紙』を見つけて、ぽつりと呟いたのである。
「一度聞こうと思ってたんだけど、『チャンドス卿の手紙』読んだでしょ?」
「いや」ぼくは答えた。
「へええ。だって、あなたが書いたみたいよ」
家人は大学でドイツ文学を専攻していて卒論がカフカという人なのである。
ぼくは意を決した。
数日前、ぼくは本屋に行き、出たばかりの『ギャング』の横の(一緒に出たばかりの)『チャンドス卿の手紙』(川村二郎訳)を買い、家に帰り読んだ。なんだか、三十年前に別れた恋人からもらいながらそのまま読まずにおいた手紙をはじめて開けるような気分がしたのだった。
『チャンドス卿の手紙』は翻訳にして僅か二十頁ばかりの小品で、日付は千六百三年八月二十二日。若くして傑作をものしたチャンドス卿が二十六歳で文学との絶縁を宣言するに至った理由をフランシス・ベイコンに書き送ったという体裁になっている。
『手紙』にチャンドス卿が書いているのは二つのことである。
その一つは、彼が「書けなくなった直接の理由」。
そして、もう一つは、その「直接の理由」の中に潜んでいる「真の理由」。
そしてそのどちらの「理由」も、ぼくには親しいものであり、ほんとうにまるで自分が書いた手紙かと思えたのだ。いや、『チャンドス卿の手紙』を読んで、そう思わない作家がいるのだろうか?
これが、いるところがおそろしいのだよね。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする