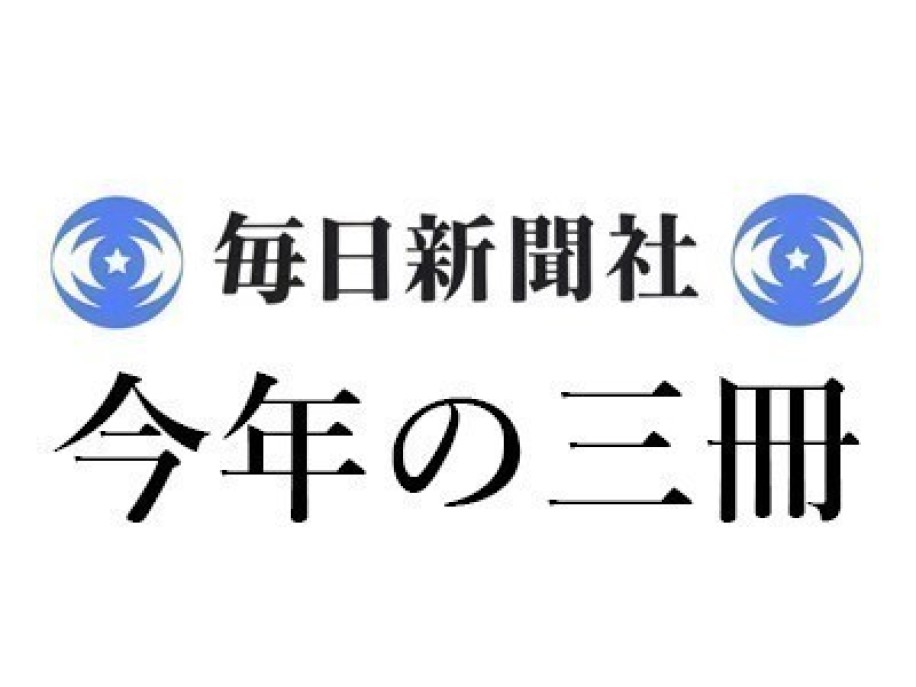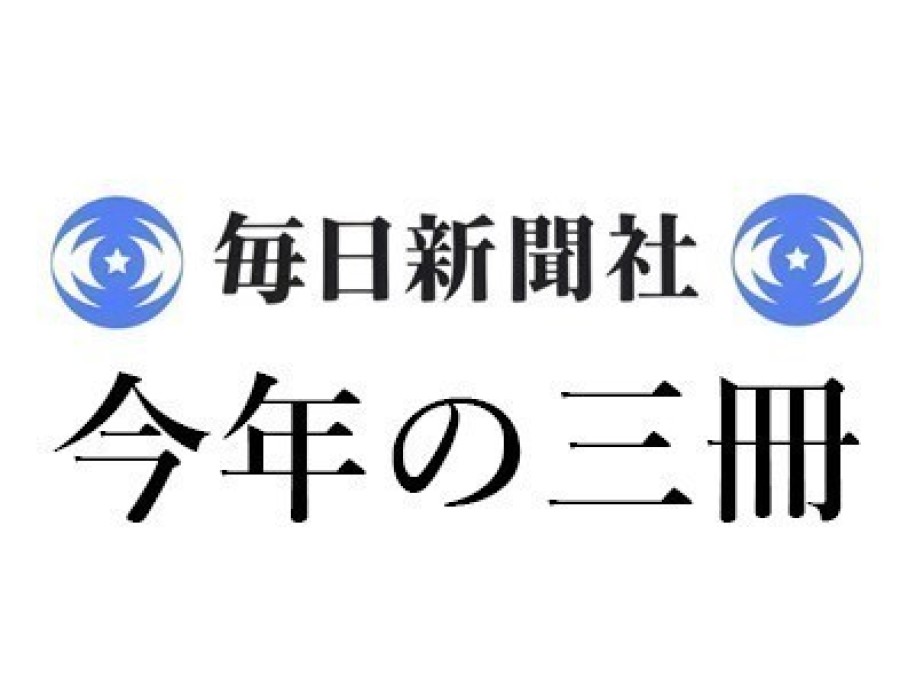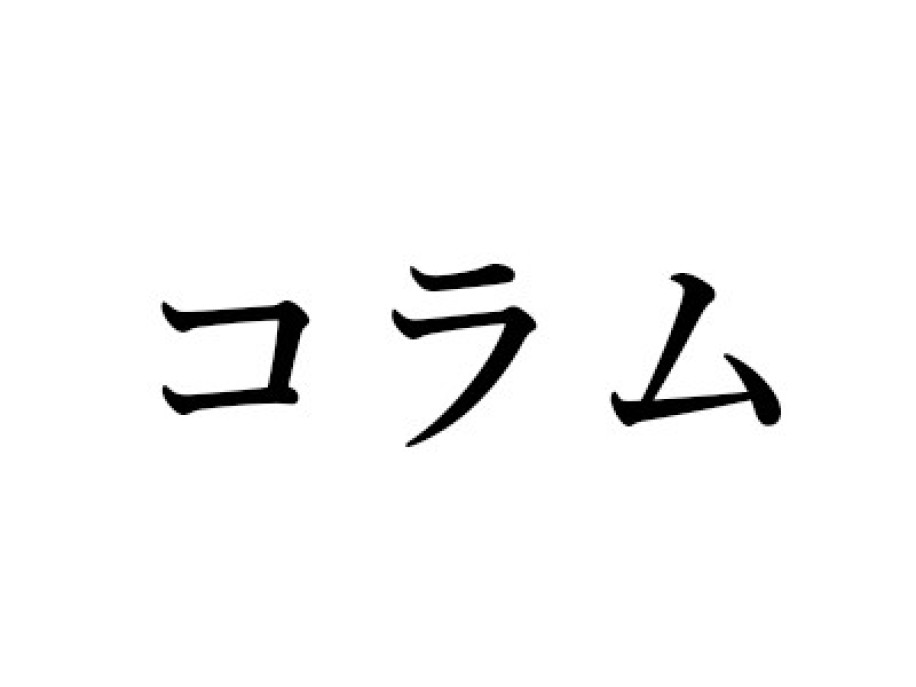書評
『マイケル・ブロードベントの世界ワイン・ヴィンテージ案内』(柴田書店)
いざとなりゃ本ぐらい読むわよ……たぶん
「高橋さん、いったい『退屈な読書』はいつ本になるんです?」この質問を受けるたびに、わたしは「そのうちに」と答えてきたが、とうとう「そのうち」が来てしまった。一九九三年十月十五日号の第一回から一九九六年八月三十日号の第八十一回までをおさめ、今週あたり本屋の店頭に出荷されるはずである。ちなみに、タイトルは『いざとなりゃ本ぐらい読むわよ』。
「なに、それ?」と思われるであろうか。タイトルがそうなった理由については、同書あとがきを読まれたい。
ところで、わたしの本のタイトルは長いものが多い。評論でいえば『文学がこんなにわかっていいかしら』に『文学じゃないかもしれない症候群』、小説でいちばん長いやつが『惑星P-13の秘密――二台の壊れたロボットのための愛と哀しみに満ちた世界文学』。
そりゃ、わたしだってたまには『こころ』とか『おしん』とか『パンセ』のようなキリリと引き締まったタイトルの作品にしてみたい。しかし、考えていくとどうしても長くなってしまう。高校の教科書を作る仕事に従事していた家人がこの前しみじみといった。
「あなたのエッセイもよく候補になるんだけど、最後に落ちちゃうのよね」
「どうして?」
「説明が多すぎるから。自分で質問して、おまけに自分で答えまで出しちゃうでしょ。答えつきじゃ、教科書には載せられないんです」
なるほど。作品のタイトルが長いのも、もしかしたらそのせいなのかもしれない。理解されないかもしれないという恐れが、筆者をしてそのような行動に走らせるのか。精神分析医ならずとも、そう判断したくなるではありませんか。
その家人が『いざとなりゃ本ぐらい読むわよ』のゲラをめくりながら、目次のところを指していった。「これ、目次?」
「はい。一回ごとのタイトルを並べてあるんだけど」
「ふーん、一瞬、詩かと思っちゃった」
昔、藤井貞和さんが伊藤比呂美さんのある本の章のタイトルを、ずらりと書き並べ「これって詩ではありませんか」と書いた。伊藤比呂美もくどいタイトルが多い。かつてわたしはそれを「理解されたい願望」のせいと書いた。いやはや。
読み返してみて、なぜ入っていないのだろうという本も多い。挙げていけばきりがないが、たとえばマイケル・ブロードベントの『ワイン・ヴィンテージ案内』(山本博訳、柴田書店)。
これはタイトルが示す通り、世界のワインの特質と価値(を☆の数で)を地方と年代ごとに簡潔に記述したもの。ボルドーのところを開くと、
1959年☆☆☆☆☆
この年はかつて「世紀の当たり年」と新聞でも報道された。イギリス市場ではとても人気がある。戦後では一番がっしりした体格をもったワインであることは確か。……。
最上の状態だと、男性的で壮大なワインになる。
「酸味に欠ける」という見方もあるが、59年ものの多くは、今でも飲んでみれば素晴らしいし、永遠に飲めそうな感じのする豊潤さをもっている。
ぼくの生まれた年はというと。
1951年おそらく、1930年以来最悪の年のひとつ。
薄く、酸味がきつく、老い衰えている。手を出さない。
こうやって、ボルドーだけで一八九〇年まで続いていく。ここには断固として答えしかない。だが、これもまた批評の究極の形の一つではあるまいか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする