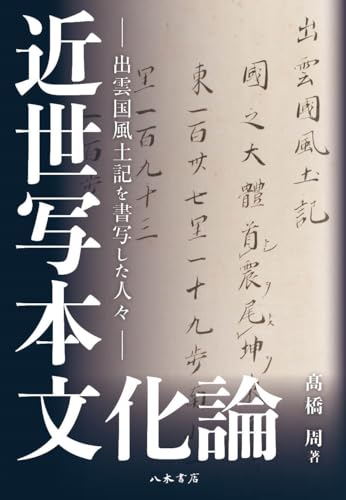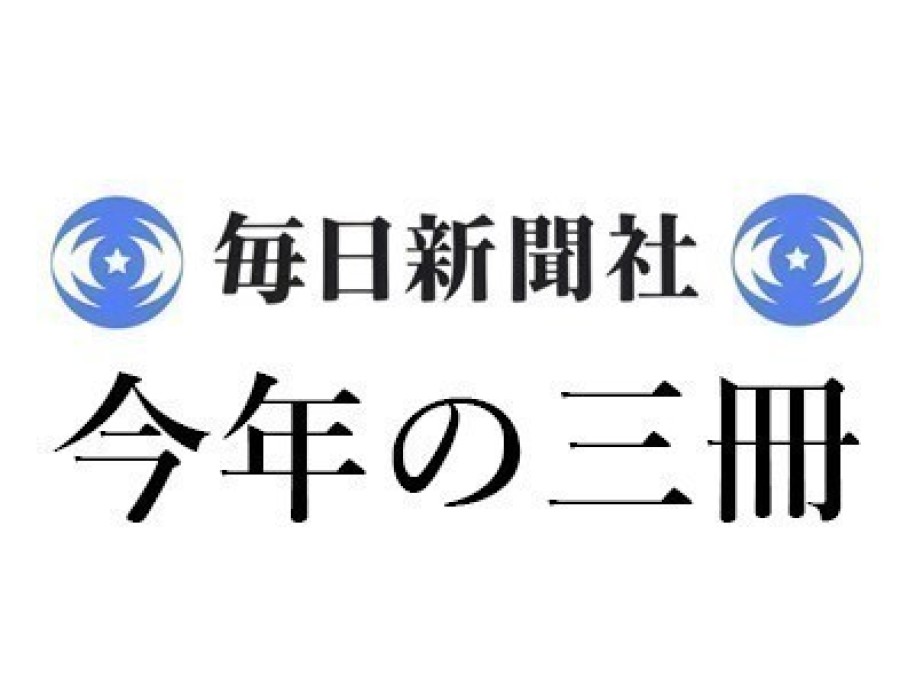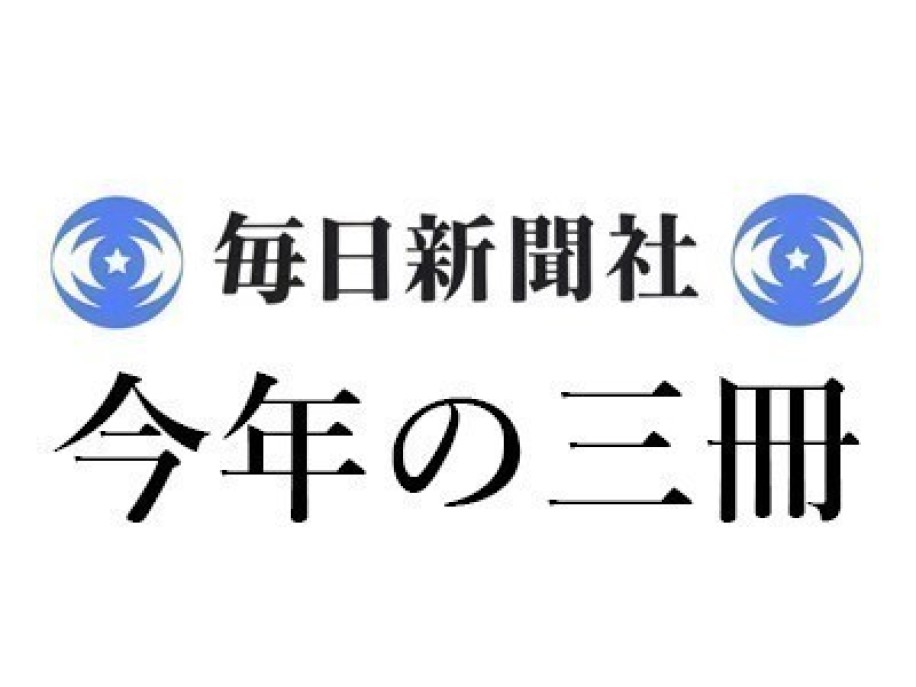書評
『赤目四十八瀧心中未遂』(文藝春秋)
「私」に関するエトセトラ
車谷長吉の『赤目四十八瀧心中未遂』(文藝春秋)を読んですぐ、彼が江藤淳と対談しているのを見つけた。車谷 広告代理店で「この会社に骨を埋めろ」と言われて会社を辞めましたが、私にとっては、「自分の骨をどこに埋めるか」ということが唯一の思想だったんです。
江藤 それで私小説に「骨を埋めよう」と決心されたんですね。
車谷 ええ。だから、私は小説を書く上で、時代の最先端の思想を追いかけることだけはしまいと心がけてきました。むしろ、時代のびりっけつを歩いていこうと考えています。
(「文學界」三月号)
確かに、私小説は日本文学の伝統的なスタイルの一つで、昔はたいへん流行り、そういう作家たちは、自分の身の周りのどうでもいいようなことや深刻なことを小説にしていた。どうして、そんなことになっていたのかというと、私小説作家は「私が書いているのは『私』の真実で、この世に真実のものがあるといって、これぐらい真実のものがあるだろうか。ザ・真実・オブ・ザ・真実、それが私小説なのだ。ドストエフスキーがすごいといったって、あんなもの噓八百じゃないか」と思っていたからだった(実際、このように発言した作家もいたのである)。
しかし、真実としての私小説は廃れた。なぜなら、それは「面白くない」からだった。お前の日常茶飯事なんか読んだって面白くない、と読者が文句をいったからだった。では、どういう小説なら「面白い」のか。その問いに答えるため、たくさんの小説が生まれた。
「私小説」でないすべての小説は、要するにフィクションだった。フィクションではなく、たまには「真実」も読みたいという読者には、ノンフィクションが与えられた。そして、時が過ぎた。フィクションとしての小説もノンフィクションもなんだか面白くなくなった。なぜだろう。テレビやアニメやゲームがフィクションを侵食したからだろうか。CNNの二十四時間ニュースやCBSのドキュメンタリー番組さえ見ていれば、ノンフィクションなど読む必要がないからだろうか。
さて、ここでもう一度「私小説」である。車谷長吉は「時代のびりっけつを歩いていこう」といった。だが、びりっけつと思っていたら、いつの間にか先頭に立っていたなんてこともあるのである。
先日、平野勝之監督の新作「流れ者図鑑」の完成試写を見た。アダルトヴィデオの劇場公開で話題になった「私映画」「わくわく不倫旅行」の続編である。監督自身と女優、この二人だけの長編自転車旅行ムービー、セックスシーンは冒頭だけで、どう考えてもAVではなく単に「映画」としか言えず、そしてその恐ろしいほどの美しさに、ぼくは何度か胸が詰まった。映画が終わり、試写室が明るくなると、十名少しの観客の中で大柄な男性が立ち上がり、平野監督に「素晴らしかった」と声をかけていた。「エヴァンゲリオン」の庵野秀明監督だった。
『赤目四十八瀧』の「私」の述懐は激しく読者を打ち、「流れ者図鑑」の「私」の怒声やモノローグは、観客を恍惚とさせ時に不安に陥れる。それは「私」が真実であるからだろうか。
そうではあるまい。言葉や映像の表現上の革新を経てなお、いやそれ故にかわたしたちは「私」というものが真実とも噓ともいえぬ奇怪な構造物であることを知っていて、「私」こそ、人間のつくり出すもっとも複雑な「作品」なのではないかと思いはじめているのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする