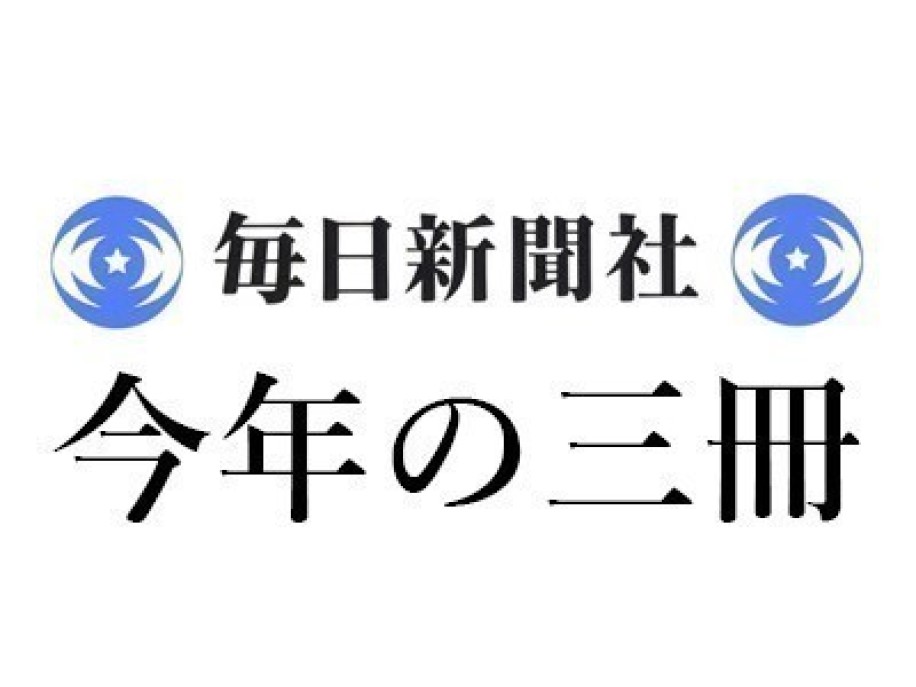書評
『ことわざの知恵』(岩波書店)
ことわざをめぐる意外な話
私たちプロのライターにとって、ことわざや故事成句のたぐいは要注意である。なにしろ含蓄があるし、響きもいいし、ちょっと気がきいている感じもして、ついつい使いたくなる。たとえば「小泉のやり方はまるで臭い物に蓋だ」とか、「小泉は我が身をつねって人の痛さを知るべきである」なんていうふうに。しかし、使うとたちまち文章が陳腐になる。ことわざや故事成句は紋切り型なのであり、だからこそ長く使われてきた。私にとって岩波書店辞典編集部編『ことわざの知恵』は、安易に使っちゃいけない言葉一覧である。
この本で面白いのは、西洋伝来のことわざを集めた章とオリジナルの意味が誤解されて使われているものを集めた章。「目から鱗が落ちる」は『新約聖書』に由来し、しかも蛇の鱗だったとは。「一石二鳥」は十七世紀イギリスのことわざだし、「火中の栗を拾う」はフランスのことわざ。
「情(なさけ)は人の為ならず」の正しい意味は知っていたけど、「君子豹変す」が自己変革を肯定評価する言葉だったとは。
それにしても変な本だ。「はじめに」によると、『岩波ことわざ辞典』を作った際の副産物のような本らしい。「ここではことわざ一つ一つの意味や出典、歴史などに十分にはふれていません。それらについては、是非『岩波ことわざ辞典』を引いてください」とある。なんだかPR誌か内容見本でも買わされたような気分だ。
漢字力向上委員会による『「故事ことわざ」って、こんなに面白い!』(角川oneテーマ21)もことわざや故事成句についての新書だが、こちらは漢字検定準拠の三段階クイズ形式というのがウリ。虫食いを埋めろとか、正しい意味を選べとか、誤りをさがせとかいう問題があり、ページを開くと答えと解説が載っている。なんと最終問題は歴史上の人物の最期の言葉。信長や業平の言葉が出てくる。なんだか「ファイナルアンサー?」と迫るみのもんたの声が聞こえてきそうだ。
ALL REVIEWSをフォローする