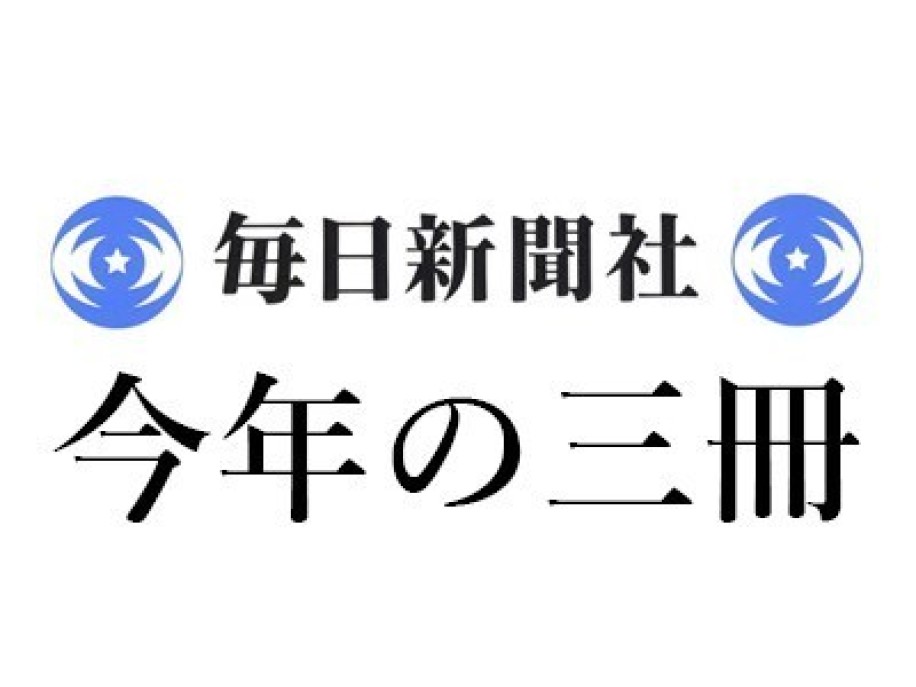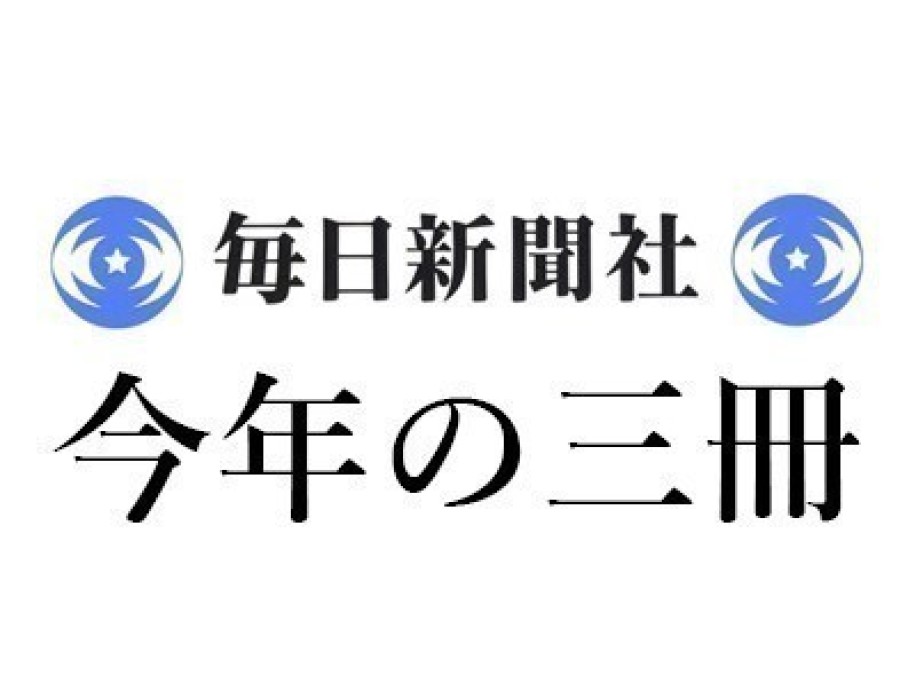書評
『アマポーラスの週末』(集英社)
八十三歳の「新人」
耕治人(こうはると)が亡くなる直前「ブレイク」してからもう十年が過ぎた。生涯きわめて地味な私小説作家だった彼は、最晩年、自身の病と惚けた老妻の世話に呻吟しながら驚くほど美しい小説を何編か書いて病院で死んだ。読者が驚いたのは、人間はそんな絶望的な状態でも小説が書けるのかということだった。しばらくして、幸田文が「ブレイク」した。こちらは死んでからで、書いたまま放っておかれた作品が続けて出版され、耕治人とは違い、老年とはなんと豊かなものであろうと読者を驚かせた。わたしが「老人文学」に興味を持ったのもその頃である。以来、わたしは武田百合子や宇野千代や森茉莉を金子光晴を読み返して「やっぱり、老人にはかなわないねえ」と感心したり、ブコウスキーのように新たに「ブレイク」する老人を見つけては、「読むなら、ただの新人より『古い新人』だ」とひとりごとを呟いたのだった。そういうわけで、ハリエット・ドウアは西洋のおばあさんでデビュー作の『イバーラの石』を書いて全米図書賞「新人」賞をとったのが七十三歳、そして二作目のこの『アマポーラスの休日』(鈴村靖爾訳、集英社)を書いたのが十年後の一九九三年でこの時、彼女は八十三歳になっていた。二作目ならまだ新人というわけだ。彼女の第三作が読めるかどうかはわからない。
舞台は一九六〇年代のメキシコの寒村アマポーラス、そこにふたりのアメリカ人男女がやって来る。男は脱税の追及から逃れ、女は離婚の傷を癒すため、ふたりはそこに土地を買い、分譲し、異邦人たちのコロニーを作り上げようとする……というストーリイである。読者はそのどこを読むべきか。多数の登場人物の中、老齢者の言動や感想を読むべきなのである。
まだ生の味わいを知らぬ子供がいて、むせかえるような青春の真っ只中にいる若者がいて、人生の折り返し点に近づきつつある者、そこを越えて来たばかりの者がいる。けれども、『アマポーラスの週末』で魅力的なのは、死を目前にした老人たちである。
七十五歳の老音楽家はスタインウェイのグランドピアノで一日中「真ん中のドの上のラの音」を叩き、「高齢だけれど、歳のほどはわからず、村では、耳が聞こえず、口もきけず、ほとんど目も見えないと思われていた」老婆は「腰にまわして結わえた綱の先に」ヤギをつなぎやはり一日中「ハコヤナギの木陰に腰をおろしていた」。いったい彼らは何をしているのか。それはまだ若いミゲル司祭にはわからない。わかっているのは、作者の代弁者であるらしい八十歳を超えるアーサラ・ボウルズだけだ。彼らは、それぞれに死の準備をしているのである。
人生の幕切れも間近だというのに、ボウルズ夫人は、自分の頭の中が整然とまとまりがついているとは思えなかった。こんな歳になれば、いろんなことにもっと答えが出ていて、それが正しいかどうかを証明することもできてよさそうなものなのに、と彼女は思う。しかし、自分でも承知しているけれど、八十三歳のいまになっても、もし自分の頭の中を覗いてみることができるならば、芽が出かかったばかりのあれこれの着想やら、夢見るばかりでいっこうに実現しない計画やら、ぜひ取り組んでみようとかつて意気ごんだ回想録やら、頭のなかでまとめてみたもののついぞ表に出したことのない言葉やら、いろんなものが雑然とひしめき合っているのを発見することだろう。
とうに人生の真ん中を越えたわたしはこういう箇所に出会うとホッとすると同時に、なんだかやりきれない気持ちになってしまうのだった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする