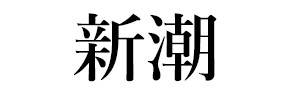書評
『近代文学と音楽の場所 母なるもの』(文藝春秋)
批評家は母の夢を見る
母なるもの、その語りにくさはだれしも感じるところだろう。そもそも肉親を語るのには照れ臭さが伴うが、父親や兄弟姉妹にも増して、母親のことは言葉にしにくい。その照れ臭さをこらえ、センチメンタルになることも辞さずに物語るならば、一気に大衆的な支持を集める作品が生まれる可能性があることは、もろもろのヒット作が証明するところだ。「おふくろさん」とは大衆性そのものなのである。それゆえに、文学的探求にとって、母親は何とも手に余る相手であるのかもしれない。明晰にして詩的な感応力に富む、著者ならではの分析の数々から浮かび上がってくるのは、母をとらえようとしてとらえそこねる文学者たちの姿である。たとえば中原中也の場合。「女」をめぐってはあれだけ自在にイメージを変化させ、「トポス的変換」の妙技を「手裏剣のようにひたひたと」決めてみせた詩人が、こと母となるとこれを「黙秘」し、「忘却」するほかなかった。むしろその「忘却表現によってしか母を超えることができなかった」ゆえんが、鮮やかに解きほぐされている。
あるいは、小林秀雄の場合。『モオツァルト』には「母上の霊に捧ぐ」との献辞が掲げられている。だが、母の死を「苦もなく」音楽に転化することができたモーツァルトと比べ、小林は結局のところ喪の体験を「言語の不完全性と不可能性」として生きるほかなかった。唯一、未完に終わった例のベルクソン論「感想」の冒頭部分に、亡き母がつかのま現われていた。母が死んで数日後、夕暮の道で蛍と出会い、「おつかさんは、今は蛍になつてゐる、と私はふと思つた」というのである。だが、その「童話的経験」を含む文章の単行本化を、小林は生前、ついに許さなかった。ようやく第五次全集別巻に収録されたその文章を、著者は改めて読み直す。そしてそれがまさしく本物の「童話」であり、「そこに登場してくるのはみんな子供なのだ」と見抜くのである。
つまり母について綴ろうとした瞬間、小林秀雄は「少年の日々まで一気に遡って」、「おつかさん」という呼び方がごく自然に口をついて出てしまう。小林は子供にかえった自らの姿を読者の目から遠ざけようとしたとも考えられる。
かくして、「文学言語」の探求者たちにおいては「母は隘路であり、通過が困難な閉鎖である」。それは「ものを言わない闕語(けつご)法」への決断を文学者たちに強いさえする、という事態がいよいよ明らかになっていく。
だが、母の前に沈黙を強いられた、あるいは「闕語法」を自らに課したかつての文学者たちとは対照的に、驚くべき闊達な語り口で自らの母の姿をいきいきと喚起してみせる現代の批評家の存在が、そこに浮かび上がる。高橋英夫その人である。
近年、著者は「逸脱」や「道草食い」、「閑談」や「漫筆」を一つの意識的方式、あるいは意識を遊ばせ自由にする手段として取り入れ、清新な魅力あふれる「文学言語」を開拓してきた。前作『時空蒼茫』に続き、本書はその実践がもたらした新たな成果である。文学テクストの隅々にまで明視を注ぐ読解の営みと並行して、自らの記憶の内で思いがけず息を吹き返す面影をとらえ、はるかな過去の断片を迎え入れる。その二つの営為がおのずから互いに刺激し合い、やわらかくなだらかな言葉の広がりを形作っていく。「隘路」であり「閉鎖」であるはずの母なるものが、回想を経て湧出し、批評の言説を潤す。
そこに溢れ出る、母への慈しみの念は、著者の旺盛な批評活動を支えてきた、対象への愛と結びつく。何しろ音楽への愛情を著者に伝えたのは母であり、母がモーツァルトのピアノ・ソナタ(K331)イ長調の第一楽章を弾くとき、左手と右手がすばやく交差して着地する、その魔術的な動きを「上体を揺さぶりながら喜ん」だのが著者幼少時の大切な思い出なのだった。もはやピアノを弾かなくなってしまってからもなお、母は「音楽はほんとにきれい」と繰り返し語ったという。「ほんとにきれい」な何かがある。そのことを母の演奏と言葉によって心身に刻み込まれた経験は、批評家としての著者の幸福というほかはないだろう。
ロラン・バルトのことがしきりに思い出された。生涯、母と二人で暮らしたバルトは、母に先立たれた衝撃に耐えながら『明るい部屋』を書いた。私の母は善良そのものだった、しかも彼女はその美質をだれから受け継いだのでもない、不幸な環境に育ちながらも善良さに輝いていた、母は私に一度たりと「意見」めいたことを言ったことがない。写真映像の存在論をめぐる精緻な論考のただなかに書きつけられた、そんな言葉の帯びる取り返しのつかない悲しみの色に打たれたものである。結局バルトは母の死から数年で世を去った。
バルトには、ゆっくりと母を回想し、夢見る時間をもつことができなかったのだと、本書を読みながら思わずにはいられない。その時間があったなら、彼が晩年考えていた「ロマネスク」なものへの接近は、はるかに具体的な進展を見せていたのではないか。逆に言えば、「すべてをまぜあわせ、溶しこみながら、『文学言語』という以外何ものとも呼べないような、何の実用の役にもたたないようなものを書き上げてみた」い(『時空蒼茫』)という意志のままに書き継がれている高橋氏の著作の芳醇な味わいは、まさに批評がロマネスクな次元へとゆるやかに、喜ばしく移行していく感触によってもたらされている。批評家が自らの記憶と忘却のはざまでたゆたうことによって開かれる、新しい散文芸術のあり方が示されているといってもいい。
ベートーヴェンのCDに耳を傾けながら、やがて著者は眠気に誘われる。うとうととしだす寸前に、著者は亡き母と会話を交わす。「お母さん」が女学校の卒業演奏のときに苦労したベートーヴェンの曲は、「このごろやっと分かったんだけど、あれはベートーヴェンにとっても卒業制作だったといえそうな曲なんだよ」と最近の発見を語って聞かせる。「あら、そうなの、じゃあきっと苦労したのね」と相槌を打っていた母は途中から何も言わなくなる。「母のおぼろな気配だけになる。気配を残して、沈黙。消失。私は眠りこむ」。
覚醒と睡眠、現実と夢の境界で意識が揺れ動く瞬間にまで筆先が及んだ、感動的な一場面である。批評的ロマネスクの可能性は、この自在な書法によって、これからもさらに窮められていくにちがいない。
ALL REVIEWSをフォローする