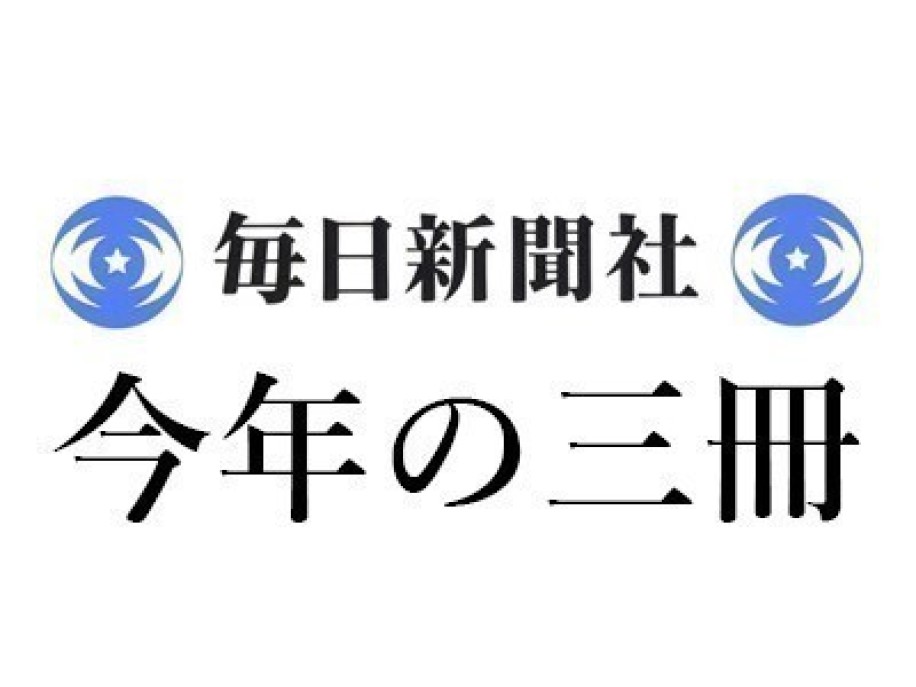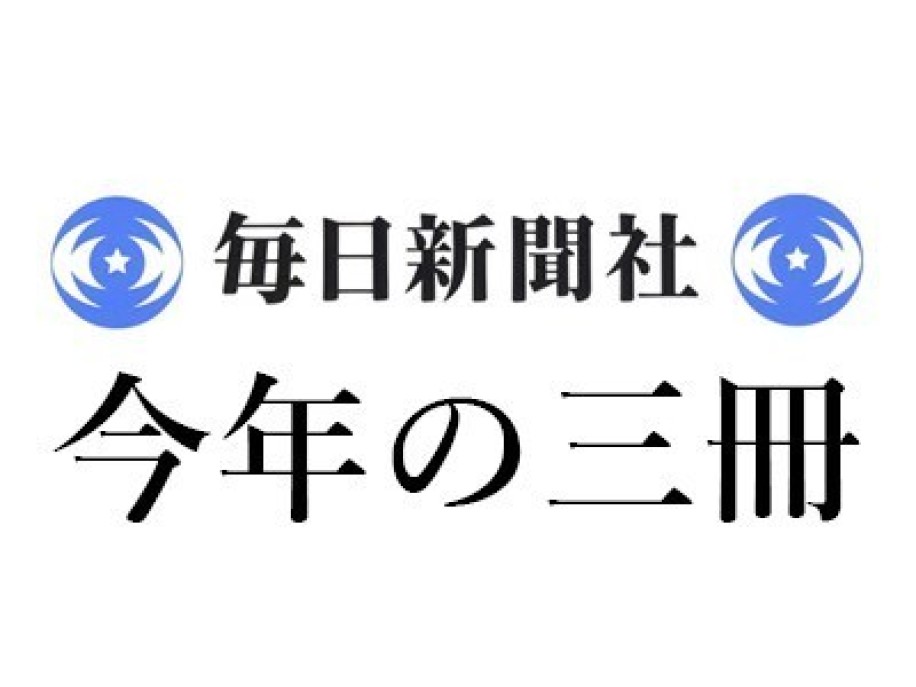書評
『海を渡った日本語―植民地の「国語」の時間』(青土社)
昔「国語」の時間があった
南の島を旅していて、日本ではもう五十年も昔にすたれたような、歌を知っている老人に出くわす。(ああ、日本はこんなところまで占領していたのか)
と思う。戦後世代の人間が、「過去」に行き当たるワンシーンだろう(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆年は1995年)。
『海を渡った日本語』(青土社)の著者、川村湊さんは戦後生まれ。日本の植民地、占領地における文学の研究で知られる。
調べるうちに、植民地へ渡った文学者で、その地での日本語教育に携わったものが、思いのほか多いことに気がついた。
どんな授業が行われていたか。その経験の中で、彼らは何を考え、日本語を、あるいは言葉というものを、どのようにとらえ直したか。
植民地の「国語」の時間を通し、日本人と日本語、人間と言葉を考える本である。南方をはじめ、台湾、朝鮮半島、旧満州、また北海道、旧樺太(サハリン)のアイヌ民族にもふれている。
日本人がごくふつうに読み書きしていた言葉は、海を越えることにより、はじめて「国語」の問題に突き当たる。植民地の人々に、外国語としての「日本語」を教えるのか、それともあくまで「国語」としてか。前者を「言葉派」、後者を「精神派」と著者は名づける。
皇民化教育の立場からすれば、むろん後者でなければならない。が、昨日まで別の言葉を話していた人々にとって、それは外国語以外の何ものでもないという矛盾を、はじめからはらんでいた。
井伏鱒二のシンガポールを舞台にした小説『花の町』が引用される。日本学園の秀才ペン・リヨンが、日本人に答えていう台詞。「私は日本語をよく話せません。はい、私は広東語と福建語と英語とマライ語が話せます」。
リヨンのありかたそのものが、皇民化教育の「言語=文化=民族という三位一体の神話」を、否定するものである。広東語をはじめ四つの言語を使い分けるが、そのたびにいちいち広東人になったり福建人になったりするわけではない。もともと複数の言語世界に生きている。著者いわく、彼らこそは、「一つの言語を習得するたびに、その言語を使用する民族、国家に忠誠を誓い、その民族、国家に成り切るといった言い方が、いかにばかげたものであるかを知っていた」。
三位一体の神話は、しかし、今日も形を変えて生き続けている、と著者。そのあたりは、もうちょっと頁を割いてほしい感はあるが、言わんとするところはわかる。
国際社会における、経済面でのプレゼンスが高まるにつれ、日本語を学ぶ外国人は増えた。彼らに対し、日本文化への無言の、ときには有言の同化を強いてはいないか。軍事力に代わって、経済力を背景とする、同化の圧力。
その危機感ゆえ、戦後半世紀以上過ぎてなお著者は、植民地の「国語」の時間を振り返るのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする