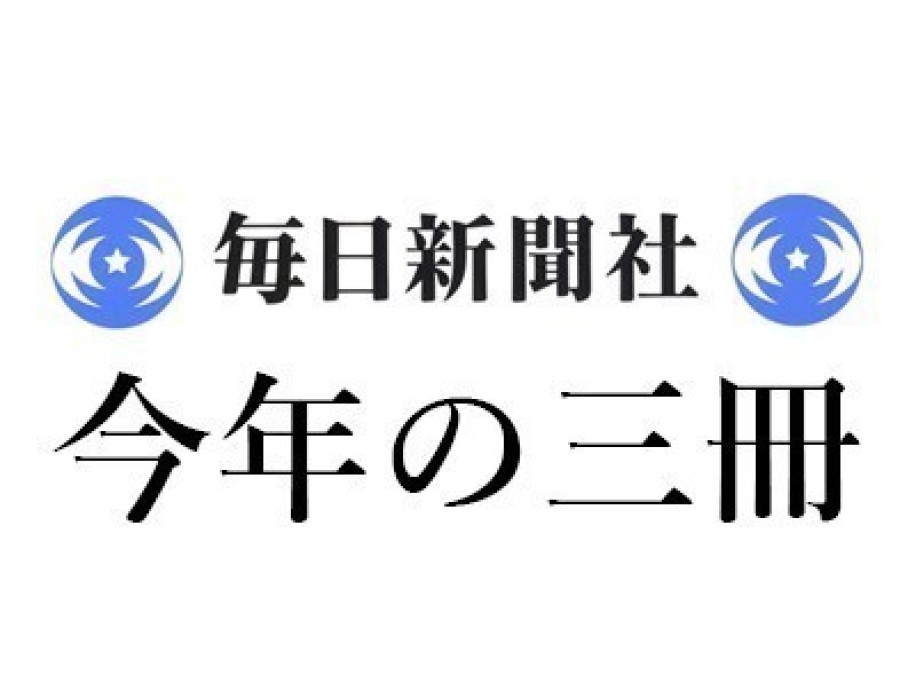書評
『犬大将ビッキ』(中央公論新社)
さまざまな別れ
エッセイのお手本のような書き出しである。「一九九一年の元旦は、どんよりとして、なんだか、めでたくない天気だった」。出久根達郎著『犬大将ビッキ』(中央公論新社)の冒頭だ。すんなり入って、急がず続ける。「七時に目がさめ、ラジオをつけた。童謡を聞きながら、洋服を着、通りに面した窓を大きく開ける」。過不足のない言葉の並び。ああも読める、こうも読めると人を迷わすことがないから、安心して先へ進める。
同時に、一冊の本のはじまりだから、「何だろう」と気をもたせるところもある。折しも、通りをはさんで向かいの家の窓から、老女が現れた。何者であるのかは、しばらくはあかされない。
やがて、著者の母であり、かなりの高齢だと、わかる。おぼつかない足どりで通りを渡り、息子の家に、雑煮を祝いにやって来た。この本の中心人物のひとりの登場だ。
タイトルの「ビッキ」は、著者の本の愛読者には、なじみのある名だろう。著者の家の飼い犬だ。相次いで逝った実母と妻の母とをしのぶ『死にたもう母』(新潮社)に、脇役で出ていた。
このたびの本では、ビッキを主役に、ふたりの母の晩年をふり返る。
そもそも犬を飼うことを思いついたのは、実母のぼけ防止のためだった。日がなコタツの前にいて、衰えていくばかり。犬がいれば、いやでも散歩に連れていくし、話し相手にもなるだろう。
が、ビッキが家に来た日から、その考えはどこかにいって、夫婦の「子ども」とする日々がはじまった。
実際、年寄りが面倒みきれるものではない。育ちざかりの犬を飼うのは、一日じゅう叱りつけていることでもある。栄養のバランスよく食べるようにと、心をくだき、下のしつけに手をやく。
平行して、母の老いも進んでいく。紙オムツをつけるよう、どう説得するかに、夫婦して頭を悩ませ、そうこうするうち、「大」をするにも、息子の手助けが必要となる。介護の現実がひたひたと迫るが、話の軸は、ビッキの日常生活にすえているから、むき出しの深刻さはない。
四人と一匹の間には、いろいろなことが起きる。標札にビッキの名をのせたことが、少しく物議をかもしたり。「ビッキちゃんは、うらやましいね」「いつも主人のそばにいて、構ってもらえるからね」。妙に意気投合する実母と義母。自分たちも子ども夫婦ともっと多くの時間を、ともに過ごしたい。甘えたい。わがままを言いたい。なのに強がる。年寄りのそうした心理の描き方は、さりげなくも、あたたかい。
実母は、入院してほどなく、苦しまずに逝った。義母は「先に休むよ」と床につき、ふたたび瞼を開くことはなかった。
幼かったビッキも病を得、入退院をくり返すようになる。動物と暮らしてつらいのは、彼らの方が年をとるのが早いことだ。一時期は、注射を打つ場所もないほど痩せほそり、最後は家で眠るように息を引きとった。
小さな体でよく吠えた、きかん気で、いばりん坊のビッキ。墓に刻まれた「犬大将」の呼び名が、哀切だ。臨終のさまはそれぞれだが、人も犬も、旅立つときはひとしく、命とひきかえに、送る人の胸に何ものかを残していくことを、深く感じる。
八年余の間に、三つの死に立ち合って、四人と一匹から、二人になった。偶然ともいえる縁で結ばれ、喜怒哀楽を束の間ともにし、別れていく。引きこもりとか少年事件とか、家族をめぐる議論がかまびすしいけれど、こんなしずかで、たんたんとした「家族の物語」もある。
ほんとうは、こういう本を評するのがいちばん難しい。文章がじょうずなのは、誰でも知るところだし、すみずみまで筆がゆき届いているので、そのうえ何をつけ加えても、出過ぎたことになってしまう。
それを承知で書いたのはやはり、多くの人に読んでもらいたかったからである。
【単行本】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする