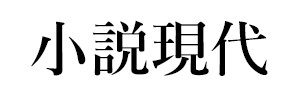書評
『光さす故郷へ―よしちゃんの戦争』(角川書店)
時を超えた対話
「らしくない」本だ。朝比奈あすか著『光さす故郷へ』(マガジンハウス)。著者の大伯母が、満州(現在の中国東北部)からの引揚者と知って、その体験を聞き書きした。いわゆる戦争モノだが、表紙から受ける印象はまったく違う。春の海のような明るい青。白いワンピースに白い帽子をかぶった女性は、子どもの頃遊んだ塗り絵のように、どこかレトロで、「昔のモダン」を思わせる。手にしているのは、赤いケシの花。なぜケシなのかは、読んでわかるが。水色とのコントラストが、目にまぶしい。
カバー絵と内容とのミスマッチ。そして、著者のプロフィールと内容とがまた、ミスマッチなのだ。一九七六年生まれ。新幹線開通、東京オリンピック、大阪万博も知らない。戦争どころか、「復興」さえも遠いできごとだろう、豊かな時代に生まれ育った。その著者がなぜ、この題材を書こうと思ったか。
いくつもの「らしくなさ」にひかれて読んだ。
十九歳のとき著者は、親戚の法事に行った先で、八十近くになるという「可愛いおばあちゃん」、よしと知り合う。いくつで結婚したの、前の旦那さんとはどうして別れちゃったのと、女の子どうしのおしゃべりのように訊ねるうち、時間のねじがぎゅうと逆回りして、何の構えもないままに、著者は「昔」に巻き込まれていく。
女学校の行き帰り、友だちと「ローレライ」を歌いながら歩いた、ハイカラでおしゃれなお嬢さんは、結婚して軍人の妻となり、満州へ渡った。ケシ畑のある裕福な中国人の家に間借りして、一女をなし、幸せな日々を送っていたが、夫のいない夜、突然のソ連軍侵攻。女子どもだけで行くのは危険だ、ここで自分の娘として生きろ、との家主のすすめに首を振り、「故郷へ」、その一念で逃げ延びて、引揚船に乗るも、内地を目前にして、娘は息絶える。
家主の子どもたちにもなつかれて、笑い声に包まれていたおだやかな日々が、一瞬にして、こうも変わってしまうものか。いや、一瞬ではない。この日に至るずいぶんと前から、事態はよしの気づかぬところで、着々と進行していた。戦争の、他国の領土を侵すことの本質を、おおい隠した上に成り立っていた日常。そのひとところが、ソ連軍によって破られたとき、世界はまるで荒々しく布をはぎとられたように、よしにとって、まったく様相を変えたのだ。そのあたりも、本書ではきちんとおさえられている。
今にしてなぜ、この題材を? と思うかも知れない。が、この本ができるには、半世紀の時間と、書き手と語り手との年齢差とが、必要だった。戦争を知らない世代にだからこそ、大伯母は、一から語る気持ちになったのだろう。
私はよしと自分の伯母とを、重ね合わせざるを得ない。彼女が引揚者だと知ったのは、ずっと後になってからだ。
満州については、早くから関心があった。近代文学を読むと、よく出てくるので。いったいどんなところだろうと、桑原甲子雄の写真集『満州昭和十五年』(晶文社)を買った。若い日の写真家が撮った街のスナップを、一九七四年に編んだもの。今は手に入りにくいが、同じ著者、版元の『東京昭和十一年』と並んで、当時のようすを伝える貴重な本として知られる。
中学生の私には、どこか異国の文字としかわからなかった、ロシア語の看板。その前に立つ、白人の女の子。
本の中に引用されている室生犀星の哈爾浜(ハルビン)をうたった詩も、『室生犀星詩集』(岩波文庫)を求めて、くり返し読んだ。
私は満州に、というよりも、その土地に焦がれた人々の思いの方にひかれた。私にとっての「満州」は、人々の心の中にかつてあったと聞く夢の地であり、失われた楽土であり、幻の国だった。すなわち、観念であった。その地で、現実の時間を生きた人間が、近親者にいようとは、考えたこともなかった。
伯母の三井田千枝は、私家版歌集「玉くしげ集」で、その経緯を記している。ほかならぬ昭和十五年に、林政庁長に赴任する夫とともに海を渡った。
燈台はなつかしきかな母の瞳(め)のまたゝくごとく点る紀伊の海
神戸からの船出に際し、詠んだ歌だ。「母の瞳」の語に、よしが、心やさしき中国人のさし延べた手をそっと振りきり、故郷へ帰ろうとした思いがわかる気がする。誰にとっても、自分を育んでくれた地は忘れがたい。
よしにとっての故郷は、生家の小間物屋、向かいのバス停、海沿いの道、、女学校の友だちと連れだって合唱しながら歩いた坂。あの空の青、あの海の青だった。それを装丁の中心に持ってきた、装丁者の南伸坊さんは、すごいと思う。
伯母の千枝は、よしと同じ昭和二十一年九月に博多港にたどり着く。二人の子はかろうじて命はあったものの、下の子は栄養失調のため、長く苦しむことになった。
二人の子を抱え、長春の街をさまよっていたとき、なつかしい調べを耳にした。ショパンのノクターンだ。東京の家でレコードをかけた少女時代。あの幸福な日々は二度と来ないと思いながらも、こんなにやさしい曲をかける人のいる国だ、もしかしたら母国へ返してくれるかも知れないと、ひとすじの光明を得たという。それが現実となったのは、蒋介石のひとことがあったからだと、帰国して後に知った。
シベリアの収容所から戻ってきた夫と、下関市で居を構え、八十三歳まで生きた。その間、日本は経済成長を遂げ、門司との間には、関門トンネルができ、海上大橋がかかった。
橋塔の赤き光りは夜もすがら絶ゆることなし北に南に
朝露に門司の山々消え行きてたゞ大いなる橋ぞかかれる
無蓋列車に乗り込んで、闇の中のレールに運命をゆだねてより、半世紀。平和の世まで永らえた伯母が、暁の空にかかる大橋を見て、どんな感慨を抱いたか、今さらながら思いをいたす。
伯母に関する記述が多くなった。忘れずに書きとめておきたい。そんな気になったのも、大伯母の体験を、若いなりにまっすぐに受け止めた『光さす故郷へ』を読んだからである。
【単行本】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする