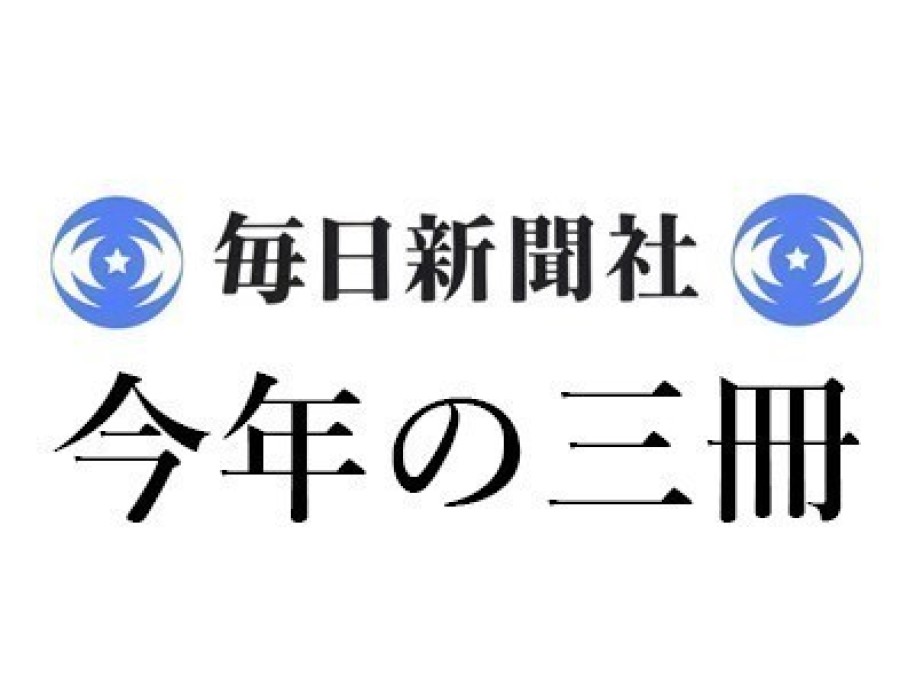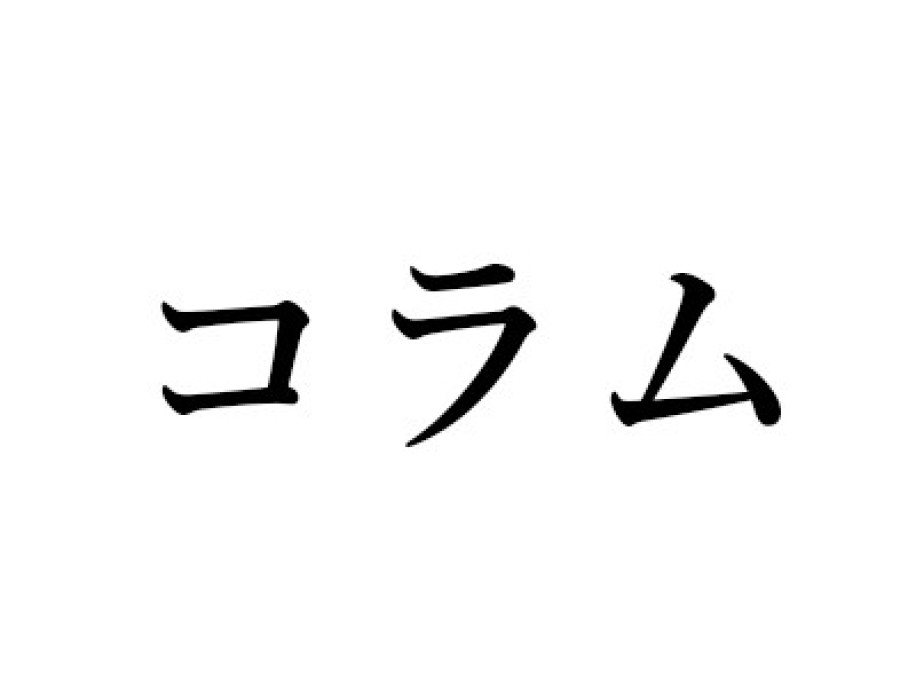書評
『これは「骨董」ではない』(晶文社)
骨董とモノの間
「骨董」ではないという。奇をてらってつけた題ではなさそうだ。収めてある品々からもわかる。友人のひいおばあさんが孫にあてた書、アフリカの「すごい壼」といった、わけのわからないものがある。むろん、李朝の屛風絵、古代メソポタミアの金属器のように、「骨董」好きをうーんと唸らせるだろうものも。『これは「骨董」ではない』(尾久彰三著・晶文社)は、美術品から日用品まで、モノとの縁や、秘められた奥深い来歴を綴るエッセイだ。
自らを「鑑定家ではない」としているが、この人のモノを見る目は、筋金入りだ。民芸運動をしていたおじの影響で、幼い頃から、用の美を究めた器や道具を、当たり前のように使っていた。
高校生になってからは、おじに連れられ骨董屋通い。著者の言う「眼の修業時代」だ。
日本のものにとどまらない。知り合いの仕入れの旅にくっついてテヘランまで行った、なんて話がさらりと出る。
洋の東西、古今を問わず、人間の造形物をたくさん見て、ほんとうに好きなモノだけ集めてきた。その経験を通じて思うのは、古いとか高価だとか珍しいとかといった分別くさいことはどうでもいい。
「ただ人間の手技として、良いものは良い、美しいものは美しいと、素直に見ることの方が大切だ」。
本の中でたびたび引かれる柳宗悦の言葉、「見テ知リソ、ナ知リテ見ソ」が、同じ心を語っている。
好きで買うのだから、真贋(しんがん)とか相場といった問題は、存在しない。損得抜きにモノと関わる。「」付きの「骨董」なる語を拒み、モノという言い方に著者がこだわるゆえんである。
雪の山中の温泉でのエピソードが好きだ。露天風呂につかりながら、白と黒とグレーからなる、深く静かな世界に感動し、「この美しさは、味わっても味わってもとても味わいきれるものではないと思った」。
モノとの出会い、蒐集したくなる気持ちも、同じではなかろうか。ちょっと見たくらいでは、とうてい味わいきれないから、そばに置き、さわって使ってまた眺めてと、いつまでもつき合い続けたいと願う。そうしたモノがひとつふたつと自分のまわりに集まって、「求めている物は何かといったことが、はっきりとわかってくる」。
写真付きのため、本としてはやや高くなったが、付いていてよかった。モノに出会い、いかに興奮したかが、文章にいきいきと書かれている。これで、ブツがひと目も拝めなかったら、かなりつらい。
「骨董」ではないなら、何だ? と考えつつ、展示品を見て歩くつもりで読むと、楽しい。
出口=あとがきに著者の答は示してあるが、たどり着くまでの間に、思いは何通りにも広がっているはずだ。
【この書評が収録されている書籍】
週刊文春 1999年2月25日号
昭和34年(1959年)創刊の総合週刊誌「週刊文春」の紹介サイトです。最新号やバックナンバーから、いくつか記事を掲載していきます。各号の目次や定期購読のご案内も掲載しています。
ALL REVIEWSをフォローする