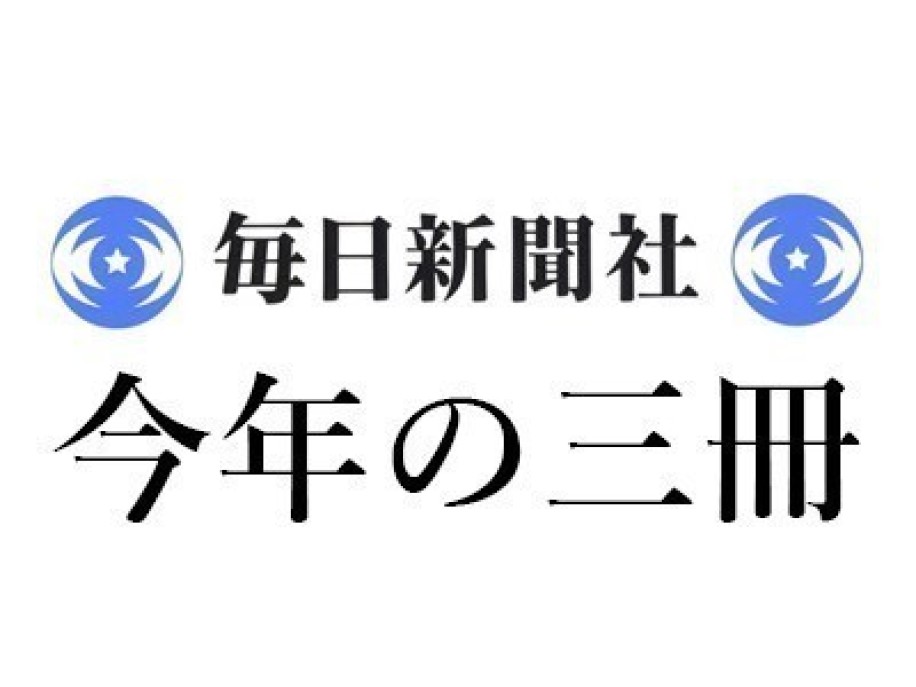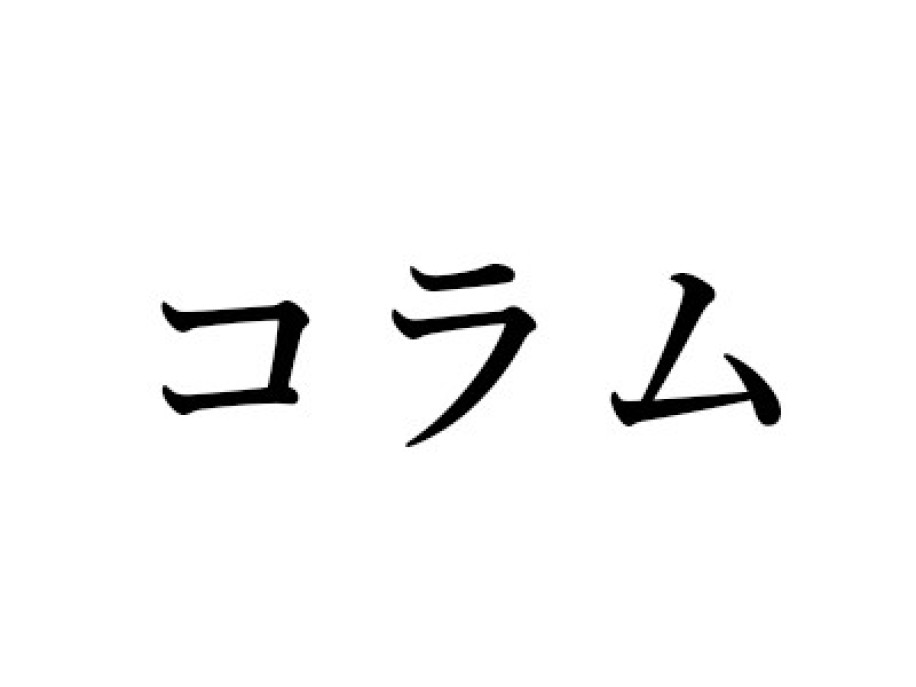書評
『清貧の思想』(文藝春秋)
「清貧」の連想
旅にふさわしいと考えて、この本を持って出た。題名は少々クサい。『清貧の思想』(中野孝次、草思社)、いかにもいま受けそうだ(ALLREVIEWS事務局注:単行本発売は1992年9月)。「清貧」という言葉自体、「貧乏」よりイデオロギッシュである。「ボランティア」や「下町」や「主婦」と同じく、意味に広がりがなく、そのわりに聞くだけで固定したイメージがパァッと広がってしまう。だが政府すら「経済大国から生活大国へ」などといい出し、その大国主義を嗤われると「簡素な生活大国」という珍な標語を考えつく時世である。今日も新聞に「なんでもある日本が貧しく、なんにもないモンゴルが豊かに見えた」という人の言葉があった。まぎれもなく精神の空漠はこの国にはげしい勢いで広がっている。とはいえメザシ食って環境破壊だってできるわけだし、「貧」の押しつけはヤダナと思いながら、まあ考える手がかりにしようと読んだ。
車中で読んでいても連想ばかりが働いてちっとも前へ進まない。
I部では生活を極限にまで簡素化し、心のゆたかさを求めた日本人の先達の生活と言葉を紹介する。
「慳貪にして富貴なること」を嫌った本阿弥光悦の母妙秀。源信『往生要集』の「足(た)ることを知らば貧(ひん)といえども富(ふ)と名づくべし」。鴨長明の『方丈記』「夫(ソレ)、三界(サンガイ)ハ只(タダ)心ヒトツナリ」。良寛の「夜雨草庵の裡(うち)、雙脚(そうきゃく)、等閑(とうかん)に伸ばす」といった心境。それぞれ心にうなずいた。
「現世の栄誉利得とはなれて別乾坤(べつけんこん)塵外(じんがい)境に遊ぶ」といってもそれは人さまざま。鴨長明は執着しぬいた世からはじき出されるように山に入り、『方丈記』の面白さはその人間臭さにある。吉田兼好『徒然草』には死生観をはじめ、おそろしいほどよく目の見える醒めた人物が感じられる、などの著者の指摘には教えられた。同じ「清貧」でもなんと対照的ではないか。
私は「旅派」と「都市隠棲派」がいるように思えた。前者の代表は花のもとにて春死なんの西行、旅人とわが名呼ばれん芭蕉だろう。後者は池大雅、橘曙覧、蕪村かなあ。私など子ども三人を追いまわしながらの文筆稼業、自由な旅もままならぬ身の上、どうしても「都市隠棲派」の後者に親近感が湧く。
池大雅とその妻玉瀾のコンビはいい感じだ。たとえばこんなふう。淀侯(よどこう)の金屏風を描いて得た大枚の謝礼を、大雅は床の上にころがしておいたら、その夜、床の側の壁を切り抜いて入った泥チャンに盗られた。妻はマァといったきり。門人が壁を直したらというと大雅平然。夏で涼しい風が入っていいではないか。夜中オシッコするにも戸を開けなくて良いし……。
こうした恬淡(てんたん)無欲の人格が描く絵は「畢竟一点の俗悪の気なし」清田憺叟(せいたせんそう)と評された。
大雅に一世紀おくれの橘曙覧(あけみ)もなかなか。
たのしみは妻子(めこ)むつまじくうちつどひ
頭ならべて物をくふ時たのしみは珍しき書(ふみ)人にかり
始(はじ)め一ひらひらげたる時
にこにこと無心な歌である。
大雅や曙覧の家は大変に汚なかったそうだ。ここでホッとする。だって清貧というと、長明の方丈も兼好の書斎もこざっぱり片付いている風ではありませんか。最近、『森銑三著作集続編』が欲しくて、よく中公の本にはさまれたしおりを眺めるが、その書見のお姿、整然と片付いた部屋、尊敬しているだけに我身のだらしなさにいじけてしまう。
しかし、池大雅の小屋(しょうおく)は「八、九畳ほどの部屋に紙や屑が散らかり放題散らかっていて、それらをかきわけてでなければ坐れぬほど」だったらしい。まるでわが家のようでうれしい。曙覧ときては貧乏人の子だくさんで、「そこかしこに塵埃が山をなし、障子はやぶれ、畳は切れ、雨も漏りそう。虱(しらみ)も這い出るかと思われる」ほど。ただし万巻の書だけはあった。この印象記は松平春嶽のもので、オ殿サマがそんな茅屋を自ら尋ね、自らの富貴を恥じ、曙覧の高雅さに伏して仕官をすすめたのもエライが、やだよとカンタンに断った曙覧も大したものです。
鳴子の共同湯に身を沈めてうつらうつら考えていると、いくつか検討したい点が湧いた。たとえば日蓮宗に信仰篤い本阿弥家の「天命を恐れる心」と家業の自負の結合は「近代プロテスタントのきびしい倫理観と同質の意識」とあるがそうかしら。そうだとしても、それはウェーバーがいうように「精神のない専門人、心情のない享楽人」として、まさに人間の内面を掘りくずす資本主義的エトスへつながっていくものではなかったか。
また一方、英国の例もひいて「紳士」は人前で金の話はしない、など士大夫(したいふ)の風というか、一度富貴を知ったものの「自覚的簡素」として「清貧」を規定しすぎてはいないか。あるいはインテリや芸術家に偏っているのではないか(もちろん庶民の暮らしにも清貧が生きていた、と著者の母上の例も語られてはいるが)。
もう一冊持って来た池内紀『旅に出たい』に、ラフカディオ・ハーンが焼津の漁民について語っている。「まるで三つ児のように無邪気で、物事があけっぱなしで、柔軟で、すなおで、それが玉に瑕というくらい無類の正直者で」……。これも立派な「清貧」に違いない。
焼津の海から、突然、プルトニウムをのせた「あかつき丸」を思い出した。ブレストはプレヴェールの詩「バルバラ」では小やみなく雨が降っていた。船が向かう先シェルブールでも雨の中で恋人たちがひき離された。感傷的な連想ながら、戦争、核、ゴミ、大気や食糧汚染、こうした現実と切りむすばないでは、いまや「清貧」はつらぬけないのではないか。
中野さんは、もはや鴨長明の時代には戻れないが、池大雅のようには生きられないがと繰り返しているが、あえて戻るしかないのではないだろうか。社会問題に果敢に関わっている著者にその辺を語ってほしかった。第II部は、外国人への講演をふくらましたためもあるのか、「日本人の文化的伝統」という観念にこだわって抽象的すぎるように感じられた。
また最近、読んだ一節を連想する。
生きられる思想というのは、その人のもつ考えかたをいうので、その人のとる考えをいうのではない。考えはとりかえることはできるかもしれないが、考えかたはそう簡単にとりかえることはできない。その人のもつ考えかたは、その人のもつ生きてある習慣にきっと根ざしているからだ(長田弘「神の派遣したスパイ」、『省察』第四号)
もちろん私自身に向かって放たれた言葉である。
【単行本】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

よむ 1991年4月~1993年10月
ALL REVIEWSをフォローする