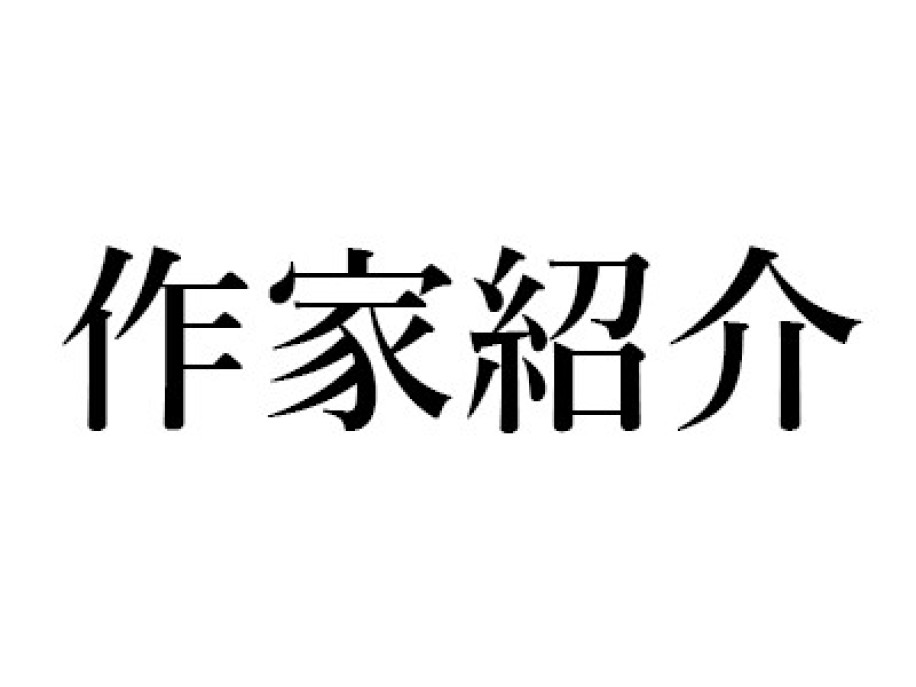書評
『グルーム』(文藝春秋)
美術教師の資格を持ちながら、荒れた学校で生徒からいじめに遭って登校拒否。母親と二人きりで暮らす一軒家で、ごっこ遊びに耽るひきこもり青年の心の闇を描いた、フランス製の傑作ノワール小説がジャン・ヴォートランの『グルーム』だ。
この小説は三つのパートで成り立っている。他者とうまくコミュニケートできないハイムの現実生活を描くパートA。それに対し、彼がなりきっている十二歳の客室係「ぼく」と、ホテルに投宿している奇矯な人物たちとのピカレスクな騒動を綴ったパートB。そして、現実世界でハイムが起こした事件を捜査する女性刑事を軸にしたパートC。パートAとBの関係が説明抜きで提示される上に、現実に存在する人物とハイムが作りだした虚構の人物の区別が判然としないまま物語がスタートするので、はじめのうちは若干読みにくさを感じるかもしれない。が、そうした虚実の境界線をあえてぼかすヴォートランのルールが了解できた途端、この異様な世界の虜になること請け合いだ。
自宅二階をホテルに見立て、ボーイごっこに夢中になっているハイム。彼の妄想が作り上げたパートBの世界は、セックスとバイオレンスの臭いに満ちていながらも、創造主の未熟な精神構造を示すかのように、映画などからの借り物のイメージの継ぎはぎに過ぎない。その滑稽さとグロテスクさがかもす、引きつった笑いが魅力だ。でも、かといってパートAとCに登場する人物たちがまともかといえば、さにあらず。ハイムの妄想の産物たちより、狂っていて暴力的で理不尽なのだ。彼らの虚偽と悪意に満ちた言動に比べると、ハイムのそれのほうが率直に見えてくるほどに。ここに、ヴォートランの世界観が反映されている。つまり「おれはくそまみれだ。おめえはくそまみれだ。みんなくそまみれだ!」ということ。いや、まったくその通り。
【この書評が収録されている書籍】
この小説は三つのパートで成り立っている。他者とうまくコミュニケートできないハイムの現実生活を描くパートA。それに対し、彼がなりきっている十二歳の客室係「ぼく」と、ホテルに投宿している奇矯な人物たちとのピカレスクな騒動を綴ったパートB。そして、現実世界でハイムが起こした事件を捜査する女性刑事を軸にしたパートC。パートAとBの関係が説明抜きで提示される上に、現実に存在する人物とハイムが作りだした虚構の人物の区別が判然としないまま物語がスタートするので、はじめのうちは若干読みにくさを感じるかもしれない。が、そうした虚実の境界線をあえてぼかすヴォートランのルールが了解できた途端、この異様な世界の虜になること請け合いだ。
自宅二階をホテルに見立て、ボーイごっこに夢中になっているハイム。彼の妄想が作り上げたパートBの世界は、セックスとバイオレンスの臭いに満ちていながらも、創造主の未熟な精神構造を示すかのように、映画などからの借り物のイメージの継ぎはぎに過ぎない。その滑稽さとグロテスクさがかもす、引きつった笑いが魅力だ。でも、かといってパートAとCに登場する人物たちがまともかといえば、さにあらず。ハイムの妄想の産物たちより、狂っていて暴力的で理不尽なのだ。彼らの虚偽と悪意に満ちた言動に比べると、ハイムのそれのほうが率直に見えてくるほどに。ここに、ヴォートランの世界観が反映されている。つまり「おれはくそまみれだ。おめえはくそまみれだ。みんなくそまみれだ!」ということ。いや、まったくその通り。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする