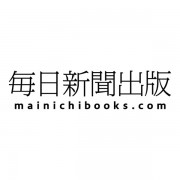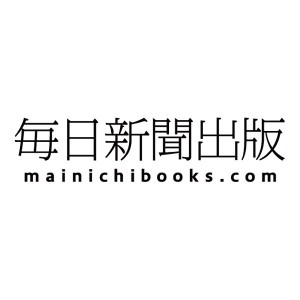前書き
『日本国の正体 「異国の眼」で見た真実の歴史』(毎日新聞出版)
刊行するやいなや、たちまちSNSで話題沸騰の孫崎享著『日本国の正体』(毎日新聞出版刊)。元外務相情報局長を務め、『戦後史の正体』等、数々のベストセラーを世にはなってきた孫崎氏は、日本の「弱点」とは「自分自身が何者かを知らないことだ」と分析しています。
「歴史を通じ、他者の声に耳を傾けなくなった時代には、必ずといっていいほど『重大な戦略ミス』を日本は犯してきた」と訴える孫崎氏は、今なぜ「外国人の眼を通じた日本人論」を世に問うのでしょうか。本書からの抜粋をお届けします。
「えっ、日本はそんな国だったの?」
一見あたり前の事に見えて、これが極めて難しい。
自己について判断し、相手について判断することは、次に私たちがとる行動の前提になる。
私たちにはもともと、「将来に向かってこうしたい」「こうありたい」という願望がある。だが自分の客観的位置、相手の客観的な位置によっては、自分の願望を実現するのが難しくなってしまう。
そのため、自己の願望を実現できるように、自分の客観的位置であるとか、相手の力を歪めて見るような力が働くのが人間である。こうした誤った判断を避けるうえで、極めて有効な手段は、第三者の評価に耳を傾けることである。
この本でしばしば指摘することになるが、日本の特色は「①孤立性」と「②均一性」にある。
「個」を排する力がどの社会よりも強い。多様性を排する力がどの社会よりも強い。
そのため、自分とは違った視点の評価に耳を傾ける機会が少なく、それが「自己」の評価や、「相手」の評価を歪めてしまう、という傾向を日本は内蔵している。
日本はユーラシア大陸の東の端に位置する島国である。この地政学的特徴によって、中国や朝鮮半島において繰り返し発生した政変は、日本に大きな影響を与えなかった。外国からの侵略は元寇のみであり、これも不成功に終わっている。
日本の歴史上、次に列挙するような大きな圧力が外国からかかった時、日本の対応は総じて稚拙であった。
①元寇
②キリスト教の布教と、鎖国へ繋がる動き
③黒船から開国への動き
④富国強兵後の列強との摩擦
⑤第二次大戦敗戦後の占領体制とその後の対米関係
国際関係が一段と緊密化する中で、国家間の折衝は今後ますます増加するだろう。
その際に判断を誤らないためには、「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)ふからず。彼を知らずして己を知れば一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば戦ふ毎に必ず殆(あや)ふし」という知恵が、これまでのどの時代よりも、今後重要になる。
我々は自己を見る時、第三者の眼が自分を客観的に眺める時に極めて有効であることを知っている。
幸い、世界の様々な人が日本を見て、様々な評価をしている。またそれ以上に幸運なことは、極めて知的な人々がこぞって日本を訪れ、日本について語っていることである。知的好奇心の欠如した人が、「極東」までわざわざ足を運ぶことはなかったのだろう。
本書はそうした外国人たちによる「日本論」を集め、筆者が解説と分析を加えたものである。「外国人による日本人観」を多数集めることで、歴史的にみて日本人が苦手としてきた「自国の能力の客観視」に役立てるのが筆者の願いである。また箸休めの番外編として「日本人による外国人観」についても考察している。
日本とは何か、日本人とは何か、という問題については、歴史認識をめぐる論争もあって、近年イデオロギー的な議論に偏っているのではないか、という危惧が筆者にはある。また、引用元を明確にしなかったり、元の資料を改変したりといった、知的手続きの問題が議論をいたずらに複雑化した結果、左右対立ばかりが煽られ、建設的な議論が妨げられているという懸念も強く持っている。
外国人の述べる「日本論」「日本人論」を知ることで、我々自身の自己への認識の客観性、正確性が一段と増すことを筆者は確信している。
[書き手]孫崎享(元外務省情報局長)
「歴史を通じ、他者の声に耳を傾けなくなった時代には、必ずといっていいほど『重大な戦略ミス』を日本は犯してきた」と訴える孫崎氏は、今なぜ「外国人の眼を通じた日本人論」を世に問うのでしょうか。本書からの抜粋をお届けします。
「えっ、日本はそんな国だったの?」
孫崎享・元外務省情報局長が分析する「驚きの正体」とは?
日本の戦略はなぜいつも間違うのか?
孫子に、「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)ふからず。彼を知らずして己を知れば一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば戦ふ毎に必ず殆(あや)ふし」という言葉がある。一見あたり前の事に見えて、これが極めて難しい。
自己について判断し、相手について判断することは、次に私たちがとる行動の前提になる。
私たちにはもともと、「将来に向かってこうしたい」「こうありたい」という願望がある。だが自分の客観的位置、相手の客観的な位置によっては、自分の願望を実現するのが難しくなってしまう。
そのため、自己の願望を実現できるように、自分の客観的位置であるとか、相手の力を歪めて見るような力が働くのが人間である。こうした誤った判断を避けるうえで、極めて有効な手段は、第三者の評価に耳を傾けることである。
この本でしばしば指摘することになるが、日本の特色は「①孤立性」と「②均一性」にある。
「個」を排する力がどの社会よりも強い。多様性を排する力がどの社会よりも強い。
そのため、自分とは違った視点の評価に耳を傾ける機会が少なく、それが「自己」の評価や、「相手」の評価を歪めてしまう、という傾向を日本は内蔵している。
日本の「歴史」と「特異性」から何が分かるのか?
考えて見ると、国際的に見れば、日本は特異な存在である。日本はユーラシア大陸の東の端に位置する島国である。この地政学的特徴によって、中国や朝鮮半島において繰り返し発生した政変は、日本に大きな影響を与えなかった。外国からの侵略は元寇のみであり、これも不成功に終わっている。
日本の歴史上、次に列挙するような大きな圧力が外国からかかった時、日本の対応は総じて稚拙であった。
①元寇
②キリスト教の布教と、鎖国へ繋がる動き
③黒船から開国への動き
④富国強兵後の列強との摩擦
⑤第二次大戦敗戦後の占領体制とその後の対米関係
国際関係が一段と緊密化する中で、国家間の折衝は今後ますます増加するだろう。
その際に判断を誤らないためには、「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)ふからず。彼を知らずして己を知れば一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば戦ふ毎に必ず殆(あや)ふし」という知恵が、これまでのどの時代よりも、今後重要になる。
我々は自己を見る時、第三者の眼が自分を客観的に眺める時に極めて有効であることを知っている。
幸い、世界の様々な人が日本を見て、様々な評価をしている。またそれ以上に幸運なことは、極めて知的な人々がこぞって日本を訪れ、日本について語っていることである。知的好奇心の欠如した人が、「極東」までわざわざ足を運ぶことはなかったのだろう。
本書はそうした外国人たちによる「日本論」を集め、筆者が解説と分析を加えたものである。「外国人による日本人観」を多数集めることで、歴史的にみて日本人が苦手としてきた「自国の能力の客観視」に役立てるのが筆者の願いである。また箸休めの番外編として「日本人による外国人観」についても考察している。
日本とは何か、日本人とは何か、という問題については、歴史認識をめぐる論争もあって、近年イデオロギー的な議論に偏っているのではないか、という危惧が筆者にはある。また、引用元を明確にしなかったり、元の資料を改変したりといった、知的手続きの問題が議論をいたずらに複雑化した結果、左右対立ばかりが煽られ、建設的な議論が妨げられているという懸念も強く持っている。
外国人の述べる「日本論」「日本人論」を知ることで、我々自身の自己への認識の客観性、正確性が一段と増すことを筆者は確信している。
[書き手]孫崎享(元外務省情報局長)
ALL REVIEWSをフォローする