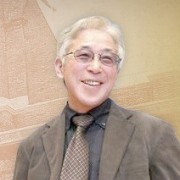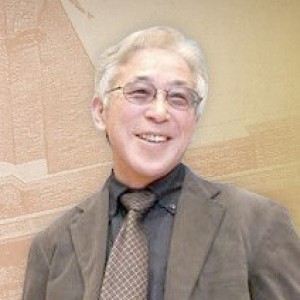書評
『人口で語る世界史』(文藝春秋)
少子高齢化時代を読む手がかり
この数年来、評者は現代日本の最大の問題は「少子化」だと思っていた。年金や労働力はもちろん、安全保障の問題にもかかわるからだ。本書を読んで、私の素朴な印象も的外れではなかったと意を強くしている。原題を『人間の潮流』という本書は、副題には「いかにして人口が現代世界を形成したか」とある。18世紀には世界の人口は10億人に満たなかったのに、今や70億を超える勢いにある。いったいこの200年間に何がおこったのだろうか、とは誰もが問いたくなる。だが、意外にも、個々の地域や国ごとにはともかく、この問題に地球規模で取り組んだ研究者は少ないという。
農業生産は少しずつしか増えないのに、人口は急速に増加するために、食料生産は追いつかなくなる。名高いマルサスの『人口論』の鉄則と思しき主張だが、彼は工業生産の繁栄地から離れた田舎に住んでいたせいで、自分の理論が破綻していくことに気づかなかったらしい。
飢饉、疫病、戦争などがあり、やがて平穏な時期が訪れる。そのなかで人口が下がったり上がったりする。歴史のなかでありふれた出来事だった。ところが、19世紀の英国(ブリテン)で前例のないことがおこる。イングランドから始まった人口の増大が長期にわたってつづき、それには工業化と都市化がともなっていたのだ。人口増加率は加速し、新大陸への大規模な海外移住があったが、50年間で倍増し、次の50年間でもさらに倍増した。
まず、劣悪な環境にあった都市部でも、やがて乳児死亡率が低下する。下水道が敷設され、コレラの流行も深刻にならなかった。蒸気船が航海し、鉄道が地域をつなぎ、道路も整備される。輸送技術の進歩で食物の調達が容易になり、人々は健康になり、公衆衛生もよくなった。このために死亡率が大幅に下がり、人口全体がますます急増する。
このイングランドの人口転換のパターンが、世界各地で追随され、くりかえされる。それが19世紀以降の世界史なのだ。その先陣を切った英国(ブリテン)は「世界の工場」となり帝国主義へ突き進むが、その武器はなによりも人口だった。海外移住が盛んだったために、北アメリカやオーストラリアなどにも“アングロ・サクソン”の覇権が生まれた。
この趨勢に黙っていなかったのが、ドイツとロシアだった。ゲルマン民族とスラブ民族の猛追が始まり、それが第一次大戦の背景にあるという。経済学者ケインズにはそれが見えていたらしく、「歴史上の大きな事件は、人口増加とその他の根本的な経済的原因が、時間がたつにつれて変化することで起こる」と語っている。
日本も例外ではなく、20世紀初めまでは3000万人前後だった人口が急増し始め、1920年代半ばには倍増した感がある。この人口規模と工業化の進展が植民地拡張を正当化する動機になった。戦後も人口増大はつづき、高度経済成長の大きな支えとなる。中国もまた終戦直後の数年間で1億人以上も人口が増え、52年には6億人になり、81年には10億を超えてしまった。教育が普及し避妊法が入手できると、女性の賢明な選択で出生率は低下する。その点で中国の「一人っ子政策」はそもそも誤りだったという。その後、インド、ラテン・アメリカ、北アフリカも人口転換の道を進み、今やサハラ以南のアフリカがその舞台となりつつある。
このようなグローバルな人口動態を見すえつつ、少子高齢化の先頭を走るわが国の将来を考える。本書はその手がかりにあふれており、速読を許さない迫力がある。
ALL REVIEWSをフォローする