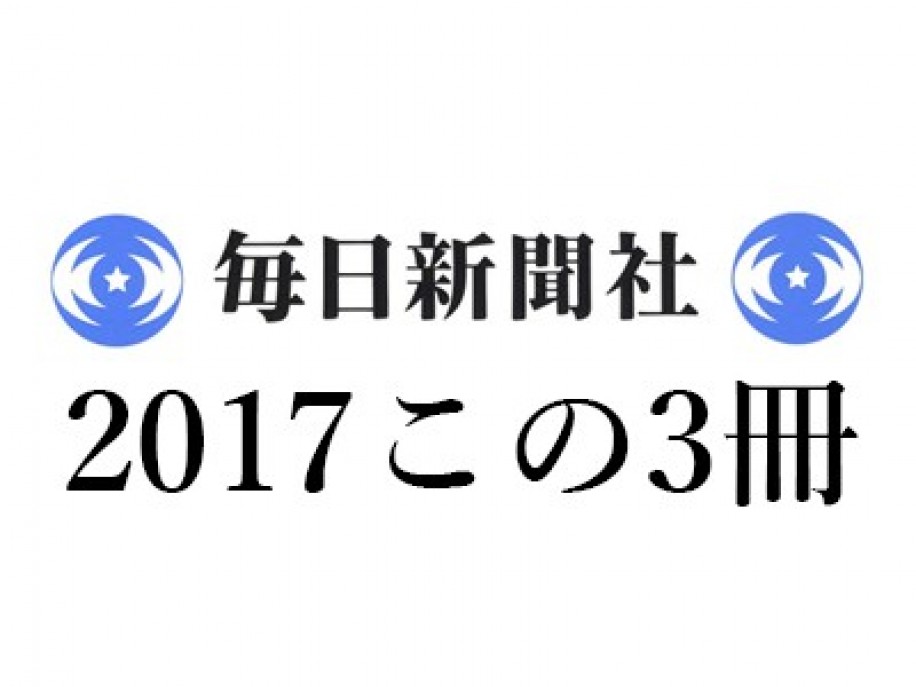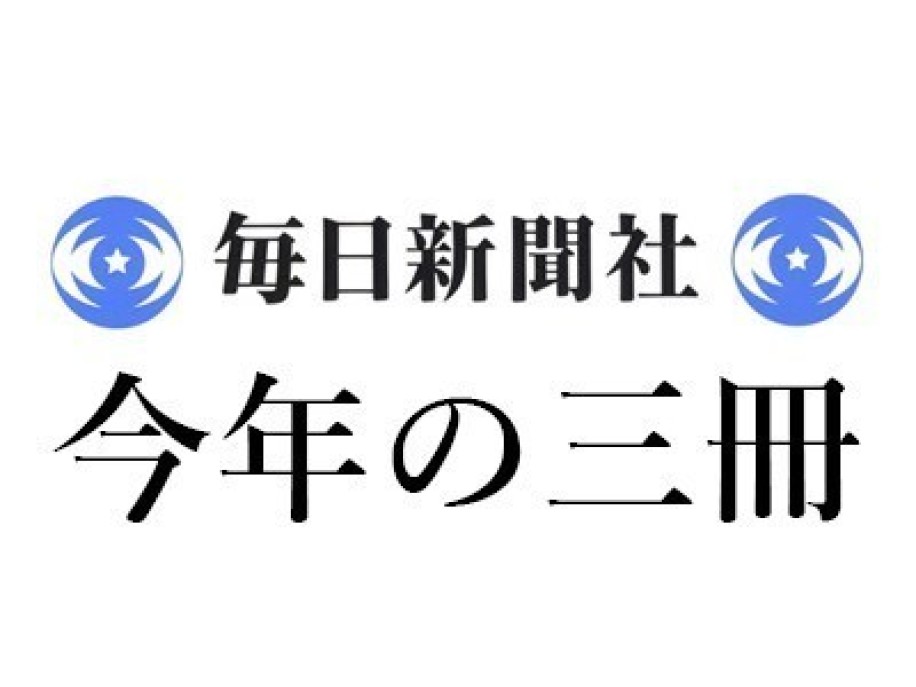書評
『原子力時代における哲学』(晶文社)
ハイデガーの論考を読み解く
福島第一原発のメルトダウン。それ見たことか、と脱原発の声が高まった。だが、著者は危惧する。かつては誰もが原子力平和利用に賛成した。いま脱原発を合唱するのも同じで、大勢に流された思考停止ではないのか。原発がダメな論拠を固めるのもよい。だがそれは政治的主張。原発とどう向き合うか、哲学ならではの役目があるはずだ。そう考え國分氏は、ドイツの哲学者ハイデガーに注目する。一九五○年代に早くも、原爆でなく原子力そのものが問題だとのべたのは彼だけだった。なぜその着眼が可能だったのか。
それを検証するために読むのは、彼のテキスト『放下』である。原子力をめぐる論考に、敗戦前に書いた対話篇が付けてある。難解である。ハイデガーは言う、≪我々は…原子力を、いったいいかなる仕方で制御…できるのか、…この途方もないエネルギーが…突如…檻(おり)を破って…「出奔」し、一切を壊滅に陥れるという危険から人類を守ることができるのか?≫、商業原発の誕生の当初に原発事故を予言している。さすがである。
科学技術バンザイではない。自然に帰れの反動でもない。ハイデガーは技術の価値を認めつつも懐疑的だ。≪現代人は思惟から逃走の最中にある≫。核技術の場合もまたしかり。自然はエネルギーを供給するガソリンスタンドみたいになっていないか。≪不気味なことは、人間がこのような世界の変動に対して少しも用意を整えていないということ≫だと言う。「科学は考えない」はハイデガーの有名な言葉だ。
大筋はこうなのだが、ハイデガーの真意は読み取りにくい。國分氏はテキストのあちこちで立ち止まり、わからないと溜め息をつく。正直なのだ。とりあえず、イオニア学派のヘラクレイトスを補助線にする。対話篇のタイトルは「アンキバシエー」。ヘラクレイトスのこの言葉は、放下(ゲラッセンハイト、英語ならレット・イット・ビーか?)と関連がある。
國分氏のもうひとつの補助線は、精神分析だ。人類は太陽の恵みで生きてきた。原子力はその自然生態系と無関係。経済システムが環境から自立して完結するかも。おそらく幼児期の全能感を想起させるせいで、多幸感をふりまく。それが無意識の執着となって原子力政策が駆動されているのかも。ならば脱原発は、論拠を固めて反論するだけではだめで、無意識にとどめを刺さねばならない。本書はそのための、勇気ある哲学者による先駆的な試みである。
本書は六年前の講演がもとだという。刊行まで時間をかけたのは、ハイデガーが技術をどう論じているか、じっくり見極めたからだ。國分氏は、ギリシャ語の中動態に注目する。能動態でも受動態でもなく、主客のいずれともつかぬ出来事の到来を表せる。プラトン以降の西欧哲学は主客図式を発展させ、世界をその図式に押し込めた。ハイデガーはその主客図式に不審を抱いた。技術は主体が、意のままに行使するものではない。むしろ出来事の到来につれて立ち上がるものではないか。対話もまた主体の意志によらずに進行する。『放下』に対話篇が付してあるのは、この気づきを促しているからではないか。――これが著者の読みである。
主客図式を相対化するのに、ラカン派やポストモダンのように無意識を持ち出すと、議論が神秘主義的になる。中動態に注目するなら、もっと明確に議論ができる。本書は、近代の主客図式を越えて進もうとする國分氏の思索の、中間報告であるとも読める。今後の展開から目が離せない著述家のひとりだ。
ALL REVIEWSをフォローする