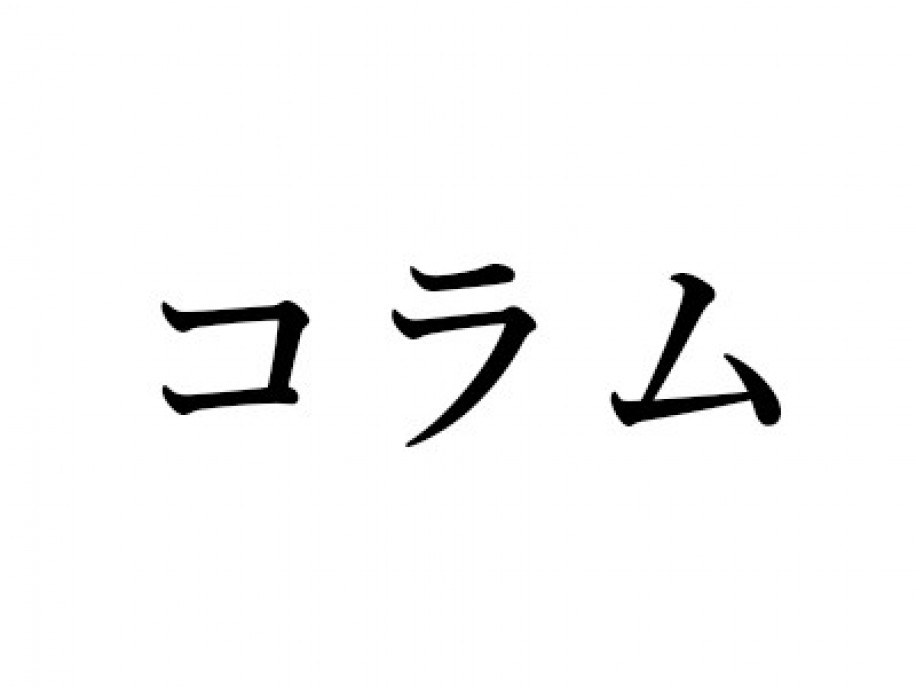書評
『草枕』(新潮社)
昨年あたりからむしょうに明治・大正のカビくさい本を読みたくなって来た。きっかけの一つは、正岡子規の日記『仰臥漫録』をたまたま読んで、その奇怪なキャラクターにびっくり仰天したことだ。びっくりしたと同時に、非常な親しみを感じた。教科書の文学年表の中に静かに、そしていくぶん偉そうにおさまって見えた人が、突然目の前に躍り出て来て、とうとうとしゃべり出したような感じ。そして、私はそのおしゃべりに圧倒されながら、こう思ったのだ――「今の人よりよっぽどヘンで、凄くて、面白いや」って。カビくさくなんて、全然ない。
そうだ、もう一つ。幸田露伴の短編小説『太郎坊』を昨年初めて読んだときにも唸った。私は、近ごろの(厳密に言うと三島由紀夫が死んでからの)、いわゆる純文学にはほとんど興味がなく、「文学的」という言葉をもっぱらケナシ言葉として使うようになっていたのだが、これを読んだとき、「文学とはこういうものだ。作家とはこんなぐあいに特殊な美しい才能を持っているものだ」とあらためて教えてもらったように思ったのだ。
高校時代に、ちょっと教養主義的な気持で文学史上の「名作」を少しは読んだが、今読み直したらどんなふうに感じるだろうか。子規や露伴のように初めて読んで、突然教科書の文学年表から生き生きと躍り出して来るように感じる人は、もっとたくさんいるのだろうか……。
というわけで、いつしか私は「思いっきり私らしく歪曲された日本文学史を作ってみたい」という野望を抱くようになったのだった。
そういうわけで、今回は無謀にも夏目漱石『草枕』――。
「山路を登りながら、こう考えた。/智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」――というのが『草枕』のあまりにも有名な書き出しで、高校時代に初めて読んだときは「うまいことを言う。さすが」と大いに感心したのだが……大人になった今読み返してみると、冒頭のこれに似た対句的なレトリックがたびたび使われていて、それがうますぎるというか、コブシが回りすぎるというか。しかし、たぶんそれ故にこそ「智に働けば……」という一節は広く長く人々に親しまれることになったのだろう(私の長年の持論だが「大衆ヒット商品はクサミがポイント」なのである)。
しかし、高校生の私の頭に、もっと深く刻み込まれたのは「非人情」の美学だった。「苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。余も三十年の間それをし通して、飽々(あきあき)した。飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ」というくだりに何か面白く意表をつかれた感じがした。
そのあと漱石は英文学から漢詩、絵画、演劇、書などにかんする大教養を駆使して、繰り返し、「非人情の天地」を論じている。執拗と言ってもいいくらいだ。よっぽど当時は理解されがたい美意識だったのだろう。
「非人情」とあんまり関係ないかもしれないが、大学時代のある時期、私は、登場人物の名前がフルネームで出て来る小説が読めなくて、記号的な名前が出て来る倉橋由美子や安部公房ばかり読んでいた。作家が電話帳からピックアップして来たような名前の人物が出て来る小説――ようするに普通の小説だと、何か頭の悪い人の身の上相談を聞かされそうでうっとうしかった。今でも、多分にその傾向がある。時どき自分を小説嫌いと思うほどだ。そう言えば、倉橋由美子の小説からは「ニル・アドミラル」という言葉を仕入れたが、ようするにこれって「非人情」ということよね。
映画でもそうなのだが、どうも私は、この俗世にべったり張りついた視点から描かれるところの「人情の機微ドラマ」というのが苦手のようだ。それこそ漱石の言う通り、現実の中であきあきした上に映画や小説で同じ刺激を繰り返すのはげんなり、なのである。私と国民作家漱石の意見は一致した。なのに、私のような読書傾向の人間がなぜ少数派なのか。理解に苦しむ。
『草枕』では俗界とか俗累とか「俗」関係の言葉がよく出て来る。「非人情の境地」とは、一つには、俗世間を超越した東洋的仙人の境地なのだろう。こういう境地をすんなり信じきって陶酔できれば、そこそこお洒落な温泉エッセーが出来あがるわけだが、漱石はそれほど素直な人ではない。仙人的境地はたびたび周囲の人々によって、それから執拗な自意識によってかき乱される(しかし、なかでも俗人の江戸っ子床屋が一番生き生きしていて魅力的なのは、なぜだろう)。漱石は「余裕派」とか「高踏派」とか呼ばれたらしいが、私には『草枕』は「仙と俗・必死の攻防戦」のように感じられる。
不思議なことに、私の場合、こういう仙人的境地への憧れは高校時代のほうが強かった。中年になった今は、逆に「いっそ毒々しい婆(ばば)あに……」なあんて思っている。「俗」を「ポップ」と言いくるめて愛し続けることに決めたからで、それは漱石に対する私の裏返しの敬意と思っているのだけれど……。
【この書評が収録されている書籍】
そうだ、もう一つ。幸田露伴の短編小説『太郎坊』を昨年初めて読んだときにも唸った。私は、近ごろの(厳密に言うと三島由紀夫が死んでからの)、いわゆる純文学にはほとんど興味がなく、「文学的」という言葉をもっぱらケナシ言葉として使うようになっていたのだが、これを読んだとき、「文学とはこういうものだ。作家とはこんなぐあいに特殊な美しい才能を持っているものだ」とあらためて教えてもらったように思ったのだ。
高校時代に、ちょっと教養主義的な気持で文学史上の「名作」を少しは読んだが、今読み直したらどんなふうに感じるだろうか。子規や露伴のように初めて読んで、突然教科書の文学年表から生き生きと躍り出して来るように感じる人は、もっとたくさんいるのだろうか……。
というわけで、いつしか私は「思いっきり私らしく歪曲された日本文学史を作ってみたい」という野望を抱くようになったのだった。
そういうわけで、今回は無謀にも夏目漱石『草枕』――。
「山路を登りながら、こう考えた。/智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」――というのが『草枕』のあまりにも有名な書き出しで、高校時代に初めて読んだときは「うまいことを言う。さすが」と大いに感心したのだが……大人になった今読み返してみると、冒頭のこれに似た対句的なレトリックがたびたび使われていて、それがうますぎるというか、コブシが回りすぎるというか。しかし、たぶんそれ故にこそ「智に働けば……」という一節は広く長く人々に親しまれることになったのだろう(私の長年の持論だが「大衆ヒット商品はクサミがポイント」なのである)。
しかし、高校生の私の頭に、もっと深く刻み込まれたのは「非人情」の美学だった。「苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。余も三十年の間それをし通して、飽々(あきあき)した。飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ」というくだりに何か面白く意表をつかれた感じがした。
そのあと漱石は英文学から漢詩、絵画、演劇、書などにかんする大教養を駆使して、繰り返し、「非人情の天地」を論じている。執拗と言ってもいいくらいだ。よっぽど当時は理解されがたい美意識だったのだろう。
「非人情」とあんまり関係ないかもしれないが、大学時代のある時期、私は、登場人物の名前がフルネームで出て来る小説が読めなくて、記号的な名前が出て来る倉橋由美子や安部公房ばかり読んでいた。作家が電話帳からピックアップして来たような名前の人物が出て来る小説――ようするに普通の小説だと、何か頭の悪い人の身の上相談を聞かされそうでうっとうしかった。今でも、多分にその傾向がある。時どき自分を小説嫌いと思うほどだ。そう言えば、倉橋由美子の小説からは「ニル・アドミラル」という言葉を仕入れたが、ようするにこれって「非人情」ということよね。
映画でもそうなのだが、どうも私は、この俗世にべったり張りついた視点から描かれるところの「人情の機微ドラマ」というのが苦手のようだ。それこそ漱石の言う通り、現実の中であきあきした上に映画や小説で同じ刺激を繰り返すのはげんなり、なのである。私と国民作家漱石の意見は一致した。なのに、私のような読書傾向の人間がなぜ少数派なのか。理解に苦しむ。
『草枕』では俗界とか俗累とか「俗」関係の言葉がよく出て来る。「非人情の境地」とは、一つには、俗世間を超越した東洋的仙人の境地なのだろう。こういう境地をすんなり信じきって陶酔できれば、そこそこお洒落な温泉エッセーが出来あがるわけだが、漱石はそれほど素直な人ではない。仙人的境地はたびたび周囲の人々によって、それから執拗な自意識によってかき乱される(しかし、なかでも俗人の江戸っ子床屋が一番生き生きしていて魅力的なのは、なぜだろう)。漱石は「余裕派」とか「高踏派」とか呼ばれたらしいが、私には『草枕』は「仙と俗・必死の攻防戦」のように感じられる。
不思議なことに、私の場合、こういう仙人的境地への憧れは高校時代のほうが強かった。中年になった今は、逆に「いっそ毒々しい婆(ばば)あに……」なあんて思っている。「俗」を「ポップ」と言いくるめて愛し続けることに決めたからで、それは漱石に対する私の裏返しの敬意と思っているのだけれど……。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
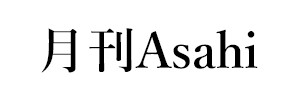
月刊Asahi(終刊) 1993年4月号
ALL REVIEWSをフォローする