書評
『華族女学校教師の見た 明治日本の内側』(中央公論社)
アリスの見た明治社会
明治の日本を見た外国人女性の見聞録として、イザベラ・バード『日本奥地紀行』やクララ・ホイットニー『クララの日記』がある。そして新たな本が加わった。『華族女学校教師の見た明治日本の内側』(中央公論社)、題は長いが原文では「インテリア・ジャパン」である。著者アリス・べーコンは山川捨松のホームステイ先の娘である。捨松はあまり知られていないが、津田梅子らと共に、明治四年に日本初の女子留学生として渡米し、ヴァッサー女子大学に学んだ。会津藩の家老の娘で薩州人大山巌と結婚した。この人については本書の訳者久野明子氏に『鹿鳴館の貴婦人大山捨松』(中央公論社)がある。捨松は家庭に入ったため、津田梅子のように有名にならなかったが、すぐれた人であった。﨟(ろう)たけて美しく、最後まで英字新聞を読み、慈善事業にかかわり、親友津田梅子が創始した津田塾も陰で支援した。
アリスは明治二十一年、津田梅子の推薦で、おそらくはお雇い外国人の女性第一号として招かれ、華族女学校の英語教師として赴任する。捨松と梅子は友人が来日するというので、紀尾井町に洋館のついた貸家を探し、横浜まで迎えに出向いた。そのうち梅子はアリスと同居するようになる。
アリスは日本でのカルチャーショックを率直にユーモラスに書きとめる。たとえば学校の正月料理はこんな風。
「どんなワインと比べても美味(おい)しくなく大嫌いな日本酒、悪臭のあるきのこと緑色のものが入ったスープ。するめといかの煮物がお昼の献立でした。するめを食べてみたのですが、靴の紐と区別がつかないような味がしました」
一方、アリスの洋館を訪ねた津田梅子の叔母たちの様子。
用心深く椅子のはじっこに腰かけ、それでもなお、珍しいものがないかと鶴のように首をのばして部屋を見まわしていました.
アリスは明治の上流社会に飛び込んできた。そのため天長節の祝には明治天皇を側近く見、鹿鳴館のパーティーにも出、特異な体験をすることができた。しかし、牧師の娘であるアリスは、むしろふつうの社会を静かに観察する。往来に多い子供たち、露店商や団子坂菊人形などの見世物、芝の勧工場での買い物、神式や仏式の葬式体験、馬丁の離婚などを書きとめている。その目の公平なことに感銘を受けた。
たとえば華族女学校の生徒を見て、ヴァージニア州ハンプトンで教えていた貧しい黒人の子供たちを思いだす。「ある一つの点で彼らはとてもよく似ているからです。それは、彼らの人生は生まれ育った環境に束縛され、自由に生きることができないという点です」
日本人の多くは、ちょうど私たちアメリカ人がラテン語やギリシャ語を勉強するように英語を学ぶようです。つまり、文学を学ぶために読み方を勉強し、英語の発音とか話し方を学ぶようなことは全然しないようです。
これなども、百年後の英語教育に通じないだろうか。
津田梅子や大山捨松も、偉人伝の中よりは、こうした親友の日記の中の方が生き生きと動き出す。とくに親切な夫大山巌、彼女をベーコンチャンと呼ぶ息子らがいる捨松一家はいい雰囲気だ。
「天皇のお顔立ちは彫りが深くどっしりしています。どことなくインカの王に似ています」、「皇后は、小さな痩せた女性で、彼女の顔は、私にはとても悲しそうで、何かを耐え忍んでいるようにさえ見えました」
明治の日本が、異文化というプリズムの向こうに見えてくる。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
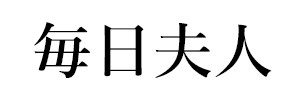
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする











































