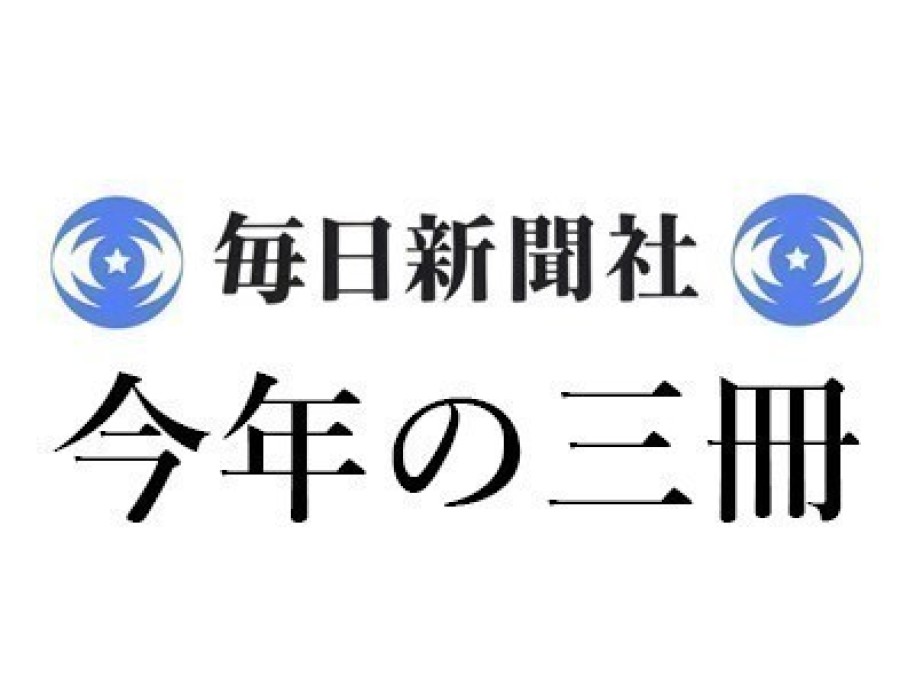書評
『月島物語』(集英社)
月島の幸せ
江戸や東京の名を冠した本が次々と出るが、ブームを当て込んだ孫引きやつまみぐい本もいぜん多い。もっと小さな町の範囲でよいから、その風の匂いや人々のざわめきが聞こえる本が読みたい、というところへ四方田犬彦『月島物語』(集英社)があらわれた。著者は映画史・映像論を教える大学の先生。ニューヨークはマンハッタンの生活を切りあげて帰国し、どうも管理されたマンションを見て歩いても馴染めぬうち、月島の築六十年の長屋をみつけた。マンハッタンが島だったから、やはり水の風景のある島に住みたかった。銀座の映画の試写会へも歩いてゆける。
トラヴェリング・ライター(旅行作家)は世にひしめいている。物珍しい外国に取材して書いた小説も評判になる。が、住んでみるといかに違う世界がみえてくるか。彼は『ストレンジャー・ザン・ニューヨーク』につづき、ドウェリング・ライター(居住作家)としての二作目をものしたわけである。
著者はおずおずと路地に住い、住民たちに自分が受容されていく過程をうれしげに語る。「センセイ」と呼ばれ、宅配便を預かってくれたり、刺身のおすそわけに預かったり、戦後GIの横暴に屈しなかった鳶の頭の伝説を聞く。長屋の鍵はかけないし、好奇心からもんじゃ焼の店員にもなってみる。ネズミとりもしかける。ノーテンキなマスコミが一過性の取材で下町情緒を囃(はや)したてる間に、銭湯や長屋があっさりと壊されていくさまもつづる。
そんな日常的な目にくわえ、広く資料に当り、月島のダイナミックな歴史も詳しく書いている。ここは明治のなかごろに造られた埋立地であり、海水浴場、別荘、工場地帯、そして庶民の集合住宅すなわち長屋群ができ、いまやウォーターフロントの最前線へとめまぐるしく変わった。
島崎藤村や三木露風の滞在した伝説的旅館、海水館の記憶も面白い。大岡昇平、きだみのる、吉本隆明らゆかりの人々についても語り、黒沢明「酔いどれ天使」、小津安二郎「風の中の牝鶏」など映画とのかかわりについての章は面目躍如といったところ。
月島を語るのにロートレアモンやボルヘスやランボーまで持ち出されるのにはややヘキエキだが、彼のような間口の広いインテリがたまたま住み込んだことによって、これだけ多彩で深みのある町の物語が残ったことは月島にとって幸せだろう。最終章「路地に佇む」の文章が絶品だ。
たとえ町がポンペイのように一日にして崩れ果てようとも、その日まで玄関先の金魚鉢に餌を撒(ま)き、格子戸に這う朝顔の蔓の具合を確かめるような凡庸な生活者でありつつ、路地の視座を保つ批評家でありたいと願うばかりである。
凡庸どころか非凡な決意である。
【単行本】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
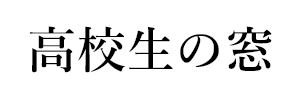
高校生の窓(休刊) 1993年~1996年
ALL REVIEWSをフォローする