書評
『〈報道写真〉と戦争: 1930-1960』(吉川弘文館)
翼賛の実像をあらわに
戦時中、日本軍に協力した文化人や芸術家は多い。協力しなければ軍に疎まれるばかりか、資材などの入手も厳しかった。写真とて同じ。とりわけ報道写真は軍にとって魅力的な存在だったのだろうとの思いで、本書を手に取った。まず戦前の広告写真に触れる。例えば木村伊兵衛は広告写真に携わったが、ドイツから帰国した名取洋之助の報道写真(ルポルタージュ・フォト)に理想を見いだした。やがて土門拳らも名取に影響されていく。
1937年に日中戦争となるや、名取は軍部と親密な関係を結び始める。彼が南京で撮影した、日本軍に処刑されるまでの中国人ゲリラの写真は、米独の2誌に掲載されたが、説明文はそれぞれ逆の意味付けをされた。戦争を異なる方向で宣伝したい両国の思惑が見える。
やがて名取らは「中支軍報道部写真班」と称し、「事務所の経費も全部軍」の出資で、欧米に日本軍の残虐行為を否定する立場を担い始めた。木村らの中国での役割は「国民生活を実際以上の水準に見せる『宣伝写真』だった」。
太平洋戦争に突入し、「真珠湾攻撃の戦果を上げた海軍」の写真に多数の報道写真家が携わる中、41年には「情報局の国家宣伝一翼の写真技術者」の一団に土門拳らも参加して「准国家機関」を設立。「カメラを銃としペンとする(略)大東亜共栄圏確立の大理想達成」と、写真家の参戦宣言をした。体制側は日本写真の「精神論」の浸透を推進し、軍部主導の翼賛写真へと導いていく。
本書は綿密に資料を調べ、多岐にわたり戦時中の写真活動をつづる。カメラ雑誌、日本写真家協会、アマチュアなどに触れつつ、戦後の写真家たちの動向にも言及。敗戦後は、連合国軍総司令部(GHQ)が報道規制を行う中での写真家たちの苦悩や工夫を、大量の資料から抽出する。
写真家がいかに軍や国家に利用されやすいかという現実が、著者の筆によって迫ってくる。集団的自衛権や「イスラム国」の現実感の中で、決して過去になってはいないことを感じながら読んだ。
[書き手] 大石 芳野(おおいし よしの・写真家)
初出メディア
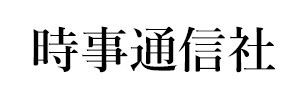
時事通信社 2014年11月
ALL REVIEWSをフォローする









































