書評
『歩くひとりもの』(筑摩書房)
ふむふむ、やっておるな
過渡期なのである。東京では四、五十代の男性の一〇%近くが独身なのに、もはや「男やもめ」とはいわなくなった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1993年頃)。離婚した私も「出戻り」とか「バツイチ」なんて言われたことがない。独身の女の友だちの誰も「行かず後家」とか「ハイミス」なんて言葉は聞いたこともないだろう。
こんな差別語が死語になってうれしいことだ。
核家族も傾斜生産方式による独身者の都市流入が成立根拠であり、それがあの「高度成長」をもたらしたのなら、五五年体制と同じく、そろそろ命運が尽きてもいいころだ。
で、津野海太郎『歩くひとりもの』(思想の科学社・ちくま文庫)。ちかごろ出色の本と思う。
著者は一九三八年生れ。本づくりや芝居の仕事にかかわってきたベテランのひとりもの。
その日常が淡々と語られる。ユーモアをもって。
朝起きると、まっさきに手帳をひらき、きょうやるべきことのリストをつくる。そのほとんどが家事に関すること。やりとげると、「うれしさのあまり」ついバラの花を買ったりするのは家事の素人だからという。私の手帳も開いてみると「ポリバケツ、粗大ゴミ連絡、予防注射、給食費支払い、PTA、図書館」などと書いてあるが、子どもが三人いるため雑用多く、いちいちバラの花束なぞ買ってらんない。
ひとりものの大先輩、長谷川如是閑にならってドリップ式のコーヒーを悠々といれ、「ゆっくりコーヒーをいれるという日常の習慣に根ざした本当の社会主義」を夢想したりする。ここでも子持ちのひとりものはイイナア、と嘆息してしまう。
ところが長谷川如是閑にしても、会津八一も、正岡子規も、昔のひとりものの男には妹とか親戚の女性とか、「妹の力」という奥の手があった、ということに著者は気づく。ひとりったって性生活がないだけで家庭はあるではないか。ちょっとずるいや、と現代のひとりものはつぶやく。
人をのびのびさせる料理書について、ひとりで痛みをがまんすることについて、手紙嫌いについて、自分を変えたいときには友だちを全とっかえする、といった様々な日常の知恵が示される。話法はアンチ・クライマックス。いろいろ引用されるが適切でひけらかしっぽくなく、じつに魅力的だ。
たとえばブレヒトがスターリン批判のさい、自分をも笑いとばしながら、当局を煙にまいた芝居をつくった。それについて著者は「ひとりの「私」が世界に責任をとることができるという立場そのものに距離をおく」という教訓を引き出す。これはひとりものにも有効だろうが、市民運動、組合運動家にも必要な息抜きだろう。
海老坂武『シングル・ライフ』(中央公論社)はちょっとお洒落で、むしろ自由恋愛を楽しむための独身というイデオロギーが強かった。それと対照的に、この本は衣食住や手紙や電話、すなわち暮らしの細部からひとりものの男が浮び上ってくる。ふむふむ、やっておるな。
家族も敵視しない。子どもも嫌いでない。病気すると周囲の心配がうれしい。ときどき女友だちが気になる。そんな開かれた、正直なひとりものがここにいる。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
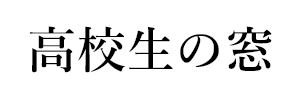
高校生の窓(休刊) 1993年-1996年
ALL REVIEWSをフォローする










































