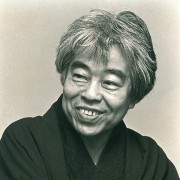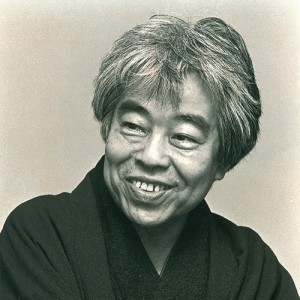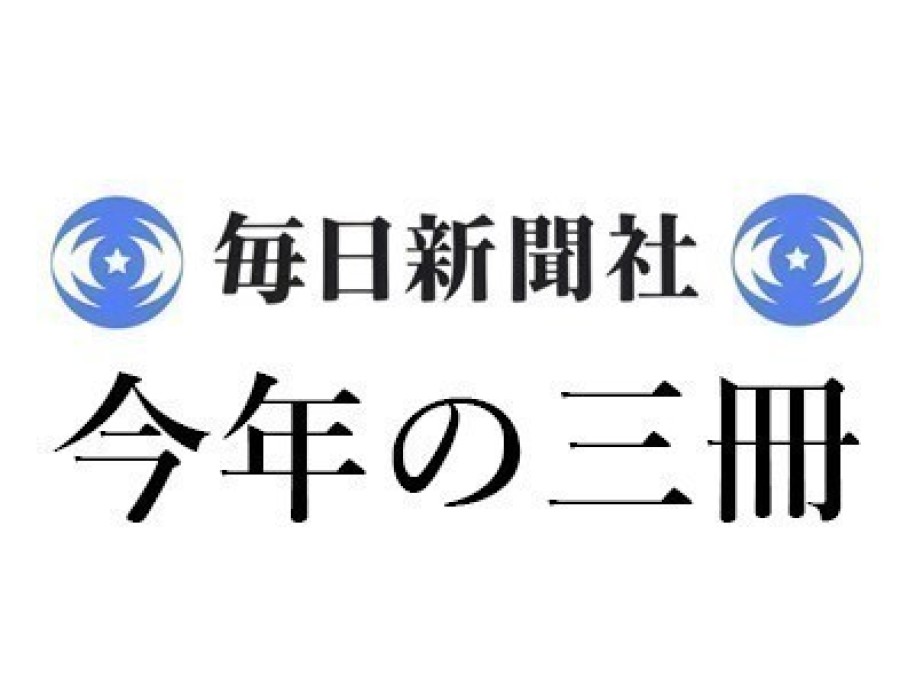書評
『私説国定忠治』(中央公論新社)
壮絶に生きた男への深い共感
国定忠治はうどんが好きだったという。あやまって灰の中に落したものまで拾い、灰のついたまま食べたという話さえある。まわりの者が注意すると、「うどん一本でもお百姓の汗の結晶だ。おれのような奴が粗末にしたのではバチがあたる」といった。すこし話ができすぎている感じだが、これは子母沢寛がまだ読売の社会部遊軍だったころ、忠治の七十五年祭の取材にあたり、忠治の甥である長岡利喜松老人からいろいろ話を聞いた。利喜松老人にいわせると、赤城の山にこもっていた忠治は、例のまけず嫌いからそんなことを言ったものの、実際は腹をすかしていて、こんなものがうまかったのかもしれない、と語ったという。実情はそうだったのであろうが、忠治のセリフは義民説話の根拠ともされ、やがて虚構化されてゆく。虚像と実像との間は紙一重で、同じ話が受けとめかたによって無限の距離をうんでゆくものなのだ。
笹沢左保はこの作品の冒頭で忠治の容貌についてふれ、人によってまったく正反対の印象を与えたと述べているが、大衆の間に伝承された義民忠治の像と、しようのない旦那博奕のボスとしての実像の間には、かなりなへだたりができている。笹沢左保はその二つの説をふまえながら、それなりの忠治像をまとめようとこころみているのだ。「私説国定忠治」と題したのもそのためではないか。
忠治は文化七年に上州佐位郡国定村、現在の群馬県佐波郡東村東国定の素封家の家に生れた。普通ならば富農の主として安穏な生涯を過ごしたはずだが、その平穏無事を嫌い、壮絶な生きかたを夢みて、十代のときから賭場へ出入りし、二十一歳のときに百々(どうどう)村の紋治の縄張りをゆずられ、やがて隣接する島村のボス伊三郎を斬って信州へ逃げる。
話はこの伊三郎の賭場へ忠治がなぐりこみをかけ、簀巻(すま)きにされるところを乞食坊主の円蔵に助けられるあたりからはじまる。忠治の反骨ぶりをみこんだ円蔵は、その軍師になろうと誓い、忠治と円蔵の切っても切れない縁がうまれる。しかし円蔵の留守中に一の子分三ツ木の文蔵が伊三郎一家に殴打された腹いせから、伊三郎を襲い、わらじをはいて信州へ逃げこんだ。だが忠治は何もせずにひそんでいるなどということは性分にあわない。賭場荒しをくりかえし、ふたたび上州へもどって赤城の山にかくれる。
山にこもった忠治は、円蔵の進言をいれていくつもの堀をめぐらす。それは農民のこころをつかむことだった。たまたま深刻な飢饉にみまわれていたときだけに、忠治が行なった種々のほどこしや土木工事は、おおいに人々の支持を得た。義民説話がふくらんでゆくのもそれ以後のことだ。忠治は円蔵の忠告にしたがっただけでなく、おりにふれて円蔵から多くのものを学んだ。開明的な思想を抱くようになったのもそのためで、大戸の関所破りも彼の反権力意識のあらわれだった。
忠治は嘉永三年七月に脳出血で倒れ、逮捕された後、その年の暮れに磔(はりつけ)となった。四十一歳である。笹沢左保は忠治を反骨のかたまりとして描き、それに円蔵の深慮を対応させている。
ぬるま湯につかったようなありかたに反逆し、男っぽく生きた忠治の姿に、著者は現代にも通じる共感を覚えているのではないだろうか。
ALL REVIEWSをフォローする