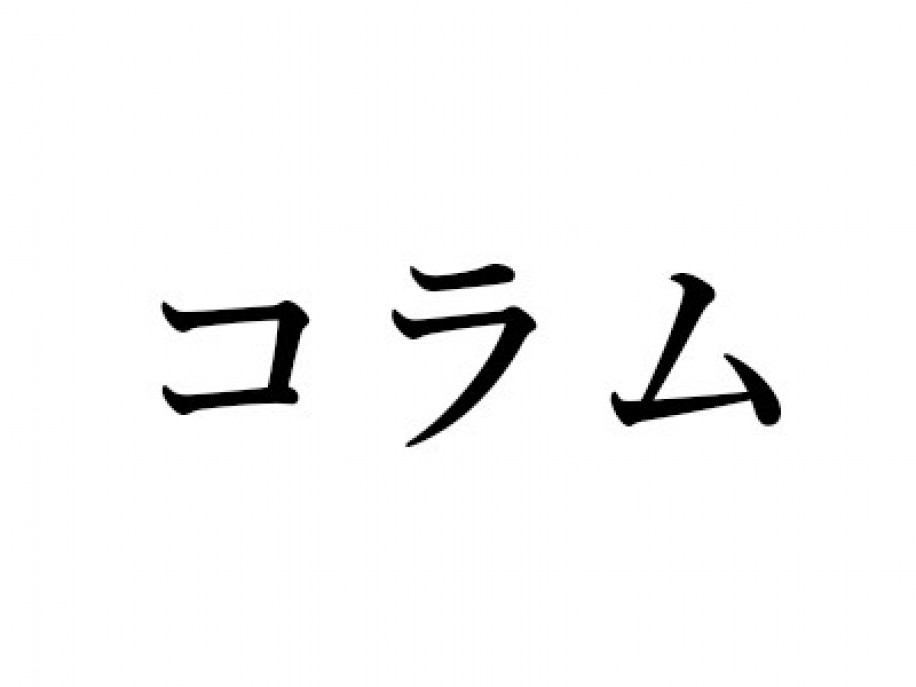書評
『クール・ルールズ』(研究社)
「カッコいい」の変遷クールに分析
「カッコいい」「ダサい」。隔たった世代のあいだで通じる言葉が乏しくなる一方で、この言葉だけはいまも、たぶん五十代から十代まで共有できる。チープなもの、みすぼらしいもの、アンバランスなものがカッコよさにぎりぎりのところで反転する瞬間の感覚までふくめて。よいこと・わるいことについてすら合意がなりたちにくいそんな不確実な現在でも、ひとは「カッコいい」か否かの判定には迷わない。<クール>という感覚。これを日本語に置き換えれば、たぶんこの「カッコいい」にいちばん近いだろう。<クール>が米国で一気に浮上した一九五〇年代には、それはスクエア(堅物・石頭)への反逆としてあった。もとはといえば、奴隷制下、黒人たちがひどい差別や搾取のなかで、感情を表に出さずに虐待や侮辱に耐える心的な防衛機制であった<クール>、それに戦後、白人中流階級の若者たちが飛びついた。貧困から不安へと時代の鬱(ふさ)ぎが重心移動を起こしたからだと、著者たちは見る。
ビート世代からカウンターカルチャー世代まで、このナルシスティックで無関心で悦楽的な「個人主義」者たちは、ファッション、音楽からアート、政治運動まで、さまざまな転覆をくりかえした。が、それは運動の物質主義的な屈折でもあり、カウンターカルチャーが「若い消費者たちの心と財布をつかむ方法」となり、ファッション、音楽、ソフトドリンクを通じて「資本主義の尖兵(せんぺい)」となりゆく過程でもあった。そしていまでは、「特注のペイントをほどこしたハーレーに乗るテレビ局の重役」を見かけてもだれも驚かない。
なぜか?
分析の眼(め)は細心である。パンクの装飾過剰とけたたましさに<クール>が内在させているバロック的な感受性を、ヤッピーの上昇志向に<クール>の快楽主義を、サイコバブルやセラピー文化に<クール>の強度の感情主義を、ビッグ・スポーツにおけるテクニックの何げなさに<クール>がルネッサンスの廷臣たちから受け継いだ「さりげなさ」を、巨大独占企業を打ち砕くパソコン産業の創業者たちに<クール>の反体制気質を、企業人に忠誠心よりは順応性をもとめるクリントンの民主党やブレアの新労働党に<クール>の柔軟性を、冷笑と無関心と官能をまき散らすメディア・プロデューサーに<クール>の空虚な全体主義を、著者たちは読み取る。そして、<クール>はその反抗的な姿勢は失いつつも社会の襞(ひだ)の一つ一つに浸透してゆき、ついに脱工業化時代に支配的な思考スタイル、ないしは道徳的価値観へと変容したと結論づける。
<クール>についてのとてもクールな視線である。
朝日新聞 2003年6月29日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする