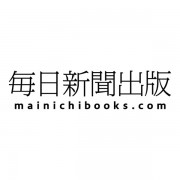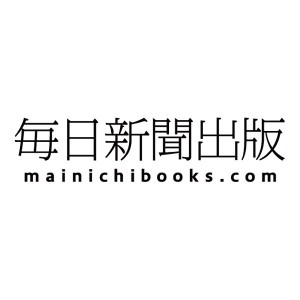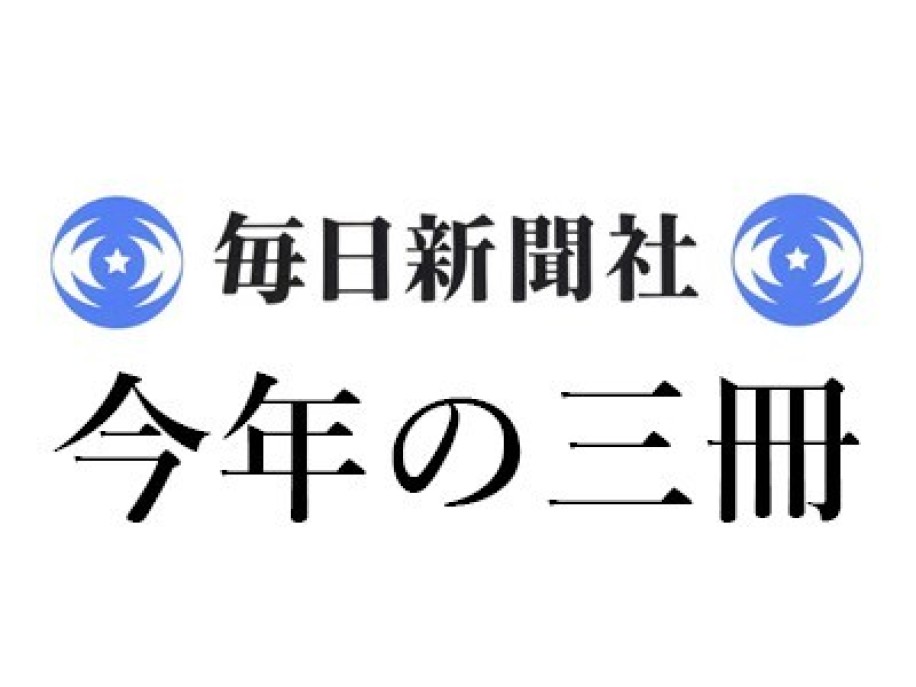前書き
『この国のかたちを見つめ直す』(毎日新聞出版)
1930年代の日本の外交と軍事を専門とする東京大学教授・加藤陽子氏の著書『この国のかたちを見つめ直す』が2021年7月27日、発売となりました。
本書に収録された文章は、2010年から2021年現在までに書かれたものです。この10年余という時間は、その入り口と出口が、日本にとって、そして世界にとって重大な経済危機に見舞われた年として記憶されています。危機の時代には、国家と国民の関係を国民の側から問い返し、見つめ直すことが必須だと説く加藤氏の「はじめに」を特別公開します。
内容によって六つの章に分けられたこの本は、ほぼ3種の文章からなっている。一つは、2010年4月から月1回連載された「時代の風」というエッセー、二つは、2020年4月から同じく月1回連載中の「加藤陽子の近代史の扉」というコラム、そしてその間に「今週の本棚」に書かれた書評であり、若干の例外として数本のインタビュー記事も含むが、その全てが「毎日新聞」に掲載されたものだ。
原稿用紙にして4~5枚、一息でとは言わないが通勤途中の1駅ほどで読める分量で、国家と国民、東日本大震災、天皇と天皇制、戦争の記憶、世界と日本、を論じている。2021年5月18日に内閣府が発表した2020年度のGDP(国内総生産)は、世界的に感染拡大が見られた新型コロナウイルスの影響もあって、実質伸び率でマイナス4・6%を記録し、比較可能な1995年度以降最大の下落となった。これは、リーマン・ショックに伴う世界的な金融システムの混乱に揺れた2008年度より悪いことを意味する。
本書の文章が書かれたほぼ10年間という時間軸は、その入り口と出口において尋常ならざる経済的な危機に刻印された時期となった。著者は、1930年代の日本の外交と軍事を専門としてきたが、この1930年代の危機とは、世界的規模における経済的危機であり、英米ソ日などが角逐する極東の軍事的危機でもあった。著者が2010年から現在に至るまでにその時々の「今」を見つめる際、脳の中で参照するインデックスはどうしてもこの1930年代の歴史ファイルとなるが、期せずして最適の引証例になったかもしれない。
本書のタイトルは、司馬遼太郎が1986年から「文藝春秋」に連載したコラム「この国のかたち」(後に『この国のかたち』文藝春秋)を踏まえている。明治国家が日露戦後に変質していった理由を司馬は、統帥権独立の法解釈の暴走が鍵とみた。その際の「国のかたち」とは、国柄、国の成り立ち、政治文化を意味する。著者には、司馬のこのコラムに触発され、それを批判的に論じた論考「統帥権再考」(『戦争の論理日露戦争から太平洋戦争まで』勁草書房)もある。
危機の時代には、国家と国民の関係を国民の側から問い返して、見つめ直すことが必須となろう。本書がそのためのハンドブックともなれば幸いである。
[書き手]加藤陽子(東京大学大学院人文社会系研究科教授)
本書に収録された文章は、2010年から2021年現在までに書かれたものです。この10年余という時間は、その入り口と出口が、日本にとって、そして世界にとって重大な経済危機に見舞われた年として記憶されています。危機の時代には、国家と国民の関係を国民の側から問い返し、見つめ直すことが必須だと説く加藤氏の「はじめに」を特別公開します。
内容によって六つの章に分けられたこの本は、ほぼ3種の文章からなっている。一つは、2010年4月から月1回連載された「時代の風」というエッセー、二つは、2020年4月から同じく月1回連載中の「加藤陽子の近代史の扉」というコラム、そしてその間に「今週の本棚」に書かれた書評であり、若干の例外として数本のインタビュー記事も含むが、その全てが「毎日新聞」に掲載されたものだ。
原稿用紙にして4~5枚、一息でとは言わないが通勤途中の1駅ほどで読める分量で、国家と国民、東日本大震災、天皇と天皇制、戦争の記憶、世界と日本、を論じている。2021年5月18日に内閣府が発表した2020年度のGDP(国内総生産)は、世界的に感染拡大が見られた新型コロナウイルスの影響もあって、実質伸び率でマイナス4・6%を記録し、比較可能な1995年度以降最大の下落となった。これは、リーマン・ショックに伴う世界的な金融システムの混乱に揺れた2008年度より悪いことを意味する。
本書の文章が書かれたほぼ10年間という時間軸は、その入り口と出口において尋常ならざる経済的な危機に刻印された時期となった。著者は、1930年代の日本の外交と軍事を専門としてきたが、この1930年代の危機とは、世界的規模における経済的危機であり、英米ソ日などが角逐する極東の軍事的危機でもあった。著者が2010年から現在に至るまでにその時々の「今」を見つめる際、脳の中で参照するインデックスはどうしてもこの1930年代の歴史ファイルとなるが、期せずして最適の引証例になったかもしれない。
本書のタイトルは、司馬遼太郎が1986年から「文藝春秋」に連載したコラム「この国のかたち」(後に『この国のかたち』文藝春秋)を踏まえている。明治国家が日露戦後に変質していった理由を司馬は、統帥権独立の法解釈の暴走が鍵とみた。その際の「国のかたち」とは、国柄、国の成り立ち、政治文化を意味する。著者には、司馬のこのコラムに触発され、それを批判的に論じた論考「統帥権再考」(『戦争の論理日露戦争から太平洋戦争まで』勁草書房)もある。
危機の時代には、国家と国民の関係を国民の側から問い返して、見つめ直すことが必須となろう。本書がそのためのハンドブックともなれば幸いである。
[書き手]加藤陽子(東京大学大学院人文社会系研究科教授)
ALL REVIEWSをフォローする