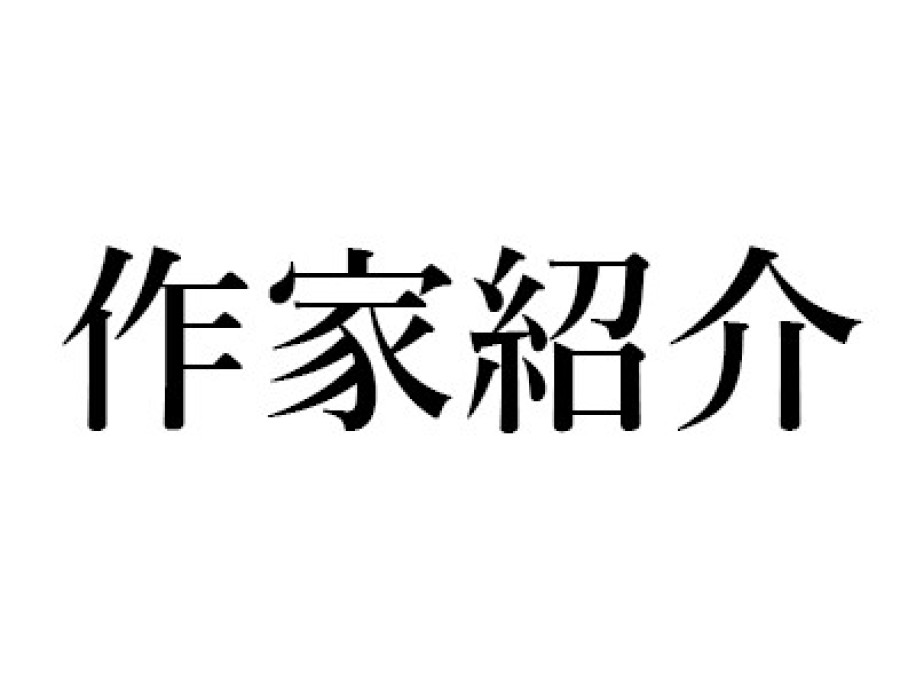書評
『ドレフュス事件: 真実と伝説』(法政大学出版局)
繰り返される排除と人種差別
一九〇〇年前後にフランスの国論を二分したドレフュス事件は一九〇六年には完全決着がついたはずだった。だが、ゾラ研究の泰斗が事件の虚実を再点検した歴史シリーズ「真実と伝説」の一冊である本書によると、ドレフュス事件は潜在的には世界中どこでも何度でも起こる可能性があるという。だが、そもそもドレフュス事件とはどのような事件だったのか?
(1)一八九四年、フランス陸軍はドイツ内通容疑でユダヤ人士官ドレフュス大尉を軍法会議にかけ、有罪を宣告、仏領ギアナに流刑。(2)防諜(ぼうちょう)局長となったピカール中佐は一八九六年、内通者はエステラジー少佐であると突き止めるが、報告は将軍たちに握り潰される。(3)その直後、アンリ少佐がドレフュス有罪を証明する偽造文書を作成、ピカールは左遷される。(4)一八九八年一月十一日、エステラジーは軍法会議で無罪判決を受ける。(5)二日後、ゾラはクレマンソー主筆の《オーロール》紙に共和国大統領への公開書簡「私は告発する」を発表、ドレフュスの再審を要求する。(6)反ユダヤ主義者ドリュモン主筆の《リーブル・パロール》紙をはじめとする国権勢力がこれに猛反発。一方、知識人たちは連名でゾラを擁護。(7)ゾラは有罪を宣告され、イギリスに亡命。(8)アンリ中佐が文書偽造を自白の後、獄中で自殺。(9)ゾラ、自宅で一酸化炭素中毒死。(10)一九〇六年、ドレフュスの有罪判決は破棄され、ピカールも復権。
以上の経緯を踏まえ、著者は当時流布していた様々なポスト・トルースを検証しながら次のように言う。「あまりに単純な本事件はすぐに決着がつくはずだった。しかし、進展するにつれ、事態は複雑さを増す一方となった。真実が明るみになるたびに、それに対立する伝説がひとつ現れたからである」。こうした伝説の一つがドリュモンの唱えるユダヤ組合説。「金を持っているユダヤ人たちは、彼らの同宗者である裏切り者のドレフュスの放免を得るために、莫大(ばくだい)な資金源を使って国際的な組合を作っているというのである」。ゾラはユダヤ組合説は集団的幻想の産物と切って捨てるが、反ドレフュス派は陸軍への誹謗中傷は反仏的で、国家への裏切りであるという論法で反論する。
知識人・文化人ばかりか極左派さえ二分され、新しい党派地図ができあがる。反ドレフュス派の作家モーリス・バレスは「ドレフュスが売国奴であり得るということを、私は彼の民族から結論する」と断言し、再審要求署名に加わったインテリたちを「普通のフランス人のように考えることを恥ずかしいと思う憐れな愚か者たちだ」と揶揄する。
著者の総括によると、ドレフュス事件が今日的課題であり続ける理由は二つある。
一つは理性と国家の利害が対立したとき断固として理性を選び、自らの選択を社会的に表明する参加型知識人の出現を見たこと。もう一つは反ユダヤ主義に象徴される排除と人種差別のイデオロギーが歴史の前面に登場したこと。「それは、不寛容の言説の繁殖によって特徴づけられた世界において、現代が立ち向かうべき試練である」
著者は「この事件が終われば終わるほど、それが決して終わることはないのは明らかだ」というシャルル・ペギーの言葉を引用して最後を締めくくる。歴史を学ぶ意義を教えてくれる一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする