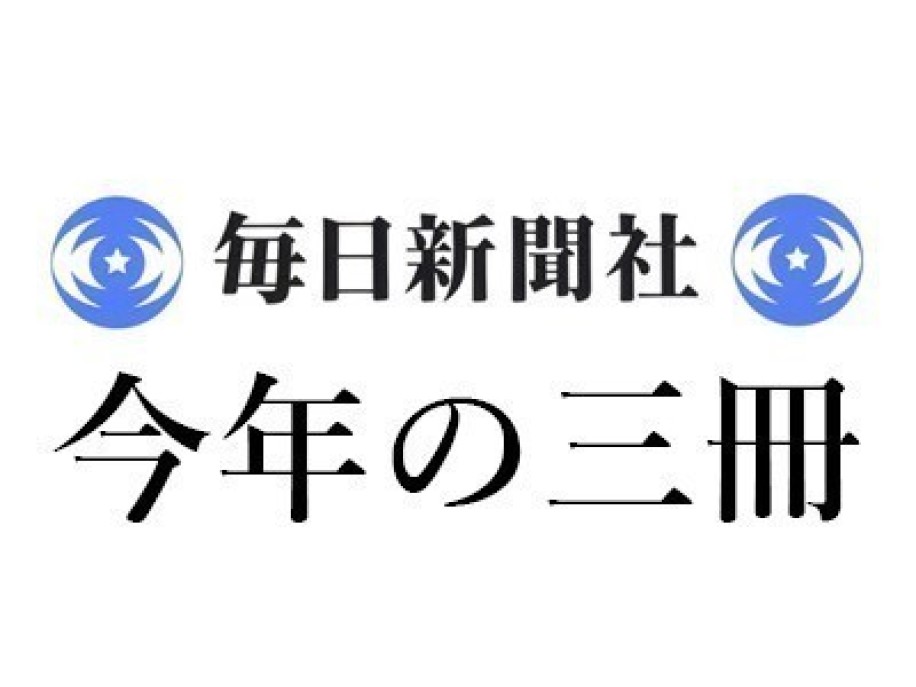前書き
『アートからたどる 悪魔学歴史大全』(原書房)
人類は「悪魔とは何か」を探し続けてきた。古代から現代にいたるまで、その時代ごとに描かれてきた悪魔と人間の関係を、300点あまりの絵画や映像とともにたどった『アートからたどる 悪魔学歴史大全』より、序章より一部を公開します。

2 悪魔とは、悪魔を定義する暗喩と象徴とイメージのネットワークであり、時代とともにそれらがさまざまなかたちで関わりあったり、変化していったりする。
3 象徴として、悪魔はさまざまなものをあらわす。ときに矛盾するものをあらわす場合もある。
4 美学とオカルトというカテゴリーのあいだにはっきりとした区別はない。悪魔の詩学的定義とは、文学と魔法を基本的に同じものと考えるという解釈の枠組みに従う。
5 悪魔のなかには、ある特定の時代につねに象徴として他の優位に立つものがいる。
6 悪魔は超越的なもの、超自然的なもの、崇高なものの交わるところにいる。悪魔はその名のとおり邪悪なものだが、同時にまたその名のとおり聖なるものの一面でもある。この神的なるものと悪魔的なるものの両方を包含する存在の核にはなにかがあるが、我々はそれを正確に描写することばをもたない。
7 悪魔学の歴史は、すなわちこの世界の歴史である。
本書ではおもにこれらの原理を解釈していくのだが、この原理の大部分は本書を実際に書いていくうちにあきらかになってきたものだ。こういった原理は一連の公理、議論あるいは命題として自明である必要はないのだが、だからこそ私はこれらの原理を体系化してみることにした。
本書の章立てがその体系化された図式に従って組み立てられていることには、ひとつの意味がある。たとえば、ある時代の精神を代表する特定の悪魔を分析しようとすれば、文学作品を詳細に読みこまねばならないし、個々の悪魔の象徴的な意味が移ろいやすいことも強調しておかねばならない。一例として、ルキフェルは邪悪と叛逆を体現する堕天使から、ロマン主義の英雄へと進化をとげていくのだ。この漠然としたなにか、ことばでは正しく言いあらわすことのできない聖なるものの存在があるとすれば、それをとらえることこそが本書執筆の動機であり、我々はつねにそこに向かって議論を組み立てていかねばならない(もちろん、そのためにその重要さが損なわれることはない)。

本書の全体を眺めてみれば、個々の悪魔の歴史というよりは悪魔学の歴史に近いものだということがわかるだろう。確かに本書には、悪魔の序列から古代の魔導書とその呪文、オカルトの技に優れているという名声を得た魔術師の名にいたるまで、読者が期待するようなものの全てが含まれている。バアルやマモンといった名をもつ異世界の存在に対する考察も豊富に見出すことができるだろう。
しかし本書はそのような生き物を百科事典的に並べるものというよりは(そういう本はほかにたくさんある)、学問の一領域としての悪魔学の幅広い歴史を記した世界初の本であると考えていただきたい。つまり、本書がもっとも重きをおいているのは、人々が――コルネリウス・アグリッパに始まりジョン・ディー、アレイスター・クロウリー、アントン・ラヴェイにいたるまで――悪魔的なものをどのように想像してきたか、そしてその結果としてどのような作品が生みだされてきたか、ということなのだ。
さらに本書でとりあげる人物は、一般的にオカルティストというカテゴリーでとらえられる人々のみに限らない。たとえば表向きには主流とされる(なかでもとくに)ルネ・デカルト、フリードリヒ・ニーチェ、ハンナ・アーレントといった哲学者たちの著作に対しても、悪魔的なものがどのような影響を与えたかという分析を行っている。神秘学の伝統は、正統的な研究機関からは当たり前のように無視されてきたが、じつは一般に思われているより大きな影響力を放っており、悪魔的なもののきらめく光沢は世間で認められているよりはるかに離れた領域においても見出すことができるのだ。

私は(正確には)研究者ではあるのだが、本書はいわゆる伝統的な意味での研究書ではない。とはいえ、悪魔を解釈し批評するという目的のもとに書かれた書物であることは間違いないし、本書の執筆にあたって多くの歴史家や神学者、哲学者、文学理論の研究者の非常に貴重な研究に頼った部分は大きい。悪魔に関するあらゆることを網羅したなどとうそぶくつもりはないが、その内容が多岐にわたることは事実だ。もちろん、本書に私自身の物の見方や興味、弱味、偏見が反映されていることに疑いの余地はなく、それについては寛大なるご理解とお許しをいただきたいと思う。
ここでいかなる個別の分析や、綿密なテキストの解釈、特定の人物やできごとやテキストの詳述にも増してなによりも重要なのは、本書のもっとも基本となる論拠――すなわち、悪魔はこの世界の王子であり、したがって悪魔学の歴史とは事実上この世界の歴史であるという認識だ。
「悪魔の詩学的定義」とはつねにことばではあらわしようのないものを表現しようとする試みなのだが、その前提としてあるのは、ことばとはつねに変化していってしまうものであり、それゆえ悪魔はそれぞれの時代におけるかけがえのない想像力による暗喩を用いることによって、みずからの存在を邪悪なものだけでなくより一般的な現実との関わりのなかに特異なものとして出現させるのだ、という考えだ。
細かいところを見れば確かにケチをつけたくなるような部分もたくさんあるだろうが、たとえ自分の学者としての経歴を損うことになろうと、私はつねに完璧な正しさを求めるよりも、面白さのほうを優先させてきた。できればその両方が実現できていることが理想だが、どちらを望むかと聞かれたら、少なくとも面白さが実現できればいいと考えている。
[書き手]エド・サイモン(著述家、英語学博士)
専門はルネサンス時代と宗教改革期の文学と宗教。『アトランティック』、『パリ・レビュー・デイリー』、『ワシントン・ポスト』、『ニューヨーク・タイムズ』などさまざまな媒体への寄稿多数。近著に『ユートピアに刻まれた印:ルネサンスの改革主義 Printed in Utopia: The Renaissance's Radicalism』と『ピッツバーグのもうひとつの歴史 An Alternative History of Pittsburgh』(未訳)がある。

悪魔の詩学的定義
1 悪魔が存在するかどうかにかかわらず、人々の悪魔に関わる経験は絶対的に存在する。2 悪魔とは、悪魔を定義する暗喩と象徴とイメージのネットワークであり、時代とともにそれらがさまざまなかたちで関わりあったり、変化していったりする。
3 象徴として、悪魔はさまざまなものをあらわす。ときに矛盾するものをあらわす場合もある。
4 美学とオカルトというカテゴリーのあいだにはっきりとした区別はない。悪魔の詩学的定義とは、文学と魔法を基本的に同じものと考えるという解釈の枠組みに従う。
5 悪魔のなかには、ある特定の時代につねに象徴として他の優位に立つものがいる。
6 悪魔は超越的なもの、超自然的なもの、崇高なものの交わるところにいる。悪魔はその名のとおり邪悪なものだが、同時にまたその名のとおり聖なるものの一面でもある。この神的なるものと悪魔的なるものの両方を包含する存在の核にはなにかがあるが、我々はそれを正確に描写することばをもたない。
7 悪魔学の歴史は、すなわちこの世界の歴史である。
本書ではおもにこれらの原理を解釈していくのだが、この原理の大部分は本書を実際に書いていくうちにあきらかになってきたものだ。こういった原理は一連の公理、議論あるいは命題として自明である必要はないのだが、だからこそ私はこれらの原理を体系化してみることにした。
本書の章立てがその体系化された図式に従って組み立てられていることには、ひとつの意味がある。たとえば、ある時代の精神を代表する特定の悪魔を分析しようとすれば、文学作品を詳細に読みこまねばならないし、個々の悪魔の象徴的な意味が移ろいやすいことも強調しておかねばならない。一例として、ルキフェルは邪悪と叛逆を体現する堕天使から、ロマン主義の英雄へと進化をとげていくのだ。この漠然としたなにか、ことばでは正しく言いあらわすことのできない聖なるものの存在があるとすれば、それをとらえることこそが本書執筆の動機であり、我々はつねにそこに向かって議論を組み立てていかねばならない(もちろん、そのためにその重要さが損なわれることはない)。

本書の全体を眺めてみれば、個々の悪魔の歴史というよりは悪魔学の歴史に近いものだということがわかるだろう。確かに本書には、悪魔の序列から古代の魔導書とその呪文、オカルトの技に優れているという名声を得た魔術師の名にいたるまで、読者が期待するようなものの全てが含まれている。バアルやマモンといった名をもつ異世界の存在に対する考察も豊富に見出すことができるだろう。
しかし本書はそのような生き物を百科事典的に並べるものというよりは(そういう本はほかにたくさんある)、学問の一領域としての悪魔学の幅広い歴史を記した世界初の本であると考えていただきたい。つまり、本書がもっとも重きをおいているのは、人々が――コルネリウス・アグリッパに始まりジョン・ディー、アレイスター・クロウリー、アントン・ラヴェイにいたるまで――悪魔的なものをどのように想像してきたか、そしてその結果としてどのような作品が生みだされてきたか、ということなのだ。
さらに本書でとりあげる人物は、一般的にオカルティストというカテゴリーでとらえられる人々のみに限らない。たとえば表向きには主流とされる(なかでもとくに)ルネ・デカルト、フリードリヒ・ニーチェ、ハンナ・アーレントといった哲学者たちの著作に対しても、悪魔的なものがどのような影響を与えたかという分析を行っている。神秘学の伝統は、正統的な研究機関からは当たり前のように無視されてきたが、じつは一般に思われているより大きな影響力を放っており、悪魔的なもののきらめく光沢は世間で認められているよりはるかに離れた領域においても見出すことができるのだ。

私は(正確には)研究者ではあるのだが、本書はいわゆる伝統的な意味での研究書ではない。とはいえ、悪魔を解釈し批評するという目的のもとに書かれた書物であることは間違いないし、本書の執筆にあたって多くの歴史家や神学者、哲学者、文学理論の研究者の非常に貴重な研究に頼った部分は大きい。悪魔に関するあらゆることを網羅したなどとうそぶくつもりはないが、その内容が多岐にわたることは事実だ。もちろん、本書に私自身の物の見方や興味、弱味、偏見が反映されていることに疑いの余地はなく、それについては寛大なるご理解とお許しをいただきたいと思う。
ここでいかなる個別の分析や、綿密なテキストの解釈、特定の人物やできごとやテキストの詳述にも増してなによりも重要なのは、本書のもっとも基本となる論拠――すなわち、悪魔はこの世界の王子であり、したがって悪魔学の歴史とは事実上この世界の歴史であるという認識だ。
「悪魔の詩学的定義」とはつねにことばではあらわしようのないものを表現しようとする試みなのだが、その前提としてあるのは、ことばとはつねに変化していってしまうものであり、それゆえ悪魔はそれぞれの時代におけるかけがえのない想像力による暗喩を用いることによって、みずからの存在を邪悪なものだけでなくより一般的な現実との関わりのなかに特異なものとして出現させるのだ、という考えだ。
細かいところを見れば確かにケチをつけたくなるような部分もたくさんあるだろうが、たとえ自分の学者としての経歴を損うことになろうと、私はつねに完璧な正しさを求めるよりも、面白さのほうを優先させてきた。できればその両方が実現できていることが理想だが、どちらを望むかと聞かれたら、少なくとも面白さが実現できればいいと考えている。
[書き手]エド・サイモン(著述家、英語学博士)
専門はルネサンス時代と宗教改革期の文学と宗教。『アトランティック』、『パリ・レビュー・デイリー』、『ワシントン・ポスト』、『ニューヨーク・タイムズ』などさまざまな媒体への寄稿多数。近著に『ユートピアに刻まれた印:ルネサンスの改革主義 Printed in Utopia: The Renaissance's Radicalism』と『ピッツバーグのもうひとつの歴史 An Alternative History of Pittsburgh』(未訳)がある。
ALL REVIEWSをフォローする