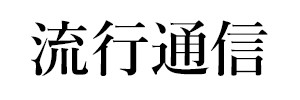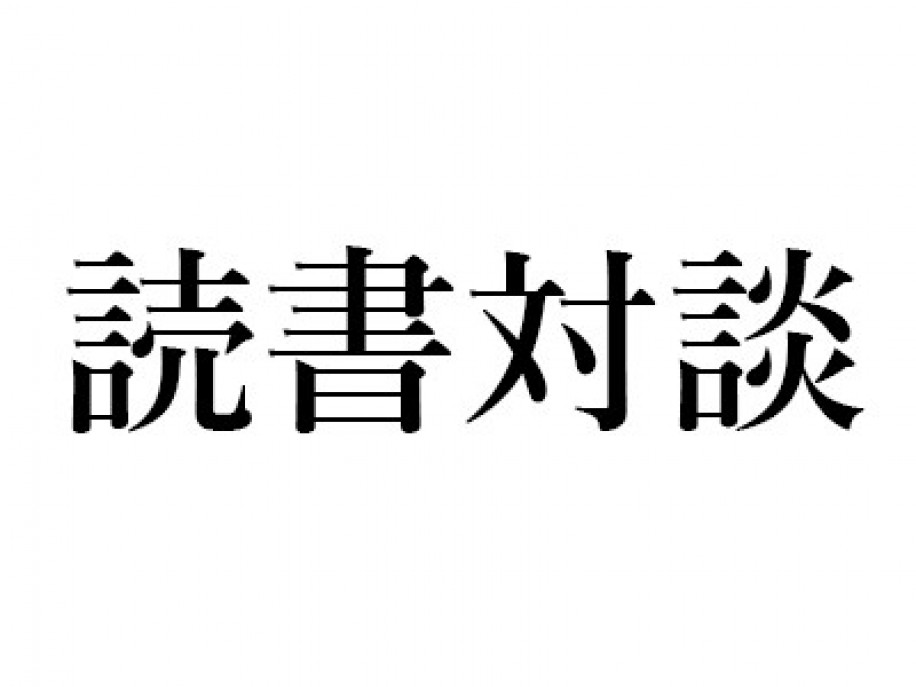書評
『フィンバーズ・ホテル』(東京創元社)
パリのとあるアパルトマンに住む住民を中心に、約一五〇〇名もの人物を登場させる奇想天外にして、空前絶後のポストモダニスティックな人間喜劇百物語――七十八年に生まれたとんでもない小説が、ジョルジュ・ペレックの『人生使用法』(水声社)だ。これはいわば、作家の究極の夢の実現だろう。多くの作家は内心抱いているはずなのだ。「できるだけたくさんの人物の視点から描かれる大きな世界の構築」という神に成りかわるがごとき野望を。
ペレック作品よりはずっと小規模とはいえ、その企みに挑んで楽しい読み心地を残すのが『フィンバーズ・ホテル』だ。ダブリンにある閉鎖間近の古びたホテルに泊まり合わせた人々、七つの部屋の七つの視点を中心に、一泊二日の時間を立体的に描くという、“グランド・ホテル”形式を採っている。しかも七人のアイルランド人作家によるオムニバス形式で。
たとえば、あなたが海外旅行に出て、どこかのホテルに泊まったとする。当然、あなたは他の泊まり客のことを知らない。ところが、別の部屋ではイギリス人老夫婦かなんかが、こんな会話を交わしているかもしれないのだ。
「向かいの部屋に泊まっている東洋人はシャネルを着てたわよ」「ずいぶん若そうなのに、どうしてそんな高い服を買う金があるのかね」「コールガールなんじゃないかしら」とか何とか。
袖振り合うも多生の縁という言葉があるけれど、人間は社会的な生き物だから、いつどこで誰とどんな形で関わり合うか、わからない。あなたのあずかり知らないところで、あなたが他者として息づいている瞬間もあり得るのだ。
ペレック作品やこのオムニバス小説はまさに、その多生の縁を描いている点が面白い。七つの人生の断片が単独に描かれているのではなく、それぞれがちょっとした形で互いの断片に重なり合う。各章の語り手によるセルフイメージだけではなく、他の章の語り手による客観的な視点が加わるから七つの人生の断片の奥行きが増す、そこが妙味なんである。旅先のホテルで隣室から聞こえる物音をBGMに読みたい一冊だ。
【この書評が収録されている書籍】
ペレック作品よりはずっと小規模とはいえ、その企みに挑んで楽しい読み心地を残すのが『フィンバーズ・ホテル』だ。ダブリンにある閉鎖間近の古びたホテルに泊まり合わせた人々、七つの部屋の七つの視点を中心に、一泊二日の時間を立体的に描くという、“グランド・ホテル”形式を採っている。しかも七人のアイルランド人作家によるオムニバス形式で。
たとえば、あなたが海外旅行に出て、どこかのホテルに泊まったとする。当然、あなたは他の泊まり客のことを知らない。ところが、別の部屋ではイギリス人老夫婦かなんかが、こんな会話を交わしているかもしれないのだ。
「向かいの部屋に泊まっている東洋人はシャネルを着てたわよ」「ずいぶん若そうなのに、どうしてそんな高い服を買う金があるのかね」「コールガールなんじゃないかしら」とか何とか。
袖振り合うも多生の縁という言葉があるけれど、人間は社会的な生き物だから、いつどこで誰とどんな形で関わり合うか、わからない。あなたのあずかり知らないところで、あなたが他者として息づいている瞬間もあり得るのだ。
ペレック作品やこのオムニバス小説はまさに、その多生の縁を描いている点が面白い。七つの人生の断片が単独に描かれているのではなく、それぞれがちょっとした形で互いの断片に重なり合う。各章の語り手によるセルフイメージだけではなく、他の章の語り手による客観的な視点が加わるから七つの人生の断片の奥行きが増す、そこが妙味なんである。旅先のホテルで隣室から聞こえる物音をBGMに読みたい一冊だ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする