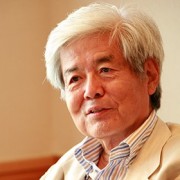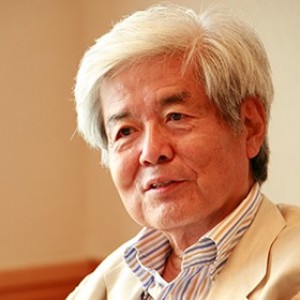書評
『ぼっちな食卓-限界家族と「個」の風景』(中央公論新社)
食卓調べ実証 「個の独立」実験中の日本
著者は食の研究ですでにいくつかの著書があり、ご存じの人も多いであろう。「食卓」とあるのは、食材とか栄養のような食物自体の問題ではなく、家庭での食事の在り方に関わる調査研究であることを示す。その結果、食卓から現代家族の実態をうかがうことができる。調査自体は三つの手続きに分けられる。一九六〇年以降生まれの主婦を対象として、まずアンケート、次に食卓の写真と家族各人の食卓の記録、三番目にそうしたデータを参考にした上で、個別の詳細な面接調査である。初回調査は一九九八年から二〇〇九年まで。
大変な調査だと思う。調査される側も、いろいろ面倒だと感じたに違いない。対象は最初は二四〇家庭、一〇年後には百余家庭、有効サンプルとしては八九、二〇年後には八。こう数を書くだけならなんということはないが、同じ家庭を二〇年以上にわたって追跡調査するのは、きわめて難しい。しかもその間、著者は得られたデータについて考え、解析する。そこで浮かび上がるのは、現代家族の在り方である。
全体は六部構成となっており、研究結果の考察に相当するので、統計数字が多出するわけでもなく、ごく読みやすい。研究書ではなく、一般書のつもりで読んで、まったく違和感はない。調査例の中から、著者が典型的と考えるものを選んで解説するから、話が具体的で、いわば「眼に見える」ようになる。
家族のそれぞれが好きなものを選んで、好きな時に、好きなように食べる。その背景となる考え方は「個の尊重」である。とくに子どもに嫌うものを無理に食べさせるのは、食事時間を楽しく過ごす邪魔になる。その種の躾は保育園や学校の給食に任せる。こうしたことは、子どもの教育に限らない。義父母への対応も似たようなものである。
教育におけるいわゆる「個性の尊重」が何を意味するのか、評者自身は長年悩んで来た。その接地点がこんなところにあったとは。現代の若者がしばしば問題とする「自分」は皮膚より中の身体、しかもその時々の軽い生理的欲求に始まる。現代の母親はそういうものをしっかりと認定し、育てている。
生まれてから死ぬまでを一貫する自分という概念は、最後の審判を前提とする一神教世界で成立する。たとえ死んでいても、最後の審判には個人として出なければならないからである。諸行無常の世界には、元来そういうものはない。時間的には天皇家や家制度に見るように、祖先と継続し現在的には周囲とつながる。最終的には、周囲の自然と一体化する。土から生まれて土に返る。
そうした古くからの思考装置を排除し、素直に独立の個を立てようとする。そんなことが可能かどうか、現代日本社会はそれを実験中だ。そう言うしかなかろう。事の成否を私は知らない。解答の義理もない。
このように、著者の調査はきわめて本質的な社会の問題を考えさせてしまう。なぜなら話が実証的で、大上段に振りかぶった思想から振り下ろされる上から目線ではないからである。現に自分が生きている日本社会の日常、それがどのように在るのかを着実に教えてくれる。
現代社会を考えようとする人にとって、本書は必読と言えよう。ChatGPTのように、記号操作が中心を占めかけている現代社会では、本書のように接地点が明瞭な作品は貴重である。どこにも接地しなくても、文章は書ける時代だからである。
本書の研究対象は主婦であるが、すでに著者は前作で「日本の主婦の五〇パーセントは、言っていることとやっていることが一八〇度違う」と述べており、それが裏づけられるのは食卓の写真を撮っているからである。本書でも、栄養や健康に関わる職種に就いている主婦が、教室の講義で述べることと、自宅の食卓がまったく一致しない複数例に触れているが、日本社会におけるいわゆるホンネとタテマエの分離の実例として興味深い。日本社会では立場によって言うべきことが決まっており、自分のホンネは立場上表明していることとは無関係でいいのである。こうした社会で言葉はどれだけ現実を規定するかという問題は常に評者を悩ませている。
我々は現に自分が生きている社会について、じつはかなり無知なのではないか。本書を読了して思う。無知はお前だけだろう、と言われそうだが、本書のような実証的研究が一般化しないのはなぜかと考えてしまう。とりあえず手数がかかってしょうがない。本書のような研究が定量的にも意味を持つようになるには、どれだけの調査が必要か。それを賄える予算がどこから出るか。
日常の食卓なんかより、もっと高級な概念を振り回して、空中戦を演じたほうが格好がいい。社会関係の学問がそれで動いていないことを望む。ともあれ評者自身にとっては、専門などと関係なく、大いに刺激的で参考になる書物であった。人間には興味がないといつも嘯いているが、日常は別である。どうしたって日常からは逃れられないからである。食卓はその典型であろう。
ALL REVIEWSをフォローする