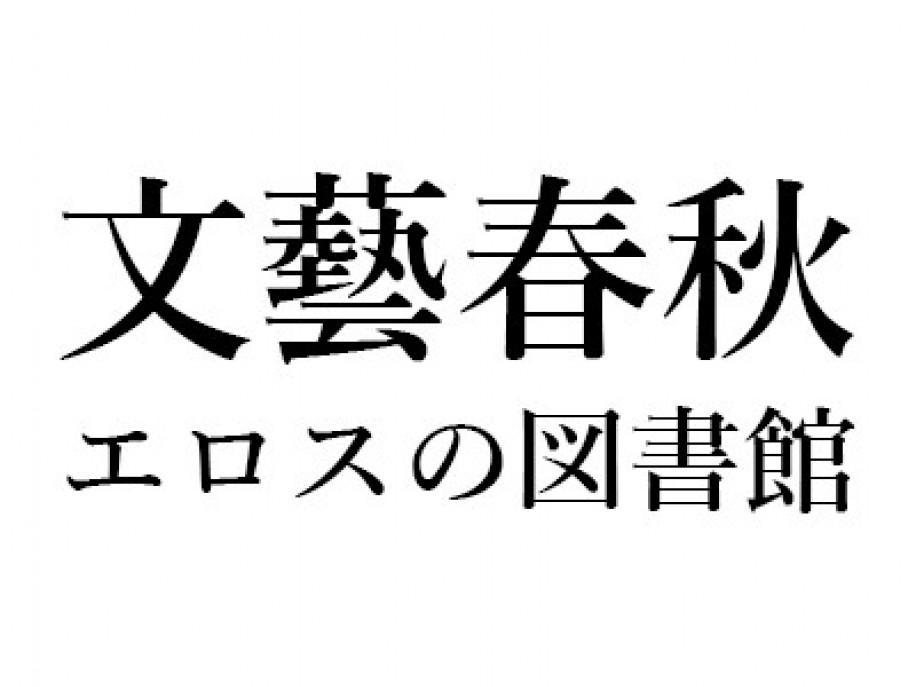書評
『ためない暮らし』(大和書房)
モノを「使い切る」コツ
身のまわりのモノはできるだけ少なく、簡素に静かに暮らしていたい。茶室が美しいのは、そこに余計なものが何もないからだ。炉にかけられた釜が静かに音をたてる(透木釜(すきぎがま)の季節ですね)。水指(みずさし)や棗(なつめ)、茶碗を運び入れて茶を点て、客が飲み終わると運び出す。茶室はまた何もない空間に戻る。
しかし現実はきびしい。だまっていてもモノが増えていく。あると便利だろうと思って買ったモノ。他人からのいただきモノ。いつか使うかもしれないと思って捨てられないモノ。モノがたくさんあっても、豊かになった気はしない。片づけ術、整理法を説いた本が売れるのは、誰もがこうした悩みを抱えているからだろう。不況なのにモノがいっぱい。胸がいっぱい、おなかもいっぱい。
有元葉子『ためない暮らし』は、不要なものをため込まないためのヒント集である。というよりも、思いつくままエッセイを書いていたら、結果的に「ためない」話が多くなったらしい。
料理研究家らしく、食材や調理器具、キッチンの話が参考になる。食材をいかにためず、むだにしないか。夏みかんはジャムに、水分が抜けかかったりんごはタルトタタンに。ぼくがグッときたのは、空煎りした大豆を味噌でからめた豆味噌。そうだ、大豆ならわが家の冷蔵庫にもたくさんあったはずだ。ぼくもつくってみようかな、と思わせる魅力がこの本にはある。
もっとも、有元葉子は所有することを否定するわけではない。たまった食材は廃棄するのではなく、腐敗する前に加工して、より長く食べやすくする。ストックの形態を変えてムダをなくすのだ。
「気持ちよく別れたい──おわりに」を読んでほっとした。「自分の持ち物を再点検してみると、買ったけれど今ひとつ満足感のない、つまり、使い切って命を全うしていない物も実はちらほらと目につきます」とある。ああ、有元葉子でもそうなのだ。「ためない暮らし」は理想であり、見果てぬ夢だ。
ALL REVIEWSをフォローする