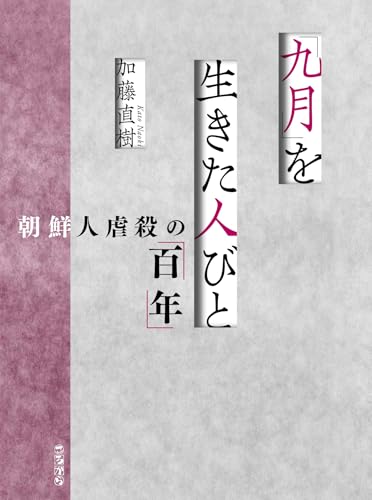書評
『桃花源の幻』(アストラハウス)
豊饒な中国文芸の伝統を現代につなぐ
現代中国文学を代表する作家の一人、格非による「江南三部作」。その第一部『桃花源の幻』(原題・「人面桃花」)は、2004年に刊行されるや絶賛され、第二部、三部とともにいくつもの賞を受賞している。評価は国内にとどまらず、2020年にアメリカで英訳が出版され、翌年の全米図書賞翻訳部門の最終候補になった。まず注目すべきは、物語としての群を抜いたおもしろさだろう。正気を失い閣楼(ゴーロウ)に軟禁されていた父・陸侃(ルーカン)が、ふらりと出て行ってしまうところから物語は始まる。その遠因ともされる「桃源図」の存在、父が残した「普済(プージー)にもうじき雨が降る」という言葉、唐代の詩人・李商隠の詩にある「金蟾(きんせん)(ひきがえる)」の書き間違えとされる「金蟬(きんせん)」。いくつもの印象的な謎が、読者を引きつける。
主人公は、初潮を迎えたばかりの少女・秀米(シュウミー)だ。江南の村・普済の大地主である陸家の一人娘が、動乱の時代に巻き込まれ(時代背景は辛亥(しんがい)革命前夜)、初めての恋をし、その相手を失い、匪賊にかどわかされ、尼僧と二人きりで小島の生活を送り、やがて革命の志士となり、桃源郷を夢見て行動し、夢破れて投獄され、声を失って帰郷する。波瀾万丈の一代記なのである。
しかし、この小説のほんとうの魅力は、物語のおもしろさに頼らない、洗練された語りにある。日本での秀米の革命家としての目覚めは、ほのめかしのように数行で語られるだけ。舞台は江南を離れようとせず、そのかわりに大胆に時をスリップさせ、村の有り様と変遷、そこに生きる人々を描き出す。人だけではない、風景と植物は丁寧に描きこまれ、読むものを百年前の中国南部地方に、軽々と連れて行ってくれるのだ。
ことに小説の終盤、秀米が丹念に世話をする花々の描写には心を奪われた。そして、それらが物語の初めのころに、秀米と張季元(ジャンジーユエン)が交わした『紅楼夢』の一節を思わせる花々だと思い出すとき、全編にくまなくちりばめられた中国古典文学や詩歌が、芳香のように立ち上ってきて、ただの衒学趣味ではない、作者の文学の本質への畏敬と愛着が、読み手にもあたたかさとともに伝わってくる。
主人公は秀米だが、全体の印象は群像劇であり、父・陸侃、張季元、匪賊の総元締め、秀米自身と、「桃源郷」を求めてはその幻に翻弄された人々の年代記でもある。またその一方で、秀米、喜鵲(シーチュエ)、翠蓮(ツイリエン)、韓六(ハンリュウ)といった女たちの、一種のシスターフッドの物語であるところも興味深い。陸家の女中に過ぎなかった喜鵲が、口を利かなくなった秀米のために字を覚え、やがて詩に開眼するくだりは、ほんとうに美しい。時代状況もあって、彼女たちは過酷な運命に抗えないが、それぞれ意思を持った存在としてくっきりと描かれている。
秀米の「桃源郷」の夢は潰えたが、レベッカ・ソルニットの言葉を借りれば、いわゆる「災害ユートピア」が、飢饉の年につかのま、それこそ幻のように立ち上がるエピソードも胸に残る。
1980年代にポストモダン作家として華麗なデビューを飾った格非が、豊饒な中国文芸の伝統を鮮やかに現代文学につなげた力作でもある。中国詩歌の引用に満ちた作品を見事な日本語に移し替えた訳業にも瞠目した。読後、一編の長い、長い詩を読み終えたような、余韻の残る読書だった。
ALL REVIEWSをフォローする