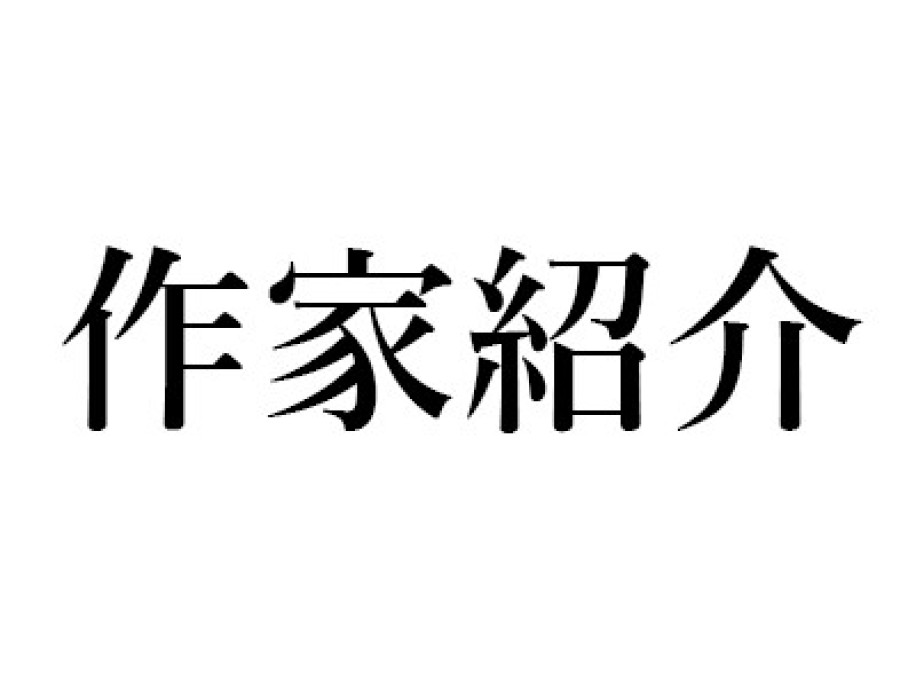書評
『白昼堂々』(講談社)
違法行為をしゃれのめす
昭和三十四年、というといまから三十七年前、北九州からはるばる上京した炭鉱出身の万引団が日本橋三越で犯行中に一斉検挙されるという事件があったらしい。エネルギー革命の大波をかぶって、炭鉱は深刻な不況のまっただなかだった。閉山があいつぎ、炭鉱労働者は容赦なしに首を切られ、路頭に迷っていた。結城昌治の『白昼堂々』は、その事件に着想を得て、昭和四十年に週刊誌に連載された。
話は、以前は一流のスリとして鳴らして、いまはデパートの保安係を実直に勤めている銀三の十三年ぶりの帰郷ではじまる。めざした故郷は、かつてはわが国随一の出炭量を誇った筑豊炭田のどまんなか、福岡県田川郡江間川町だが、廃虚同然にあれはてた炭鉱住宅を目の前にして、銀三は呆然とする。
気を取りなおした銀三は、ムショ暮らし時代に同業同郷のよしみで兄弟以上に親しみ、やはり十年前に足を洗って炭鉱(ヤマ)に帰っていた勝次をたずねあてる。
勝次は健在だったが、もちろん石炭を掘って食っていけてるわけはない。スリ、万引の元締めとなって仲間ともどもかつかつに食いつないでいた。勝次たちの窮状をみるにみかねて銀三は、デパートの呉服売場の反物を白昼堂々盗み出す妙案を口にする。
数ヵ月後、売場を見回り中の銀三の面前で、飲ませ屋・真打ち・吸いとり・幕(マク)・店(テン)びき・シケ張り、と集団万引の各役をそろえて、大胆不敵な犯行が繰り広げられる。啞然とする銀三の前に、でかし顔の勝次が立つ。
クライム・コメディーと作者はこの小説を呼んだそうだ。違法行為をしゃれのめすのはおおむね、書き手の上っ調子ばかりが気になって、シラけることが多いのに、この小説にはそれがないところがいい。
万引団の面々の風貌と言動がとにかくおかしい。ハゲ寅、マーチ、大耳、上海(シャンハイ)などの頼りにならない男たちのずっこけぶりにくわえて、泥棒小町の腰石よし子以下の女たちの度をこしたちゃっかりぶり、しっかりさ加減の対比の妙。連中が、笑いを取りにではなく、真剣に商品を盗りにきているだけに、なおさらおかしい。
その骨法は、人物だけでなく、さりげない文章にまで及んでいる。
「万引用語で盗むことをノムという。彼らがノミに行く先は、決して酒場ではない」
銀三の面前で、集団万引のデモンストレーションをやったあと、勝次は銀三を当のデパートの屋上に誘い、盗品の処分役になってくれとせがむ。銀三は返事をしないまま熱帯魚売場の水槽をみつづける。幼い娘と父親の会話が耳に入る。
「お魚はなぜ泳いでいるの」
「泳がなければ沈んでしまうじゃないか」
そのとき、銀三は急に鼻の奥がツーンとして、「引き受けよう」と返事する。
やがて警察が動きだし、知恵くらべ、根くらべの悪戦がつづき、ついに万引団は追いつめられる。窮地におちいってからの銀三の処世がまたおかしくて、絶品なのだが、それは読んでのおたのしみ。
単行本につけられた作者自身の「あとがき」がまた妙な味がある。面々の矜持や物語の後の身の振り方にまで気を配っていて、温かい。
作者は昭和二年に生まれ、平成八年に亡くなった。大きく割りをくった昭和一ケタ世代に属するが、晩年になるにつれて筆はいよいよ絶妙洒脱になっていった。辞世句が解説にのせられている。
「書き遺すことなどなくて涼しさよ」
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする